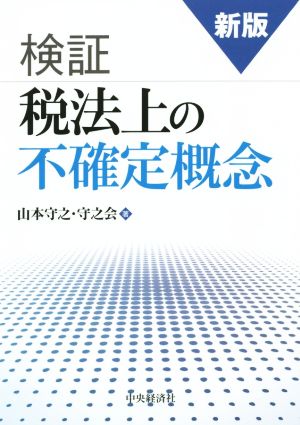
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-03-16
検証 税法上の不確定概念 新版
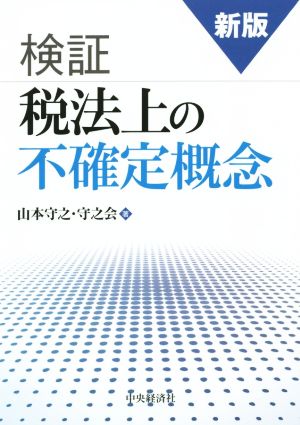
定価 ¥4,400
3,520円 定価より880円(19%)おトク
獲得ポイント32P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央経済社 |
| 発売年月日 | 2015/05/01 |
| JAN | 9784502141713 |
- 書籍
- 書籍
検証 税法上の不確定概念 新版
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
検証 税法上の不確定概念 新版
¥3,520
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
憲法84条では租税法律主義を規定しているが、この構成要素の一つに課税要件明確主義がある。課税要件明確主義とは課税要件を定める税法の規定も、その委任を受けた政省令の規定も可能な限り一義的でしかも明確でなければならないとするものである。しかしながら、課税要件明確主義を規定しているにも...
憲法84条では租税法律主義を規定しているが、この構成要素の一つに課税要件明確主義がある。課税要件明確主義とは課税要件を定める税法の規定も、その委任を受けた政省令の規定も可能な限り一義的でしかも明確でなければならないとするものである。しかしながら、課税要件明確主義を規定しているにもかかわらず、現行の租税法及びその委任を受けた政令、法令の解釈基準となる通達の中には「相当程度」「不当に減少」「正当な理由」など数多くの不確定概念が存在する。このような不確定な文言が税法上使用されているのは、法令通達等に明確な数値基準を設けると、その指標が一人歩きし、取引の背景を配慮した適正な法解釈を行う余地をなくし、画一的かつ無機質な執行がなされる恐れがあるためである。その点で不確定概念は課税庁の一方的な解釈に委ねられることなく弾力的な運用を担保していると言える。本書では過大役員給与の「不相当に高額」、同族会社の行為計算否認における「不当に減少」などについて制度趣旨から争われた裁判・裁決事例を引用し具体的に解説されていた。不確定概念については税務調査でも揉めるところなので本書を通じてしっかり押さえておきたいところだ。 P252 ②関西電力事件(消費税申告書の提出の失念と消費税の無申告加算税の賦課) ·平成17年9月16日大阪地裁判決税資255号順号10134 Z255-10134 消費税及び地方消費税につき、その確定申告期限である平成15年6月2日までに税額248億円余りを全額納付したものの、申告期限までに申告書を提出することを原告会社の担当者が失念していたことが判明し、6月13日になってようやく確定申告書を提出したところ、無申告加算税12億円余りが賦課された事例である。判決は、本件納付を国税通則法59条の予納として扱われたことによっても納付時点にさかのぼって消費税及び地方消費税に係る租税債務が消滅したものとは解することはできないとし、国税通則法66条が定める無申告加算税は行政上の制裁の一種であり、原告会社が法定申告期限までに申告していない義務違反があり、平成12年7月3日付けの事務運営指針に照らしても「正当な理由」がないとした。 もっともこの事案を契機として、平成18年度税制改正で国税通則法66条6項が付加されることとなり、法定申告期限から2週間以内に期限後申告書が提出され、期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されていたことなど一定の要件を満たす場合は無申告加算税を課さないこととされた。さらに、平成27年度税制改正で、「2週間以内」が「1月以内」に延長された。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
不確定概念を深く理解するのに非常に有益な本 不確定概念は、租税法律主義の課税要件確定主義と、税法に明確に規定することによって変動する経済に対してその適用が硬直的になるという相反する価値観の間に存在する →具体的な数値を通達に載せてしまうと、法益の保護ができなくなる可能性。 →ただし、法的安定性と納税者の予測可能性を確保する必要はある ・不確定概念 不相当に高額 相当期間 相当程度 通常要する 著しく不適当 やむを得ない 正当な理由 ・特徴 抽象性 経済環境の影響 多様性 ・租税法律主義の4つの内容 課税要件法定主義 課税要件明確主義 合法性の原則 手続的保証原則 ・通達の位置づけ ①租税法の法源ではない ②行政内部では拘束力を有する ③納税者に対しては拘束力を有しない ④裁判所の審査に対しては拘束力を有しない ・租税回避:通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的効果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること ヤフー事件に注目 ・役員給与の損金不算入制度:趣旨:お手盛りの防止→税負担回避目的防止→課税の公平の実現 役員報酬:職務執行の対価 役員賞与:利益をあげた功労への報い →損金不算入という見出しは、構造上仕方がないことであり、原則損金不算入という意味合いではない ・過大役員給与の「不相当に高額」:趣旨:お手盛りの防止→利益処分に帰すべきもの? ・同族会社の行為計算否認における「不当に減少」 2つの解釈 1、非同族対比説:同族会社だからこそなしうるならば、これを否認する 2、合理性基準説:経済人の行為として合理性があるか ・交際費等における不確定概念 交際費等課税の趣旨:法人の冗費、濫費抑制 3つの成立要件(有力説) 支出の目的 支出の相手方:事業に関係のある者の適用範囲は拡大しつつある(オリエンタルランド事件) 行為の様態 ・財産評価通達における「著しく不適当」 総則6項の適用における2つの流れ 1、路線価の時点調整や借地権の底地、貸家建付地の評価等にみる時価評価の適正性を問う流れ 2、税負担軽減・回避策に注目してその否認を目的とする流れ ・加算税が課されない場合の「正当な理由」 1、不可抗力説 2、不当・過酷事情説 3、帰責事由不存在説 4、故意・過失不存在説 5、比較衡量説 ・立証責任は、納税者が負うべき(民事訴訟法の規範説) ・不確定概念一覧表がある。便利
Posted by 



