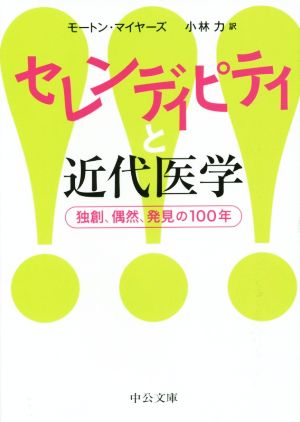
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
- 1224-25-01
セレンディピティと近代医学 独創、偶然、発見の100年 中公文庫
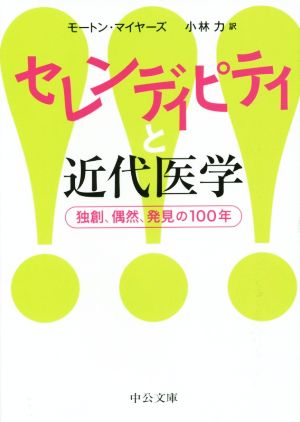
定価 ¥1,210
220円 定価より990円(81%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/12(月)~1/17(土)
店舗到着予定:1/12(月)~1/17(土)
店舗受取目安:1/12(月)~1/17(土)
店舗到着予定
1/12(月)~1/17

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/12(月)~1/17(土)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 2015/04/01 |
| JAN | 9784122061064 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
1/12(月)~1/17(土)
- 書籍
- 文庫
セレンディピティと近代医学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
セレンディピティと近代医学
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
本屋で見かけて。ペニシリン、抗がん剤、ピロリ菌など19~20世紀に発見された画期的な治療法がセレンディピティ(予想外で偶然の発見)であったこと書いた本。最終章が著者の主張で、最近の基礎研究の実施方法、特に国家的科学研究、論文のピアレビュー、製薬会社のマーケティング志向がセレンディ...
本屋で見かけて。ペニシリン、抗がん剤、ピロリ菌など19~20世紀に発見された画期的な治療法がセレンディピティ(予想外で偶然の発見)であったこと書いた本。最終章が著者の主張で、最近の基礎研究の実施方法、特に国家的科学研究、論文のピアレビュー、製薬会社のマーケティング志向がセレンディピティを阻害しており、画期的な医学的成果が得られにくくなっているので改善が必要と訴えている。 個人的にはセレンディピティが重要なのは当たり前という感覚なのだが、今の研究方法にも合理性があるのかもと逆に考えさせられた。例えば製薬会社のマーケティング志向については、人工知能や再生医療などの新分野に比べて古典的な製薬分野は成熟産業になっておりもう昔のような画期的な発見は期待できないと分析してる、とか。 事例の中では「39 幻覚剤LSDの物語」が劇的でおもしろかった。スイスの民間企業の一化学者アルベルト・ホフマンがよくぞ拾い上げた。 「その後1943年4月、彼は5年前に何かを見逃したかもしれないという「虫の知らせ」を感じ、ある朝LSD-25を新しく合成しなおした。午後には結晶を得る」(p373)
Posted by 
偶然だけど、運だけでない。準備して、コツコツ積み重ねてきて、誰もが気づけないところ。先入観を捨て、これ、むつかしい。
Posted by 
◆画期的なイノベーションとは、数多の失敗と、偶然というものが去来させるるもの。意外に見えるこの事実を、医学・薬学の発展過程を素描することで具体的に開陳する本書。是非、財政に携わる方々に熟読・味読してもらいたい◆ 2015年(底本2010年)刊行。 著者はニューヨーク州立大学スト...
◆画期的なイノベーションとは、数多の失敗と、偶然というものが去来させるるもの。意外に見えるこの事実を、医学・薬学の発展過程を素描することで具体的に開陳する本書。是非、財政に携わる方々に熟読・味読してもらいたい◆ 2015年(底本2010年)刊行。 著者はニューヨーク州立大学ストーニーブルック校医学部名誉教授(放射線科・内科)。 医学(というよりも、ここでは薬学かな。そういう意味では内科医らしい纏めではある)上の重大な発見は、計画化された研究、大規模プロジェクトと化した研究活動によるのではなく、偶然に得られた結論・観察結果と、その結論を何か異種の項目、目的外の要素とを結びつけることで創発されてきた。 その具体的実例を、細菌病理学、癌、循環器疾患、精神病理に区分けして叙述する書である。 重厚、そして豊富な具体例に圧倒される。 元よりここでは、単にこれらの発見をなした先人らの業績を称えることだけを目的とした書ではない。 結論の項にあるように、大規模プロジェクト、目的追求型プロジェクトでは、創発・イノベーティブ・革新的な知見は得られず、この事実を特に、金を配分する立場にある人間が理解しなければならないことを強く訴えかける書なのだ。 そしてこれは、研究開発というだけでなく、人材教育という側面においても同様に思いを致さねばならない事象であろう。 個人的には、大規模プロジェクトの持つ漸進的発見(未発見も含む)の長所も存在するとは思う。しかし、それで事足れりではない。 本書では、米国の政府他を批判しているが、同様の批判は日本(特に最近の、独立行政法人化の著しい時代相)にも妥当する。 そもそも失敗とは、成功にならない道筋を明らかにするために必要な上。失敗が文字通りの失敗とは限らないことは、本書列挙の実例が教えるところである。 一方、科学振興に金銭投資が不可欠な中、それが無意味か否かは、着手してある程度遂行しないと判明しない。つまり社会におけるイノベーティブにはムダ金が不可避な上、さらに無駄な失敗を繰り返させないため、失敗というものは、確実に社会に報告され、社会還元されるべきなのだ。 本書が、一部の分野に限ってではあるが、イノベーションの数多の例と、その偶発性(当然、成功より遥かに多くの失敗、イノベーションの結果を招来しない実例が存することが含意されている)を開陳して見せるのは、失敗を社会が許容しなければ、イノベーションはないのだという当たり前の事実を突きつけていると言っても過言ではないはず。
Posted by 


