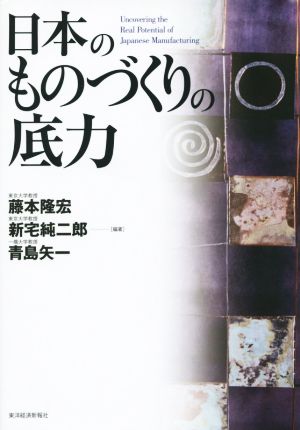
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1212-01-20
日本のものづくりの底力
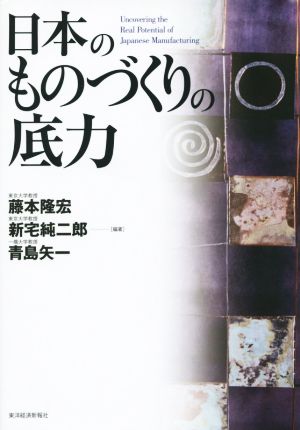
定価 ¥3,520
385円 定価より3,135円(89%)おトク
獲得ポイント3P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 2015/02/01 |
| JAN | 9784492522127 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
日本のものづくりの底力
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
日本のものづくりの底力
¥385
在庫あり
商品レビュー
3
1件のお客様レビュー
楠木教授の著書にたびたび登場する藤本隆宏氏が編著の書。 第1章は藤本氏自ら執筆。 「…『日本のものづくりは衰退した』と騒ぐ論説が多い。このような意見は、現場・企業・産業・経済の根本的な違いを無視し、『ものづくりは現場で起こる』という基本認識を欠いている。…特に直近20年の国内現場...
楠木教授の著書にたびたび登場する藤本隆宏氏が編著の書。 第1章は藤本氏自ら執筆。 「…『日本のものづくりは衰退した』と騒ぐ論説が多い。このような意見は、現場・企業・産業・経済の根本的な違いを無視し、『ものづくりは現場で起こる』という基本認識を欠いている。…特に直近20年の国内現場に注目すると、現場にとっては円高が進行するなか低賃金の隣国との過酷な競争を強いられた『暗黒時代』だった。しかし、これらのハンディを能力構築で克服して生き残り、なお生産性向上の大きな伸びしろを持つ国内の優良現場は、今後20年は、過去20年より存続の可能性が高まるだろう。内外賃金差が急速に縮小しているからである。」 先日日経新聞で中国の賃金と逆転したような記事も目にしたから、国内産業の空洞化に歯止めがかかり、著者の言うような状況になればと切に願う。 「企業の損益は、ものづくりの現場力だけでなく、戦略ミス、ライバルの動向、政府の政策ミス、運、その他競争環境などが複合的に作用する。企業業績の悪化と現場のものづくり力の低下は直結しない。」 言われてみればその通りだが、あまりこういう視点で語る人は少ないように思う。 第2章は小池和男氏。こちらも楠木教授お薦めに出てくる著者。 「もの造りの底力はまずは人材にある、…西欧、北欧、米、日をとわず、職場の人材の働きが生産性に大きく寄与していることがわかってきた。生産性の向上に大きく寄与したのは人材の活用の仕方だ、という研究がいまや欧米でめじろおしなのだ。その要因のほとんどを、日本はつよく持っている。」 そのような要因の真の勘所として、真に生産性に寄与する技能、チームだけでなく個人の動き、すぐれた個人にむくいる長期のインセンティブを挙げている。 その他、印象に残った箇所。 「戦略という観点から日本企業を眺めたとき、最も欠けているのは、会社の内部である『内』ではなく、競合企業や顧客そして協力企業を含むさまざまな利害関係者である『外』を動かす経営である。元来、競合企業や業界を動かす、競争の場を自分の土俵に持ってくる、そうした外部環境のマネジメントが『戦略』の目的である。自力を磨き上げる、高めることは重要であるが、他力を梃子にさらに自力を高めるという姿勢が重要であろう。… 業界の定義が変わり、競争相手が変わり、戦い方が変わるのが経営の世界の必然である。…複雑性への対処の難しさは、規模が拡大することで顕在化するだけでなく、外部環境の変化の早さによっても顕在化している。環境変化は従来にも増して高速化しているので、より迅速に戦略的な対応が求められている。複雑性の陥穽に落ちているとますます状況は悪化する。なるべく早くそれを打開する経営が求められている。」 「結果は衝撃的だった。1997年の金融危機の時期において、存続企業と退出企業とを比較すると、退出企業のほうが存続企業よりも生産性が高い、つまり生産性の高い企業のほうが退出しているという特異な状況が起こっていたことがわかったのである。 …効率の良い企業が退出し、効率の悪い企業が存続することは、『ゾンビ企業』の問題として広く知られることになった。」
Posted by 


