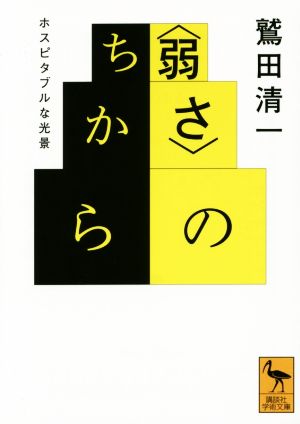
- 中古
- 書籍
- 文庫
〈弱さ〉のちから ホスピタブルな光景 講談社学術文庫
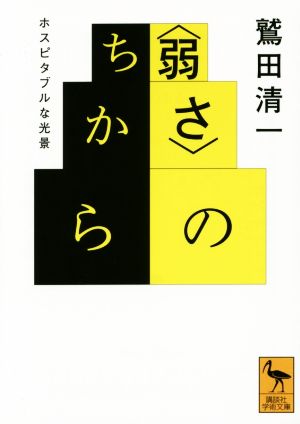
定価 ¥1,100
605円 定価より495円(44%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 講談社 |
| 発売年月日 | 2014/11/01 |
| JAN | 9784062922678 |
- 書籍
- 文庫
〈弱さ〉のちから ホスピタブルな光景
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
〈弱さ〉のちから ホスピタブルな光景
¥605
在庫なし
商品レビュー
4.2
7件のお客様レビュー
ディベートをさせると、震災の時に援助をすることを考える人は多くいるが、補助を受けさせるためにはどうすればいいのかを考える人がいないというのを読んでいて、確かにそうだなと思った。 色々な制度があったとしても、本当に必要な人にはその情報がいかないこともある。 そして、人は誰しも弱...
ディベートをさせると、震災の時に援助をすることを考える人は多くいるが、補助を受けさせるためにはどうすればいいのかを考える人がいないというのを読んでいて、確かにそうだなと思った。 色々な制度があったとしても、本当に必要な人にはその情報がいかないこともある。 そして、人は誰しも弱い部分がある。 その弱さを認めるということはとても大切で、それを力に変えられることができれば、とても強いエネルギーが出るのではないかと思った。
Posted by 
講談社学術文庫で、 鷲田清一氏の著作で、 タイトルが『〈弱さ〉のちから ホスピタブルな光景』。 お硬い本を予想して買ったんですが(もちろんどんなにかたいテーマでも優しく語ってくださるのが鷲田清一氏の本なのですが)、あにはからんや、鷲田氏が性感マッサージ嬢やゲイバーのマスターや生け...
講談社学術文庫で、 鷲田清一氏の著作で、 タイトルが『〈弱さ〉のちから ホスピタブルな光景』。 お硬い本を予想して買ったんですが(もちろんどんなにかたいテーマでも優しく語ってくださるのが鷲田清一氏の本なのですが)、あにはからんや、鷲田氏が性感マッサージ嬢やゲイバーのマスターや生け花作家など一癖も二癖もありそうな人に会いに行って、話を聞くという体裁の本。 でも(だから?)、これが深い。 それぞれのインタビューが、それぞれの生き方に裏打ちされて出てきた言葉の積み重ねだから、ちょっとやそっとじゃ「分からない」。 もちろんインタビューだから、書いてあることそのものが分からないわけじゃない。 でもその真意を探ろうとすると「分からない」。 こういうことかな、という感想は持てるけれど、たぶん違うな、少なくとも言わんとされていることを捉えきれていないなという感覚が残る。 だから深い。 何年かごとに、繰り返し読み返したいなと思いながら読みました。
Posted by 
あらゆる場面で見つけた弱さのちからをまとめた本。 精神科の病棟で見る患者は、この本にあるように”どう生きるかを、いつも目に見える形で突き詰めないと生きられない人たち”で、” 普通は人知れず悩むことを、過剰なまでに抱え込んできている人たち” 。その姿を見るうちに自分の歪さや弱さに...
あらゆる場面で見つけた弱さのちからをまとめた本。 精神科の病棟で見る患者は、この本にあるように”どう生きるかを、いつも目に見える形で突き詰めないと生きられない人たち”で、” 普通は人知れず悩むことを、過剰なまでに抱え込んできている人たち” 。その姿を見るうちに自分の歪さや弱さに気づく。精神科にいると、自分の過去を振り返ることにもなる、といった先輩医師の言葉通りであった。それから友人の脆さや作り上げた歪な自分らしさも少しずつ垣間見えるようになって、自分の生きづらさがほんの少しだけど肯定されたような気になった べてるの家では、精神疾患を治すものとして捉えない。 疾患で生じる苦労を治しても、他の苦労がある。人間が耐えきれない苦労を支える装置として、治療するのでなく会社を作った。 “人と競ったり、嘘をついたり、誰かになろうとした時、見ないようにしてきた大事なことを、病気のスイッチがちゃんと入る人たち。脆さを持った人たちが、いてくれることの大切さを考えた時に、とっても大事な存在だよね。社会にとっても大事だよね。” というように、地域の人もべてるの家の住人たちと交流することで、内に秘めていた、もしくは顕在化させてなかった悩みを話せるようになり、それは時に疾患のある患者よりも深刻であることもあった。 ひとはみな、歪な弱さを秘めている。それを補完していくことが人生の目的ではなく、その弱さのやりとりのなかで他人を内在化したり、自身を肯定することができるのでないか。 “人は転ぶ人をみると、無意識のうちに手を差し伸べる。 弱さは、それを前にしたひとの関心を引き出し、内にかすかな力を感じさせる。介助とは、おたがいにそのいのちを生かし合う、そういう関係を作り上げていくための窓口なのだ。” 医療者としても、1人の生きづらさを感じる人間としても、何度も立ち返りたい本だ。
Posted by 



