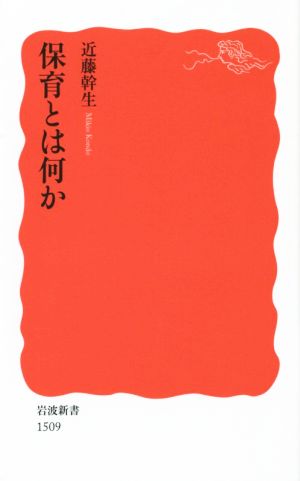
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-32-04
保育とは何か 岩波新書
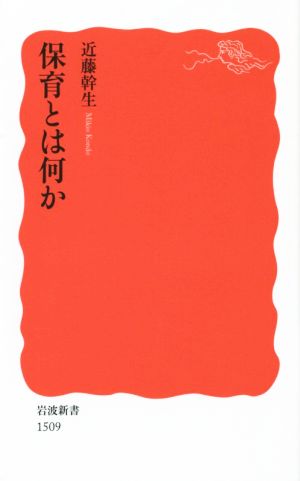
定価 ¥836
110円 定価より726円(86%)おトク
獲得ポイント1P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2014/10/01 |
| JAN | 9784004315094 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 新書
保育とは何か
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
保育とは何か
¥110
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.4
8件のお客様レビュー
この著作は、現代の保育にまつわる様々な問題について、網羅的に知ることができる 1冊である。内容は、待機児童問題、保育の現場で起こっていること、優れた保育園の実例紹介、子ども子育て支援新制度について、過去と現在の社会の変化による保育の変化、保育士の置かれている状況など。豊富な参考...
この著作は、現代の保育にまつわる様々な問題について、網羅的に知ることができる 1冊である。内容は、待機児童問題、保育の現場で起こっていること、優れた保育園の実例紹介、子ども子育て支援新制度について、過去と現在の社会の変化による保育の変化、保育士の置かれている状況など。豊富な参考文献が下支えとなっている良書である。 良書というのは、良きブックガイドになっていることも多いが、本書はまさにそうで、本書をきっかけに手に取る本を増やしていけば、より保育についての知見を深めていくことができるだろう。 著者は大学教授であるが、約30年に渡り保育士、園長を経験したスペシャリストでもある。だからこそ、第3章の「保育実践の輝き」で紹介される実例は、著者の人脈やフィールドワーク、現場を知るプロだからこそ着目できる保育園の豊かな実例に彩られている。 私自身が一番の読みどころと感じたのは、第5章で紹介される1970年代の子どもたちの姿である。ひたすら外遊びに明け暮れる子どもたちの様子が綴られる。最近ベネッセが行った意識調査では、約4割の保護者が、芸術・運動よりも勉強をしてほしいという結果が明らかになっているという。(インターネットで1万6千人が回答)。そういう意識が反映されているのか、子どもが外で思い切り遊ぶ姿というのは、都心においては、あまり見かけなくなっている気がする。 豊かな学びの土台には、遊びがあると著者は主張する。 現代は、電子機器が普及し、幼い頃からスマホに馴染む子どもがたくさんいる。 昔のように遊べる場所が激減し、危機意識から子どもを外で自由に遊ばせることに制限ができている現実もいたし方ないのかもしれない。 しかし、著者は直接的には述べていないが、社会でリーダーシップを取る人は、概ね子ども時代から遊び呆けてきた人だということを改めて認識したほうがよいと思う。 AIが本格的に登場し、生き残る職業、消滅する職業などど恐ろしい比較論も身近になってきている。機械が様々な面で労働を代替するからこそ、人間は人間にしかできないことに注力していくべきだと思う。 幼少期に外に出て遊ぶことというのは、社会にどのようなルールがあり、どんな危険があり、どんな楽しいことがあるのか。子どもだからこそもつ豊富な感性の元、喜怒哀楽の要素を身を持って知る又とない機会なのではないか。 実態を知らずに知識や情報を詰め込まれる子どもと日夜外に出かけていき様々な実物と出会っていく子どもと。どちらがたくましく育っていくだろうか。 極端な例かもしれないが、フィールドワークをする作家の書いたものとネットで調べたり、本で読んだ内容だけでものを書く作家。どちらのほうが面白いものを書くだろうか。 保育を考えることは、どういう社会を描いていくかを考えることに他ならないと思う。 藤井四段を見て、モンテッソーリ教育や将棋に関心を持つ親は多い。これは、自分の子どもには、社会を生き抜いていけるだけの知性を身に付けてほしい思いの表れだろう。 親が考えるべきは、子どもがのびのび遊ぶためにはどうしたらよいかを考えることかもしれない。
Posted by 
思い込みや視野の狭さが感じられる。学者っぽい感じ。たまたま知った保育所を理想のごとく書いていくのはいただけない。個別事例は客観的に書かないと説得力に欠ける。子ども・子育て支援新制度には精通していないようだ。
Posted by 
平成27年度から保育制度が新しくなるのにあたり、いまあらためて保育とはということを考えた本。保育制度とは、保育の現場、保育者(保育所保育士と幼稚園教諭)の課題など、今の保育にまつわるトピックを網羅的に取り上げられていると思います。保育について学びたい人におすすめですね。
Posted by 


