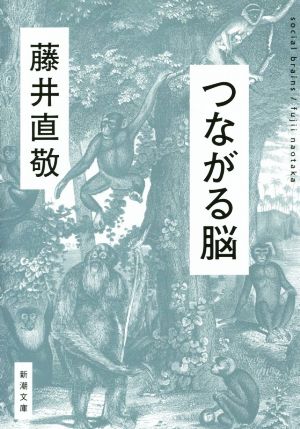
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
つながる脳 新潮文庫
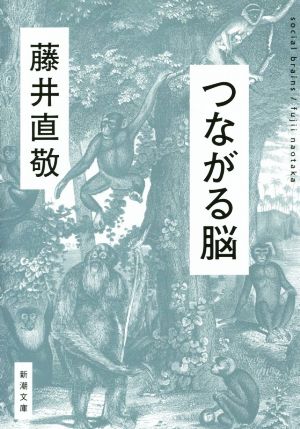
定価 ¥649
110円 定価より539円(83%)おトク
獲得ポイント1P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/7(金)~2/12(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社 |
| 発売年月日 | 2014/06/01 |
| JAN | 9784101259819 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/7(金)~2/12(水)
- 書籍
- 文庫
つながる脳
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
つながる脳
¥110
在庫あり
商品レビュー
3.3
11件のお客様レビュー
脳の高次認知機能を解明するには、脳を物質として事細かく切り刻んで実験しても本質には迫れないと思う。 そのため、筆者は、社会脳という、個体同士の繋がりの中に、意識を生む過程を探そうとする。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
これといった、決定打みたいな結論的箇所はあまりないのです。途上のなかでこう考えている、という著者の思考の流れを追体験するというか、共有するというか、そういう読書体験をしながら脳科学に触れる感じです。それでも、おもしろいトピックは多々出てきます。たとえば、<社会性とは「抑制」である>と著者が突き詰めて考えて得られた知見がありました。また、サルを使った実験での上下関係の発生状況を見ると、下位のサルほど頭を使うとも。つまり、賢いのは上に立った者よりも抑制して下位にいる者だと。社会性においての賢さですが。上位にいると頭を使わなくなる。下位の者を意識しなくなる。ということは傍若無人的姿勢になってしまうようなのです。人がいてもいないのと変わらないような脳の活動になるんだとか。一方、下位の者は上位の者を意識する。脳は抑制され、いろいろ考えだす。これは人間でも同様ではないかと思いました。以前目にしたツイートがソースではあるけれど、社長くらいになると洞察力や共感力が落ちるとあった。脳が下位の者を意識しなくなるから、頭も働かなくなる。これはサルの実験で見られたことと一緒ですよね。賢くありたいなら、できるだけ偉くならないほうがいいんでしょうね。重ねがさね書きますが、社会性においての賢さという意味で、です。初めは賢くて、そのうちいつか権力を手中にし、世の中をよくするために行使しようと考え、そうなっていく政治家がいるとして。いざ権力を手にした地位にあるときには、その権力と引き換えに初心に備わっていた賢さは消え去っているのかもしれない。……初心忘るべからず。聖書の「あなたがた皆の中で最も小さい者こそ、最も偉い者である。」という文言も、こうやって見ていくと、実は脳科学的に適合するような考え方じゃないかと思えてくる。「偉い者」が賢いから偉いとするならば、小さい者こそ社会的下位で、抑制された脳の状態で生きているのだから賢く、ゆえに偉い。社会性は抑制だ、というテーゼを受容して世の中をみてみると、どういう行動が反社会的なのかがいつもと違うわかりかたで見えてきます。すぐ偉く振る舞う人、マウンティングしてくる人なんかは、実は社会性がとぼしい脳の状態を欲しているのかなあ。社会性の賢さよりも、個人の利益を重視した賢さを選んでいるのかなと思う。最後の章では、脳科学の実験分野の話を離れて、社会性についての著者の論述が書かれています。幸せとはなにか、それはカネなのか、といったテーマに、明快かつうなずける論考がなされていました。人間とは不合理なものであることはわかりきっているのに、経済の世界では、合理的に判断していくのが人間(経済人)として規定され、それを元に社会が作られてきたと著者は説明します。金融工学が生まれたことは、それらを如実に物語っているのではないか。たとえばアメリカは、そういった合理性を重視する経済的(ビジネス重視)な国だけれども、そうやって人間個人の不合理に目をつむり社会の合理性を最優先した結果、不合理な人間同士で営む結婚生活などは、離婚率が50%ほどにまでなっている。他にもこの部分を読んでいて僕が気になったのは、アメリカの犯罪率の高さと薬物依存などが、こういった人間の不合理性を大事にしない代償なのではないかということでした。生きづらくない社会を構築するには、今後、不合理性の扱いをどうするかが大きなポイントなのかもしれません。著者は、そこのところは、トップダウンではなく、ボトムアップで探っていく方が向いているのではないかとの意見を述べていました。僕も賛同するところです。
Posted by 
研究者としての挫折から、研究対象を変え、他者との関係を脳科学的なアプローチで解き明かす。実験の仕方は猿を用いたもの。専門的な話はほとんど交えず、実験方法もイラスト付きで分かりやすい。これを読んでいると、人間なんて然程猿と変わらないと感じてしまう。 印象に残ったのは、お金という概...
研究者としての挫折から、研究対象を変え、他者との関係を脳科学的なアプローチで解き明かす。実験の仕方は猿を用いたもの。専門的な話はほとんど交えず、実験方法もイラスト付きで分かりやすい。これを読んでいると、人間なんて然程猿と変わらないと感じてしまう。 印象に残ったのは、お金という概念ができる前から、人にはインセンティブとして働く概念があったはず。それが承認欲求だという言葉だ。お金そのものは、擬似承認の代替機能を持つ。本質は何か、考えさせられる。
Posted by 


