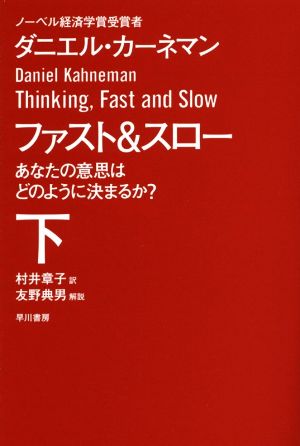
- 中古
- 書籍
- 文庫
ファスト&スロー(下) あなたの意思はどのように決まるか? ハヤカワ文庫NF
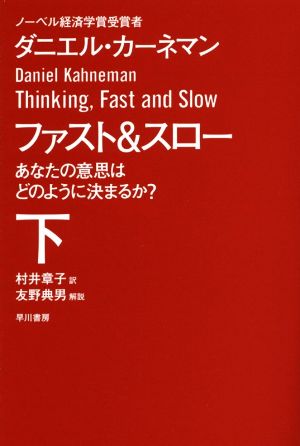
定価 ¥924
880円 定価より44円(4%)おトク
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 早川書房 |
| 発売年月日 | 2014/06/20 |
| JAN | 9784150504113 |
- 書籍
- 文庫
ファスト&スロー(下)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ファスト&スロー(下)
¥880
在庫なし
商品レビュー
4.2
83件のお客様レビュー
Fastである思考(直感的)であるシステム1と、Slowな思考(論理的)であるシステム2という概念を導入して、信じられないほどの実験結果と、自分ならどう回答するだろうかという誠実な内省の積み重ねによって、驚くべき発見をいくつもしている。 このレベルで、このサンプル数で数々の実験...
Fastである思考(直感的)であるシステム1と、Slowな思考(論理的)であるシステム2という概念を導入して、信じられないほどの実験結果と、自分ならどう回答するだろうかという誠実な内省の積み重ねによって、驚くべき発見をいくつもしている。 このレベルで、このサンプル数で数々の実験を提示されると、これが本当の心理学か…と感じる。
Posted by 
システム1(早い思考)とシステム2(遅い思考)が存在し、熟考するには システム2の呼び出しが必要になることを知った 普段考えることが面倒と感じるが、何食べるかいつも時間をかけて悩んでるのでこういう時だけシステム2が呼び出されてるんだなって感じた
Posted by 
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1826915682539446656?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
Posted by 



