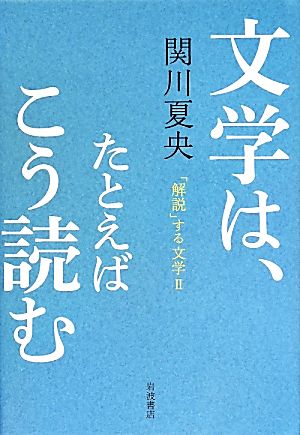
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-01-01
文学は、たとえばこう読む 「解説」する文学 Ⅱ
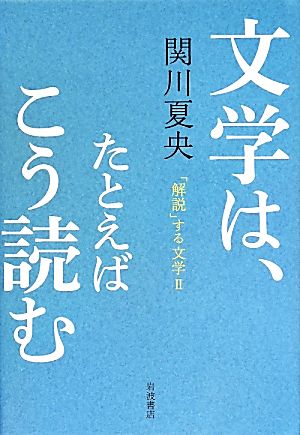
定価 ¥1,980
990円 定価より990円(50%)おトク
獲得ポイント9P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2014/05/29 |
| JAN | 9784000246958 |
- 書籍
- 書籍
文学は、たとえばこう読む
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
文学は、たとえばこう読む
¥990
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
3件のお客様レビュー
関川夏央は、本書のあとがきで、文庫本の「解説」の役割について、下記の通り書いている。 【引用】 遠い昔、文庫本の「解説」にはお世話になった。「解説」なしでは作家と作品の関係が見えず、またその本の歴史的な位置づけができなかった。 【引用終わり】 関川夏央にとって、文庫本の解説は...
関川夏央は、本書のあとがきで、文庫本の「解説」の役割について、下記の通り書いている。 【引用】 遠い昔、文庫本の「解説」にはお世話になった。「解説」なしでは作家と作品の関係が見えず、またその本の歴史的な位置づけができなかった。 【引用終わり】 関川夏央にとって、文庫本の解説は従って、少なくとも、「作家と作品との関係を示すこと」「その作品の歴史的な位置づけを示すこと」が役割として求められている。そのためには、その作家がどういう作家で、どういう作品を書いてきたのか、その中でこの作品はどういう意味合いを持つのか、あるいは、その作家が活躍した時代とはどういう時代だったのか、逆に言えば、その作家が時代からどのような影響を受けていたのか、等が示されていることが必要だ。確かに、このような「解説」がなされていれば、その作品を味わい、理解するのに助けになる。 関川夏央は、多くの文庫本の解説を書いているが、このような考えを持って、解説を書いてきたのである。 そして、「"解説"はもう少し長く読まれてよかろう。仕事の報われなさに少なからぬ不満を抱いていた」のであるが、これまで関川夏央が書いた解説を、書籍の形にする提案を出版社から受け、「喜んで応じた」のである。この本はそのようにして生まれた「"解説"する文学」シリーズの2冊目であり、これまで関川夏央が書いた文庫本の解説で構成されている。 1冊目は既に感想を書いているが、司馬遼太郎の「司馬遼太郎対話選集」全10巻の解説が多くの割合を占めている。私は、この「司馬遼太郎対話選集」という本を読んだことがないが、関川夏央の「解説」を読むことにより、司馬遼太郎がどのような作家であったかの一端を知ることが出来たし、また、その「解説」だけを楽しみながら読むことが出来た。「解説はもう少し長く読まれてよかろう」という関川夏央の不満には一定の根拠があるのだ。 2冊目の本書では、ナンシー関、河口俊彦、内田樹、伊丹十三、佐野洋子といった作家による、私が読んだことがある作品の解説があり、それは読んだ本を思い出しながら「解説」を楽しんだ。佐野洋子の「死ぬ気まんまん」に至っては、関川夏央が佐野洋子から彼女の癌が転移したことを打ち明けられる場面から「解説」が始まっている。まさに「死ぬ気まんまん」がどのように書かれたかを間際で見て知っていた者しか知り得ない情報を含めて「解説」が書かれており、作品理解にはこれ以上の「解説」は考えにくい。 その他の「解説」も楽しく読んだのは1冊目と同じであり、いくつかの本は、実際に読んでみたいとも思った。この「解説」本は、ブックガイドとしての役割も果たしているのだ。
Posted by 
「生き証人」だなと思った。いや、なんらかの事件に立ち会ったわけではないが、この著者は本を頭で読んでいない、と思ったのだ。身体で受け留め、その身体から全身で言葉を発している(抽象的でスカした言い方になるが)。思想信条としては保守的でアナクロニズムと位置づけられうるのだろうこの著者は...
「生き証人」だなと思った。いや、なんらかの事件に立ち会ったわけではないが、この著者は本を頭で読んでいない、と思ったのだ。身体で受け留め、その身体から全身で言葉を発している(抽象的でスカした言い方になるが)。思想信条としては保守的でアナクロニズムと位置づけられうるのだろうこの著者はしかし、凡庸な感傷に流れることなく身体に刻み込んだ読書体験や実体験を駆使して一冊の本とガチンコで勝負し、そこから言葉を発しようとしている。故に、斬新というか珍奇な結論はない。が、読み応えあり。良心的なオヤジのハードボイルドな解説集
Posted by 
一冊目の「解説する文学」と同じ趣向というか、関川さんの仕事の集成なんだけれど、ちょっと緩んでいる感じがして残念だった。ただ佐野洋子の作品評は心打たれた。まあ、もちろん彼女の作品のファンであることや、彼女の最期の日々を撮ったドキュメンタリー映画があったと思うが、それをぼくは残念に...
一冊目の「解説する文学」と同じ趣向というか、関川さんの仕事の集成なんだけれど、ちょっと緩んでいる感じがして残念だった。ただ佐野洋子の作品評は心打たれた。まあ、もちろん彼女の作品のファンであることや、彼女の最期の日々を撮ったドキュメンタリー映画があったと思うが、それをぼくは残念に思っていた。そういうことがあったから、関川さんの佐野評にホッとしたということかもしれない。 韓国や朝鮮に関する作品に対する彼のポジションというか、考え方は、やはり勉強になった。 読んだ本が多かったが、もういいど読もうかと思ったのは、佐野洋子だけだったというのが、結局のところこの本に対するぼくの評価だったということだ。
Posted by 



