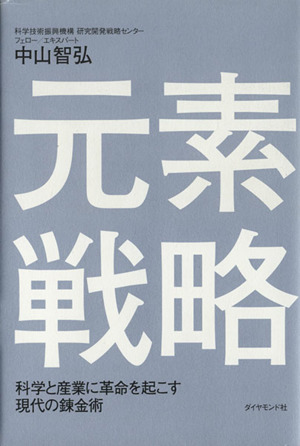
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1212-01-23
元素戦略 科学と産業に革命を起こす現代の錬金術
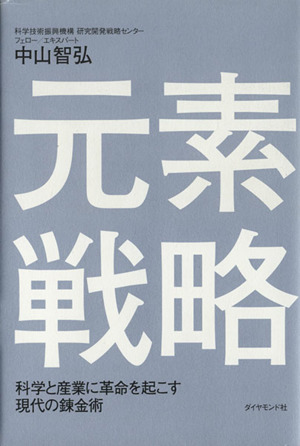
定価 ¥2,090
220円 定価より1,870円(89%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ダイヤモンド社 |
| 発売年月日 | 2013/11/25 |
| JAN | 9784478023372 |
- 書籍
- 書籍
元素戦略
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
元素戦略
¥220
在庫なし
商品レビュー
4.4
5件のお客様レビュー
日本の元素戦略とは何か。何故、必要か。どんな体制、プロジェクトや組織を、どんな研究者がテーマにしているのか。科学的な話だけではなく、政治的な中身に触れ、戦略全体がよくわかる良書。元素の基本もおさらいできる。 想定しておく元素危機とは。例えば、自動車産業のハイブリット車電気自動車...
日本の元素戦略とは何か。何故、必要か。どんな体制、プロジェクトや組織を、どんな研究者がテーマにしているのか。科学的な話だけではなく、政治的な中身に触れ、戦略全体がよくわかる良書。元素の基本もおさらいできる。 想定しておく元素危機とは。例えば、自動車産業のハイブリット車電気自動車では必ずネオジム磁石が使われている。このネオジム磁石には希少元素のジスプロシウムが欠かせない。液晶テレビ、有機ELテレビ、太陽電池にはITOと呼ばれる透明電極が使われているが、ここにもインジウムと言う希少元素。鉄鋼業でも、ニオブ。ガラスの研磨材であるセリウム。これはキャノンやニコンなどの高級レンズの件まやハードディスクのガラス基盤の研磨にも使われている。希少元素は、産業の必需品である。 しかし、この希少元素は、中国や南アフリカなどの海外に多く、依存している。1992年、鄧小平が「中東に石油があるように、中国にはレアアースがある」と述べたように、少なくとも中国では既に経済政策にも戦略的に取り入れられている。 そこで、元素戦略。その研究テーマの一つである元素間融合とは、現代版錬金術そのもの。元素Aと元素Cを混ぜるとその真ん中に位置する元素Bの性質を持つ元素を作ることができる。 そもそも、レアアースは、ランタノイド系とスカンジウム、イットリウムを合わせた17元素。レアメタルは、これに更にボロンやチタンなどを含む47元素。レアメタルとは産業への流通量が少ない金属系元素の事で、日本の経済産業省の造語。海外ではマイナーメタルと呼ぶのだが、恥ずかしながら、レアメタルの由来を知らなかった。 学び多し。願わくば、本著で紹介された研究テーマが更に発展し、日本が成果を享受できるように。
Posted by 
160109 中央図書館 電気自動車EVには、ジスプロシウムを用いたネオジム磁石が欠かせない。液晶や太陽電池にはインジウムが、鋼鉄にはニオブが必要だ。こういった希少元素に頼った工業は、先々のリスクが無視できない。 よって、鉄、アルミニウム、亜鉛など「汎用元素」でできるかぎり代替で...
160109 中央図書館 電気自動車EVには、ジスプロシウムを用いたネオジム磁石が欠かせない。液晶や太陽電池にはインジウムが、鋼鉄にはニオブが必要だ。こういった希少元素に頼った工業は、先々のリスクが無視できない。 よって、鉄、アルミニウム、亜鉛など「汎用元素」でできるかぎり代替できないか、という化学素材技術が、今後ますます注目される。
Posted by 
レアメタル、レアアースのような希少元素の代替、削減を目標にした日本の現段階での取り組みがまとめられている。もちろん詳細な成果や情報は機密情報のため書けないだろうが、単純に読み物として面白い。官庁の壁を破った組織設定、そして元素戦略に至るまでのストーリー。著者の元素戦略に懸ける思い...
レアメタル、レアアースのような希少元素の代替、削減を目標にした日本の現段階での取り組みがまとめられている。もちろん詳細な成果や情報は機密情報のため書けないだろうが、単純に読み物として面白い。官庁の壁を破った組織設定、そして元素戦略に至るまでのストーリー。著者の元素戦略に懸ける思いが伝わってきます。
Posted by 



