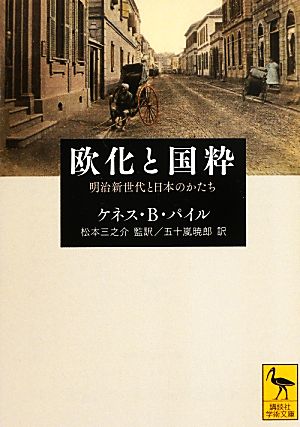
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-26-01
欧化と国粋 明治新世代と日本のかたち 講談社学術文庫2174
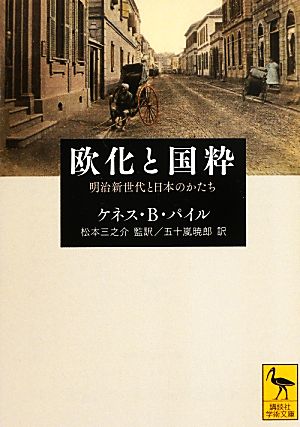
定価 ¥1,210
1,100円 定価より110円(9%)おトク
獲得ポイント10P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 講談社 |
| 発売年月日 | 2013/06/12 |
| JAN | 9784062921749 |
- 書籍
- 文庫
欧化と国粋
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
欧化と国粋
¥1,100
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
たまたま,外出先に持参した本が読み終わってしまい,書店で見つけた本。こういう場合は場当たり的に妥協して本を購入することが多いが,今回は本書を見つけられたことに感謝をしたくらい。 本書は講談社学芸文庫に収められているが,元は1986年に社会思想社から刊行されている。なんと,原著は1...
たまたま,外出先に持参した本が読み終わってしまい,書店で見つけた本。こういう場合は場当たり的に妥協して本を購入することが多いが,今回は本書を見つけられたことに感謝をしたくらい。 本書は講談社学芸文庫に収められているが,元は1986年に社会思想社から刊行されている。なんと,原著は1969年出版。なぜ,私が本書を手にとり,購入したかというと,西川長夫『国境の越え方』(筑摩書房,1992年)の4章が「欧化と回帰」と題し,日本は明治以降の近代化の過程で,欧化という欧米文化を吸収する時期と,回帰という日本人の元来の性質を見つめ直す時期とが交互に行き来するという議論をしているからだ。章のタイトルは回帰だが,当時ナショナリティの訳語として用いられていた国粋も何度も登場する。そして,『欧化と回帰』に登場する国粋主義者の陸 羯南と三宅雪嶺の名も『国境の越え方』で知ったのだ。しかし,改めて『国境の越え方』をめくってみると,本書は引かれていない。まあ,ともかく目次をみてみましょう。 序章 第一章 新しい世代 第二章 明治青年と欧化主義 第三章 日本人のアイデンティティをめぐる諸問題 第四章 国民意識の苦悩 第五章 条約改正と民族自決 第六章 精神的保証を求めて 第七章 国民的使命の探求 第八章 戦争と自己発見 第九章 日本の歴史的苦境 本書は非常に素晴らしい日本史研究である。正直いって,西川氏の本では,陸や三宅という国粋主義を標榜し,『日本人』という雑誌や『日本』という新聞を発行していたという事実は分かったものの,その内実についてはちょっとよく分からなかった。 しかし本書では,陸と三宅と,『日本風景論』の著者として地理学では有名な志賀重昂の3人の日本主義者がなぜ登場したのかということを,その前の欧化主義者,徳富蘇峰を対比させることで,非常に明快に論じている。しかも,その議論は非常に丁寧で,厳密に史料に基づいており,訳文も併せて,とても原著が1960年代に出たものとは思えない。まさに,この時代に講談社学術文庫に収められるべく本である。 本書を読むと,アンダーソンが『想像の共同体』でインドネシアなど旧植民地でのナショナリズムのあり方を議論していたことを思い出す。日本は植民地にはならなかったが,急速な近代化のなかで欧米文化の吸収によって新しい近代国歌として生まれ変わったわけだが,その後なぜ天皇を中心とする内向きの力が働き,軍国主義のもと拡張戦争へと突入していったのか,いまいち理解できていなかったのだが,本書でその一面を垣間見たような気がする。そして,内村鑑三のような人物が,キリスト教に深く心酔しながらも,日本国に対する忠誠を持っていたのかということについてもヒントを得たような気がする。 本書には直接的に書かれていないが,日本人が国粋思想というものをこの時代に得たのは,やはり国粋という言葉自体がナショナリティの翻訳語だったように,自分自身の国民アイデンティティを求めるという発想自体を欧米から学んだのではないかと考えた。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ケネス・B・パイル(松本三之介監訳、五十嵐暁郎訳)『欧化と国粋 明治新世代と日本のかたち』講談社学術文庫、読了。現在まで全てを規定する西欧文明。明治日本のショックは並大抵ではない。本書は初めて西洋型教育を受けた明治最初期の知識人の論争から国民意識確立の苦悶の系譜を浮かび上がらせる。 著者が注目するのは内発的欧化主義を唱える(初期)の徳富蘇峰、民友社に反発し国粋保存を訴える志賀重昂や陸羯南、三宅雪嶺らの言説を対比する。ハードだけでなくソフトまで西洋であることが一等国の条件であった時代(条約改正前)、日本人とは何を意味していたのか。 欧化こそ「すべての進歩した国々が則る発展の定まった普遍的な型」とみるのか。先祖返りが無意味の時、「進歩と文化的自律性が両立し得ること」を示してみせることは可能なのか。日本の近代化を素材にその軌跡描く本書は時代の転換期だからこそ読まれたい。 文庫版あとがき。本書は現在の「上滑りするナショナリズムを自省する上でも、また隣国ナショナリズムを理解する上でも、さらに国際的な状況に順応しながらナショナル・アイデンティティを保とうとすることの意味を考える場合に参考になる」(五十嵐)。
Posted by 



