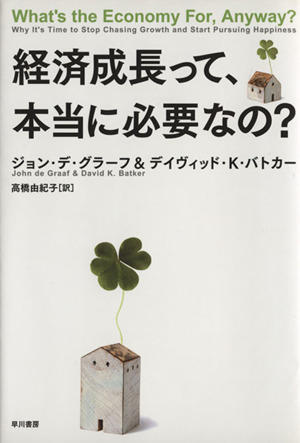
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-12
経済成長って、本当に必要なの?
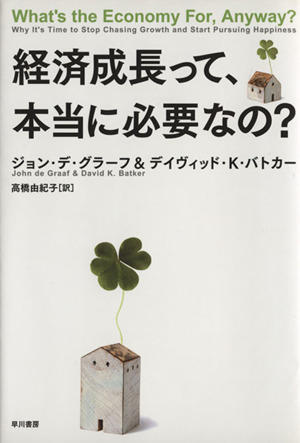
定価 ¥2,200
220円 定価より1,980円(90%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗到着予定:2/27(金)~3/4(水)

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/27(金)~3/4(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 早川書房 |
| 発売年月日 | 2013/05/11 |
| JAN | 9784152093714 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/27(金)~3/4(水)
- 書籍
- 書籍
経済成長って、本当に必要なの?
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
経済成長って、本当に必要なの?
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.3
6件のお客様レビュー
2020.7.19 68 よかった。gdpという指標の意味。 フレキシュキリティ デンマークなど ドイツ 労使の協同決定 環境や教育を織り込んでいく。 オイルこぼしたり、犯罪増えて刑務所で金使ったりもGDP UPする。GDPとの向き合い方。
Posted by 
経済成長が、幸せをもたらす。そんな神話が壊れてきている。貧富の差の拡大、長時間労働、物質的に豊かでも精神的には満たされない暮らし、金融危機、環境破壊など、経済成長だけでは、解決できない課題が、山積みとなっている。 功利主義者ベンサムは「最大多数の最大幸福」を経済の本当の目的である...
経済成長が、幸せをもたらす。そんな神話が壊れてきている。貧富の差の拡大、長時間労働、物質的に豊かでも精神的には満たされない暮らし、金融危機、環境破壊など、経済成長だけでは、解決できない課題が、山積みとなっている。 功利主義者ベンサムは「最大多数の最大幸福」を経済の本当の目的であると主張したが、現在は「最大幸福を、最大多数に、できるだけ長期間にわたってもたらす」ことよりいっそう重要となっている。 経済成長が暴走させないようにしっかりと見ていきたい。
Posted by 
資本主義経済の限界については多くの書籍に書かれていて、自分自身でも感じています。 「では次に来るのはどんな世界なのだろう?」という疑問があり、関連する図書を継続して読んでいます。 この本は、アメリカ人のドキュメンタリー番組の制作等に関わっている作家と経済学者による共著。 そもそも...
資本主義経済の限界については多くの書籍に書かれていて、自分自身でも感じています。 「では次に来るのはどんな世界なのだろう?」という疑問があり、関連する図書を継続して読んでいます。 この本は、アメリカ人のドキュメンタリー番組の制作等に関わっている作家と経済学者による共著。 そもそも経済とは何のためにあるのか、という基本的な問いかけを読者に投げかけた上で、まずはGDPという現在の「尺度」の問題点を指摘します。 その上で、「最大幸福を」「最大多数に」「できるだけ長期間に」提供するという視点で、現在のアメリカという国の課題を挙げて、今後どうしていくべきかという提案をしています。 全体を通じて、アメリカという国の問題をアメリカ国民に問いかけるような構成になっていること、そして提案よりも課題提起にページがさかれているので、日本人の僕には当事者意識が持ちづらいように感じました。 しかし日本という国にも共通する問題も多く、特に資本について「物的」「自然」「金融」という形に分けてとらえるという考え方は参考になりました。 世界を牽引するアメリカという国も、多くの課題があり、多くの悩みを抱えているのですね。 この分野については、継続して勉強していきたいと思います。
Posted by 


