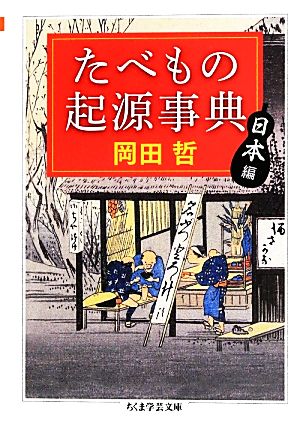
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-02-00
たべもの起源事典 日本編 ちくま学芸文庫
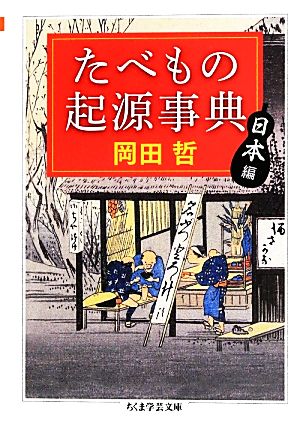
定価 ¥2,420
1,925円 定価より495円(20%)おトク
獲得ポイント17P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2013/05/10 |
| JAN | 9784480095237 |
- 書籍
- 文庫
たべもの起源事典 日本編
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
たべもの起源事典 日本編
¥1,925
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.5
3件のお客様レビュー
800ページにも及ぶ食べ物の起源。しかし索引はない。読み物、なのか? 僕の地元名物の「安倍川餅(阿倍川餅、という表記だったが)」もあれば、「飴」などの一般的なものもある(飴のほうが記述が長い)。 「味噌カツ」とか、「ホルモン焼き」とか、新し目っぽいものもある。 「鮎...
800ページにも及ぶ食べ物の起源。しかし索引はない。読み物、なのか? 僕の地元名物の「安倍川餅(阿倍川餅、という表記だったが)」もあれば、「飴」などの一般的なものもある(飴のほうが記述が長い)。 「味噌カツ」とか、「ホルモン焼き」とか、新し目っぽいものもある。 「鮎」「セロリ」まあ、起源を追うかどうかは別として、たべもの、だ。 「穀物神」農耕社会での女性を投影したもの…だが食べたことはない。というか実物を見たことも、まだない。 「自動炊飯器」…見たことある、が、まだ食べたことがない。今後も食べないと思う。 「パン祖」江川太郎左衛門。世界遺産になった韮山反射炉を作った人。兵糧のためにパンを作り、それがきっかけで日本にパンが広がったらしい。僕パン好きじゃない。こいつのせいだったのか…。やはり食べたことがない。 と、ちょっと茶化して書いてしまったが、何が出てくるかな、という楽しみがある。もちろん普通の食べ物の起源も満載である。知らなくても食えるけど、知ってたほうが楽しいじゃん。
Posted by 
いろんな食べ物に関する起源(薀蓄?)が書かれていて良い読み物になる。 wikipediaを読んでたら時間が経ってたの如く、こちらも興味本位でパラパラ読んでたら止まらない感じだ。 「イカナゴの釘煮」が無くてそこが残念だった。
Posted by 
・辞書好きだから、ちよつと変はつた辞書を見つけるとすぐに買ひたくなつてしまふ。この岡田哲「たべもの起源事典 日本編」(ちくま学芸文庫)も同様であつた。元版は東京堂の事典である。「はじめに」が平成15年の日付であるから、初版から10年で文庫化といふことであらうか。辞書としては早いの...
・辞書好きだから、ちよつと変はつた辞書を見つけるとすぐに買ひたくなつてしまふ。この岡田哲「たべもの起源事典 日本編」(ちくま学芸文庫)も同様であつた。元版は東京堂の事典である。「はじめに」が平成15年の日付であるから、初版から10年で文庫化といふことであらうか。辞書としては早いの ではないかと思ふ。それだけ売れたのであらう。個人的には辞書の文庫化大歓迎である。東京堂の辞書が文庫に入るなんてとも思ふが、そんな時代なのであらう。拡大再生産ならぬ、縮小再版の時代なのである。そんなありがたい時代にはずいぶん前からなつてゐる……。 ・内容は書名通りである。「本書は、私たちの今日の食卓を構成するたべものについて、素材・料理法・料理・調理器具・什器・様式・用語・制度などから、日本人の食文化に関わりの深い1400語を選択し、その起源発生についてまとめた。」(「凡例」3頁)といふものである。単に食べ物だけの事典ではない。例へば蕎麦屋に庵号が多いのはなぜかといふ項目(「庵号」36頁)がある。寺が関係してゐるらしい。普通の国語辞典では「庵号」といふ項目はあつても、ここまで詳しい説明はない。ならば「軒号」はと思つて引くと、これはない。数詞以上の意味は見出せないのであらうか。これを不徹底と言ふべきかどうかは私には分からない。ただ、こんなことを考へさせてくれるのは、さすが、食べ物の事典である。試みに東三河関連の項目を探してみる。例へば、菜飯田楽は「なめし」 に「愛知県豊橋市の名物飯(中略)市内には、文政年間創業の云々」(534~535頁)とある。この店、やはりそれなりに有名なのである。田楽の項は一般的な説明に終始して個別の説明はない。同じく味噌関連で「ごへいもち」、この漢字は「五平餅」とあるが、説明中には「御幣餅」もある。「長野・岐阜・愛知 の各県で知られる郷土菓子(中略)民間信仰に関わる興味深い食べ物である。」(243頁)こんなことを書かれると何か違和感がある。あれは菓子なのだらうか。私の感覚ではファストフードと言ふならともかく、菓子は無理である。木曽の串団子風のはお菓子かもしれないが、こちらの御幣型のは御幣餅定食のやうな メニューがあるくらゐだから、お菓子はかなり無理がある。民間信仰については、この祖型たる伊那の狗賓餅(ごひんもち)を言ふのであらうか。私はこれを知 らない。御幣といふ表記であつても、それは宛字だと思つてゐる。民間信仰と正面から言はれてしまふと、少なくとも私の感覚とは違ふと思ふ。更に、近くの豊川稲荷に関連して「いなりずし」、この漢字は稲荷鮓とある。詳細な説明の後に、「日本三大稲荷の一つ、豊橋の豊川稲荷一帯では、稲荷ずしが盛んである。」 (52頁)とある。これだけであるが、やはりをかしい。あれは豊川にあるから豊川稲荷なのである。古来、豊橋と豊川は別の町である。それを「豊橋の豊川稲 荷一帯」と言はれては地元の人間ならずともをかしいと思ふはずである。もしかしたら豊橋駅の駅弁として有名な稲荷寿司を思ひ浮かべてかう書いたのかもしれない。それにしても曖昧、舌足らずな記述で、豊川から見たら何と失礼なといふことになりさうである。こんなことを書いてゐると、この事典、専門性はあるが 記述の信頼性はどうなのかといふことになる。郷土料理はもちろん、全国的な料理でも様々に理解のできるものがある。その旨をすべて記してあれば良い。さう でないと誤解を招く。あるいは違和感を感じさせる。結局、本書はかういふ点を承知したうへで調べ物に使ふなり、読み物として読むのが良ささうな事典であらう。それでも私はおもしろいと思ふ。
Posted by 



