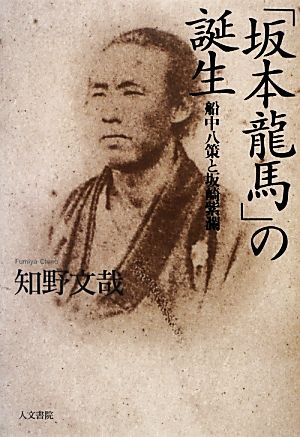
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-09
「坂本龍馬」の誕生 船中八策と坂崎紫瀾
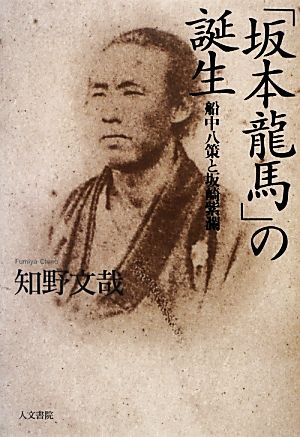
定価 ¥2,860
1,980円 定価より880円(30%)おトク
獲得ポイント18P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 人文書院 |
| 発売年月日 | 2013/02/15 |
| JAN | 9784409520581 |
- 書籍
- 書籍
「坂本龍馬」の誕生
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
「坂本龍馬」の誕生
¥1,980
在庫なし
商品レビュー
3.8
4件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
船中八策の実在性を歴史資料に基づき追跡している テキストは明治29年 弘松宣枝「坂本龍馬」に掲載 された「建議案十一ヶ条」を坂崎紫瀾が箇条書きに して、当初詳細不明とあった3条を無い事にして八 箇条の形式にし、明治40年宮内省「殉難録稿 坂本 直柔」が採録して史実となった 船中八策の名称は大正5年が初出 名将から逆算して何時・誰との時に策が練られたか なり、後藤・坂本の二人が誕生に居合わせた説は・・・ たぶん、マチガイだよね (´・ω・`)
Posted by 
所収論稿は「『船中八策』の物語」「土佐勤王党の物語―坂崎紫瀾『汗血千里の駒』」「瑞山会の物語―瑞山会編『坂本龍馬傳艸稿」。 「船中八策」を中心に今日人口に膾炙している坂本龍馬の事績・逸話の虚構性を緻密な史料批判で暴いている。土佐派の民権家で後に維新史料編纂にも関与する坂崎紫...
所収論稿は「『船中八策』の物語」「土佐勤王党の物語―坂崎紫瀾『汗血千里の駒』」「瑞山会の物語―瑞山会編『坂本龍馬傳艸稿」。 「船中八策」を中心に今日人口に膾炙している坂本龍馬の事績・逸話の虚構性を緻密な史料批判で暴いている。土佐派の民権家で後に維新史料編纂にも関与する坂崎紫瀾や、旧「土佐勤王党」顕彰組織「瑞山会」による政治的・恣意的な「坂本龍馬」像が浮かび上がる。専門的な考証に終始する一方、時々口語調を交えて文体をあえて軽くしているが、かえって読みにくいのが残念。
Posted by 
前半は「船中八策」の元ネタはどれかについて、後半は龍馬とその関係者の虚像が、坂崎紫瀾作『汗血千里の駒』等の著作を通じて、どのように形成されていったかを述べている。 前半と後半を比較すると、後半の方が断然はぎれがよく、面白い。 後半では、トリビア的な意外なエピソードが続出し、へえ...
前半は「船中八策」の元ネタはどれかについて、後半は龍馬とその関係者の虚像が、坂崎紫瀾作『汗血千里の駒』等の著作を通じて、どのように形成されていったかを述べている。 前半と後半を比較すると、後半の方が断然はぎれがよく、面白い。 後半では、トリビア的な意外なエピソードが続出し、へええと思うことばかり。例えばおりょうと龍馬の「新婚旅行」や自由恋愛・結婚の様子も、女権運動にかかわっていた紫瀾の描写に負うところが大きいという。また「土佐勤王党」という名称も、紫瀾の創作の疑いが濃い 等など。 だがこの後半部分の真骨頂は、坂崎紫瀾の意図の分析にある。『汗血~』の連載時の意図としては、板垣退助や後藤象二郎こそが土佐における倒幕運動、ひいては自由民権運動の正嫡であることを、土佐勤王党が自由党の母であるように描き出すことによって強調しようとしていたのだという。紫瀾は板垣チルドレンともいうべき立場で、大変政治的な意図をもってこの小説を連載した。だから龍馬は実は、土佐勤王党の物語の一部でしかなかった。しかし連載から本になるにあたって、編集者によって龍馬以外の勤王党メンバーの話はばっさりけずられて龍馬中心の物語になり、それが大ヒットしてしまったので、現代にまで通じる龍馬の虚像ができてしまったということらしい。そしてこの系譜が、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』にもつながっていく。 龍馬が非常に自由闊達、リベラルで、現代人にも通じるようなモダンな気質をもってる、というようなイメージを、我々がもってしまってるのも、自由民権運動の文脈に置かれたからこそなのだなあと実感する。もちろん、実際には真逆の人だったとは思わないが、後世の人の解釈の力に負うところは大きいだろう。 前半の船中八策の部分は、丁寧に史料を比較してるものの、書き方が整理されておらず読みづらいのが難点。・船中八策のもととなった文書はどのようなものがあるのか・それらの文書の信ぴょう性・その内容は龍馬の独創なのか・それらがどのような影響関係をもっていたのか・そもそも龍馬の大政奉還への考えはどのようなものだったのか などがごちゃまぜになっている。読みながら自分で論点を整理するのに骨がおれた。
Posted by 



