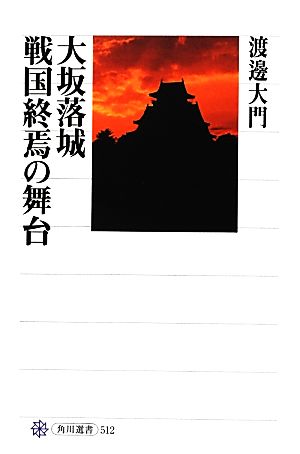
- 中古
- 書籍
- 書籍
大坂落城 戦国終焉の舞台 角川選書512
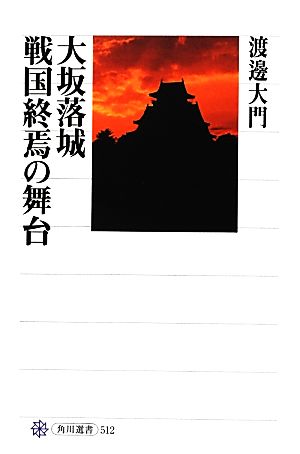
定価 ¥1,980
220円 定価より1,760円(88%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 角川学芸出版/角川グループパブリッシング |
| 発売年月日 | 2012/09/24 |
| JAN | 9784047035126 |
- 書籍
- 書籍
大坂落城 戦国終焉の舞台
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
大坂落城 戦国終焉の舞台
¥220
在庫なし
商品レビュー
2.8
5件のお客様レビュー
信長、秀吉、家康、 一番最初に買ってもらった本はこの三人の自伝だったんです。 戦国時代にタイムスリップして実際の現場でどうであったか確認してみたい。
Posted by 
専門知識のない私でも分かりやすく読めた。 この本を読む限り、大坂の陣が始まる前にもう豊臣方は負けていたのだという印象。特に夏の陣。もう流れが戦う方向に行っちゃってたから戦争回避なんてとてもできなかったよ、ということなのかなあ。しかし勝つ見込みがほとんど見えないで戦いに赴くなんて、...
専門知識のない私でも分かりやすく読めた。 この本を読む限り、大坂の陣が始まる前にもう豊臣方は負けていたのだという印象。特に夏の陣。もう流れが戦う方向に行っちゃってたから戦争回避なんてとてもできなかったよ、ということなのかなあ。しかし勝つ見込みがほとんど見えないで戦いに赴くなんて、いくら武士といえど辛かっただろうなあ。浪人勢はそれでも最後のチャンスと頑張れただろうけど。 徳川家康(と秀忠もかな)からは前もっての準備の大切さを学びましたよね・・・(全く完成していない明日のプレゼン資料を横目で見ながら) いやはやしかし関ヶ原も大坂の陣も複雑怪奇だね。今に至るまで多くの人が惹きつけられるだけある。
Posted by 
戦国時代が終わったのはいつなのかは議論が分かれるかと思いますが、私は「大坂夏の陣」で豊臣家が滅んだ時点だと思っています。 但し、この戦いは全ての大名が徳川側に味方したので、勝敗は始めから決まっていたようですね。もっとも、真田軍が徳川家康の本陣に攻め入って番狂わせがおきそうになっ...
戦国時代が終わったのはいつなのかは議論が分かれるかと思いますが、私は「大坂夏の陣」で豊臣家が滅んだ時点だと思っています。 但し、この戦いは全ての大名が徳川側に味方したので、勝敗は始めから決まっていたようですね。もっとも、真田軍が徳川家康の本陣に攻め入って番狂わせがおきそうになったそうですが、残念ながらこの本では詳しく取り上げられていませんでしたが。 戦国時代を象徴する戦いとして一番面白いのは、「関ヶ原の戦い」だと思います。私たちは結果を知っているので、徳川が多くの裏工作等をして有利だったと思っていますが、この時は日本の大名は両者に分かれて戦っていますし、石田三成の戦略も素晴らしかったと思います。 この本では、関ヶ原の戦いに始まって、大坂夏の陣までを通して解説してくれています。こうして見ると、歴史というのは一本の糸で繋がっているのだなと感じることができました。 この本を読んで思ったのは、戦国時代らしい「浪人」が世の中にあふれていたのは、北条氏との戦い(小田原の戦)までのようだとわかりました(p99)、このあたりが戦国時代なのかもしれませんね。 以下は気になったポイントです。 ・関ヶ原の戦いで没収・削封された領地は、632万石に及び(毛利、上杉、佐竹等)、約520万石は東軍に与した豊臣系武将に与えられた、135万石は徳川の直轄地(蔵入地)となった(p13、26) ・織田信長の孫である織田秀信はキリシタン大名として有名、岐阜城下には立派な教会があった、秀信は西軍に味方したので高野山へ追放(後に高野山からも追放)された(p25) ・秀頼の所領高は全国各地に散在する蔵入地を含めて220万石あったが、関ヶ原の戦い後には65万石(摂津・河内・和泉)となった(p30) ・1611年頃から豊臣恩顧の大名は死亡した、加藤清正(1611.6)池田輝政(1613.1)浅野幸長(1613.8)前田利長(1614.5)、残ったのは福島正則程度(p65) ・大坂冬の陣で秀頼の主力は、関ヶ原の戦いで敗れて浪人になったもの(p91) ・大名や家臣に使える者を奉公人というが、1)名字を持ち、武士に寄子・被官として奉公する侍、足軽、2)名字を持たない中間・小者、3)隷属した労働力の下人、に分類される、1)と2)まで(p98) ・北条氏滅亡により、1590.12には、秀吉は浪人を禁止し、村から追放するように命じた(p99) ・現在の大阪市平野区に所在した平野郷は、戦国期においては堺と並ぶ自治都市として知られていた(p106) ・大阪の陣が始まる前には、米の値段は、約7-8倍へ値上がりした(p113) ・大坂冬の陣が終わった時の合意では、二の丸・三の丸の埋め立ては豊臣方が行う予定であった(p142) ・豊臣方の大野治房は、堺に入り、徳川方に与したという理由で焼き払われた(p166) ・大阪城の焼け跡からは、金:2.8万枚、銀:2.4万枚が回収された(p178) ・大阪の陣は関ヶ原の戦いと比較して、「労多くして益少ない」戦いであった、秀頼の65万石を13名の大名で分け合った(p182) ・豊臣家の滅亡は、戦国で活躍した浪人衆や、多くの信者を獲得したキリシタンが終わりを迎えたもの象徴的であった(p214) 2012年11月23日作成
Posted by 



