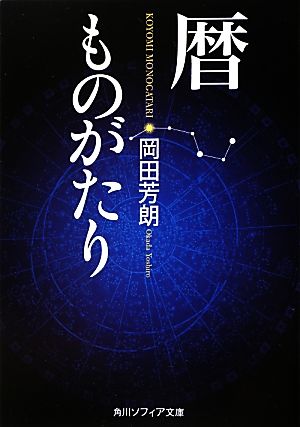
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-26-01
暦ものがたり 角川ソフィア文庫
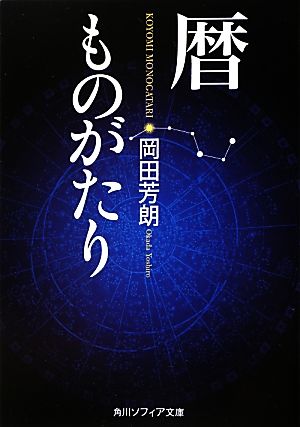
定価 ¥836
495円 定価より341円(40%)おトク
獲得ポイント4P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 角川学芸出版/角川グループパブリッシング |
| 発売年月日 | 2012/08/25 |
| JAN | 9784044064280 |
- 書籍
- 文庫
暦ものがたり
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
暦ものがたり
¥495
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3
3件のお客様レビュー
Posted by 
・岡田芳朗「暦ものがたり」(角川文庫)は、「あとがき」によれば、「年代順に章を立てており、通読していただければほぼ日本における暦の変遷をご理解いただけるもの」(273頁)である。ただ暦の歴史を述べてゐるだけでなく、暦にまつわる様々なことにも触れてをり、いささか大袈裟だが、カバーの...
・岡田芳朗「暦ものがたり」(角川文庫)は、「あとがき」によれば、「年代順に章を立てており、通読していただければほぼ日本における暦の変遷をご理解いただけるもの」(273頁)である。ただ暦の歴史を述べてゐるだけでなく、暦にまつわる様々なことにも触れてをり、いささか大袈裟だが、カバーの「時代を映す暦の森羅万象がわかる!」といふのもあながちまちがひではない。暦の専門家や暦に縁の深い歴史家ででもなければ、このくらゐの暦の知識があれば十分であらうと思はれる。古代から近代まで、自然暦から太陰暦、太陽暦、更には皇紀まで、暦の「通史ではない」(同前)が、いささか「硬い本」(275頁「文庫版あとがき」)である。正直なところ、前半の近世以前のあたりは全く身近ではないゆゑにいささか読みづらい。それでも平安朝の日記と暦の関係等はおもしろく読める。それが貞享暦あたりからおもしろくなる。所謂旧暦で生きてゐなくとも、それなりに旧暦が身の回りにあり、その現行の所謂旧暦は、江戸時代の4回の改暦の最後の暦による 「天保暦もどき」(274頁同)だからである。 ・天保といふのは文政の後で、明治維新まで30年といふ頃である。この少し前、「享和から文化頃」に「完全に現行のものと一致する形になったの」(206頁)が六曜である。六曜といふのは、暦の新旧を問はず、現代の生活にも深く関はつてゐる大安、仏滅等々といふあれである。これは気にするしないにかかはらず、慶弔中心に非常に広く使はれるので相当古くからあるのだらうと思つてしまふのだが、実は「六曜・ 九星・三隣亡は(中略)新しく登場したもので、さほど歴史の古くない」(200頁)ものであるといふ。九星は塚本邦雄が「六白嬉遊曲」な どといふのを編んでゐるが、私はほとんどこれを知らない。三隣亡も日めくり等に書いてあるのは知つてゐるが、それ以上は知らない。六曜は世間がそれを許さないところがあつて、筆者の言によれば、「いわばあやふやな『旧暦』によって六曜をはじめとして、種々の暦註が割付けられており、庶民はそれを一生懸命信奉している」(216頁)やうな状態であるから、なかなか気にせずにゐることはできない。では、いつかうなつたのか。「六曜は幕末頃にはかなり普及した占日法」(209頁)で、それも限定的に「勝負事や投機的な目的に用いられたもの」(同 前)であつたらしい。ところが明治維新以後、公許の官暦がおもしろくないといふので私製の贋暦が流行り、そこで用ゐられたのが六曜等であつた。これが庶民に受け入れられて現在に至るのである。先に引用したやうに、その昔の六曜の形、つまり用語は現在と同じものではない。意味も違ふ。そもそも最初の六曜は唐代に発案された(201頁)と言はれる「時刻の吉凶を占うもので」(202頁)あつた。そこでは大安や赤口が使はれてをり、日本でも天保頃までは使はれたらしい。ところが江戸に入つて以後、これが「日の占いに変り、解釈も日本独自のものが行われるようになり、元禄・正徳以後に今日のような順序に変化したものか」(206頁)といふ。さうして文化頃には用語も現行のものとなつたのである。新しいといへば確かに新しい。しかも非科学的である。それでもかういふものが使はれるてゐるのが現状だが、それを筆者の先の引用のやうに言つて良いものかどうか。筆者は「文庫版あとがき」で「やや硬い文章になっている部分もある。」(274頁)と書く。これなどもその類であらうか。私には所謂上から目線のやうに思へる。さういふところさへ気にしなければ、本書は暦に関はるかなりを知ることのできる重宝な書である。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
著者は、日本史、殊に暦についてを専門にしてきた人だという。 プロフィルによると、その道に進んだきっかけは、神武天皇の紀元の計算方法に疑問を持ったことだそうだ。 本書第二章にも、その話が出てくる。 ここか一番、目からウロコの話だった。 聖徳太子は、隋と対等な国交関係を築こうとして、中国で権威のあった「讖緯説」により建国の年代を定めた。 まだ若い国家だとして軽視されないよう、後漢の鄭玄の説に則り、当時(推古天皇九年)から、1260年遡ったところを神武天皇の建国と定めた、というのだ。 そのために、当時残っている伝承と整合的な説明が出来ず、国史の編纂者たちは混乱して、天皇をやたらに長寿することでつじつまを合わせたのだ、と。 それ以外にも、面白い話はたくさんある。 大学の日本史の講義で聞いた、明治の改暦も、聞いた以上に詳しく説明されていて、満足。
Posted by 



