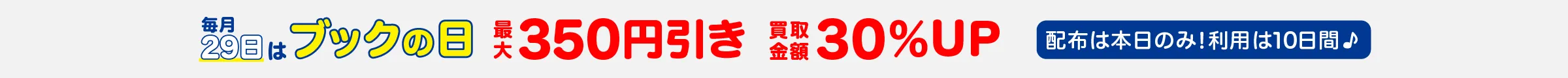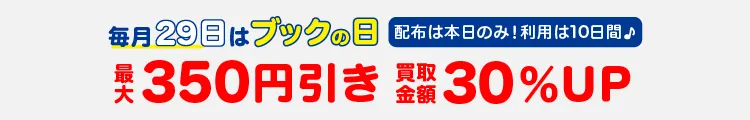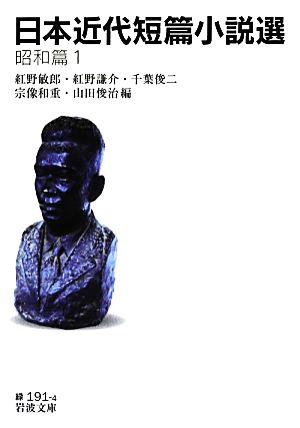
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
- 1225-06-02
日本近代短篇小説選 昭和篇(1) 岩波文庫
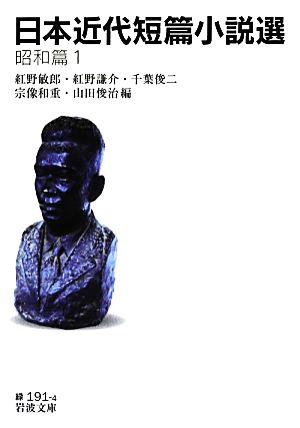
定価 ¥1,155
385円 定価より770円(66%)おトク
獲得ポイント3P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗到着予定:3/4(水)~3/9(月)

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
3/4(水)~3/9(月)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2012/08/20 |
| JAN | 9784003119143 |
- 書籍
- 文庫
日本近代短篇小説選 昭和篇(1)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
日本近代短篇小説選 昭和篇(1)
¥385
在庫あり
商品レビュー
3.8
7件のお客様レビュー
鯉 井伏鱒二 キャラメル工場から 佐多稲子 死の素描 堀辰雄 機械 横光利一 いのちの初夜 北條民雄 家霊 岡本かの子 待つ 太宰治 文字禍 中島敦
Posted by 
佐多稲子を本書で初めて知った。「キャラメル工場から」は昭和期の貧困家庭の少女の苦悩をよく描いている。中学生ぐらいの少女が工場に働きに出て家計を支えようとする姿は切実である。令和の一読者としては本作が貧困を基軸に書かれた小説に見えるが、これが「プロレタリア文学」と解釈される当時の...
佐多稲子を本書で初めて知った。「キャラメル工場から」は昭和期の貧困家庭の少女の苦悩をよく描いている。中学生ぐらいの少女が工場に働きに出て家計を支えようとする姿は切実である。令和の一読者としては本作が貧困を基軸に書かれた小説に見えるが、これが「プロレタリア文学」と解釈される当時の時代であれば少し話が変わってくる。プロレタリア文学としてこの作品を読むとすれば、この少女の貧困の姿から同情や悲哀といった弱々しい感情を持つのではなく、社会変革への勇気や階級そのものへの思慮が浮かび上がるべきなのかもしれない。 小林多喜二の「母たち」はかなりプロレタリア的だ。作中に描かれる母たちは社会主義活動によって投獄された活動家の母親である。特攻警察に対してその怒りをぶちまける母たちの口調、そして彼女らが示す憤怒といえる強い感情は、これもまた現代では見られないものだ。令和の時代ならば、警察権力に対して怒鳴り散らす行為は気狂いとも思われかねない。しかし、権力への服従と抑圧されている状況を良しとせず、真正面から対峙する母親達のような姿勢は現代おいて過剰なほどに薄れすぎてはいないか。 「機械」、「いのちの初夜」は有名かつ名作で、これらの作品をまた読ませてくれる点で本書は素晴らしいが、もっといいことは前述のようなあまり知られていない作家や埋もれている名作に触れる機会をつくっていることだろう。
Posted by 
『キャラメル工場から』は、作者である佐多稲子の境遇と重なる部分が多い作品。貧困や女性の労働について考えさせられた。
Posted by