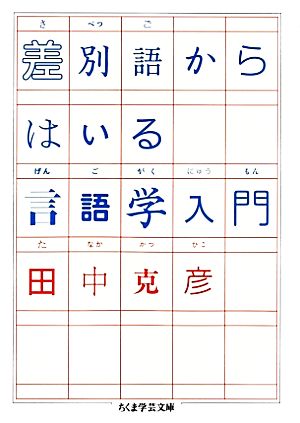
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
差別語からはいる言語学入門 ちくま学芸文庫
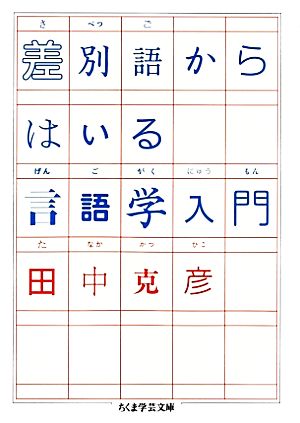
定価 ¥1,100
330円 定価より770円(70%)おトク
獲得ポイント3P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
11/26(火)~12/1(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2012/06/08 |
| JAN | 9784480094629 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
11/26(火)~12/1(日)
- 書籍
- 文庫
差別語からはいる言語学入門
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
差別語からはいる言語学入門
¥330
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.6
10件のお客様レビュー
『差別語から入る言語学入門』 田中克彦 差別語糾弾運動について、言語学的な視点から考えるという非常に面白い取り組み。運動自体を、「社会的に肉体的に差別されている人たちが、自分たちに対して、これこれの言葉を使ってほしくない、使わせないと声を上げたできごとは、人間の言語氏の上ではほ...
『差別語から入る言語学入門』 田中克彦 差別語糾弾運動について、言語学的な視点から考えるという非常に面白い取り組み。運動自体を、「社会的に肉体的に差別されている人たちが、自分たちに対して、これこれの言葉を使ってほしくない、使わせないと声を上げたできごとは、人間の言語氏の上ではほとんど考えられなかっためずらしいできごと」として、興味深いものと位置付けている。これまでの歴史では、明治日本の方言に対する態度をとっても、いわゆる正統と考えられる言語、言語の使用に関する覇権は常に、その時の政治的な強者がもっていたが、差別語糾弾運動は、その逆の、社会的に虐げられてきた人による、言語に関する覇権を奪取する運動としてみなしているところは面白い。 「ことばは、単に何かあるコト、ある事態を指すだけにとどまらず、それらをどのように見るかを言う観点を与えるというある意味で豊かさを厄介さをもっている。ことばは客観的にあたえられた世界にかかわるだけでなく、その世界をどのように見るかという言語共同体と、その主体ともかかわっていて、かれら、人間を支配している」 そのために、言語における覇権を奪取することは、それらによって見えている世界像の奪取という意味合いももっているのであろう。 差別語として、様々な事例があげられているが、興味深かったのが、「カタテオチ」「カタワ」という言葉に関する考察である。片方の腕がない方のことを指す差別語として取り上げられているが、そもそも、「カタテオチ」「カタワ」ということばが差別的と考えられる背景として、「カタ₋」と言うことば遣いが、「本来、二つではじめてそろいになっているもののうち、一方が欠けているもの」という含意を持っているが、それらに対応する言葉が日本語や中国語などのウラル¬=アルタイ諸語に特有ものであるというのである。「カタ₋」と言う言葉に、「本来二つではじめてそろいになっているもの」があるというそもそもの世界像の認識的な前提がなければ、この言葉は差別語足りえず、そして、そのような言葉が差別語として認識されているのは、まさに日本語の範疇の中だからなのである。日本においては、「本来二つではじめてそろいになっているもの」という社会的通念が言語によって形作られており、その結果として、「カタ₋」を接頭語とする言葉は、読み手に「強烈な欠損感」をもたらすのである。やはりこうした事例をとってみると、我々の世界認識というものがやはりいくぶんその使用言語に規定されているものであるとい感じざるを得ない。 最後に、差別語を考える上で、言語学が前提としている「共時主義(サンクロニー)」についても触れられていたため、メモしておく。「共時主義」とは、言葉の使い方など、それらが歴史的にどうであったかということではなく、いま、どういう風に受け取られているか、もっと言えば「話してのココロの中に生きている姿はどういうものか」ということを重要視する考え方である。一生懸命と言うことばがあるが、これは歴史的には一所懸命という言葉から来ている。しかしながら、現代的な意味で、一生懸命と言う場合の方がより広く大衆に受け入れられており、そうであるならばそちらの方に注目しようというものである。まさに差別語に関する検証も、この共時主義あってのものであろう。
Posted by 
本来、差別語と普通の単語の境目はなく、ある人が意図的に一つの言葉を用いた時に、それが差別的な意味を持つ。田中克彦先生の体当たりのような取り組みが文章でも表現されているのではないでしょうか。
Posted by 
差別語ができた経緯や、それが差別となった背景などを通して、人間の生活や文化の推移やモノの見方を分析する。 単にモノを指す言葉だったのが差別用語となったのには、人の観点の問題ということで、言葉は人間が作ったのだから、人間により徐々に変わってゆく。その経緯で人の争いや差別化が生まれ...
差別語ができた経緯や、それが差別となった背景などを通して、人間の生活や文化の推移やモノの見方を分析する。 単にモノを指す言葉だったのが差別用語となったのには、人の観点の問題ということで、言葉は人間が作ったのだから、人間により徐々に変わってゆく。その経緯で人の争いや差別化が生まれてゆく。 著者の主張は「言葉の由来は音で分かる」ということで、漢字より平仮名や片仮名表記が多い。 例えば「男・女」と書くより、音で「オトコ・オンナ」とすると、古い段階の「ヲトコ・ヲトメ」が浮かび上がり、「ヲト」をついとして、オス・メスを表す「コ・メ」が付いたと言葉だと分かる、という感じ。 昔人が自分で動物を食用にしていた頃は「しめる、ほふる」だったのが、肉を加工する人と食べる人が分かれた事により、「とさつ」ができて、「生きたカウ」と「食べるビーフ」と言葉が分かれた。 終盤に書かれた、裁判での言葉による印象操作(結果的には)の経緯は興味深かった。 ある男が会社に豚の頭を持って抗議に行ったところ脅迫罪で訴えられた。 家畜解体の仕事をする男にとって、豚の頭は日常品。 この豚の頭を最初は「豚の頭」「豚の首」と言っているのが、会社側が「豚の生首」などと残酷性を感じる言葉を使った(会社側からすればまさに「切り落としたばかりのナマクビを持ってきた」という正しい表現なんだろうけれど)。 それに被告側も合わせて「はい、豚の生首を…」などと答えてしまった。 それにより被告側の残虐性が印象付いてしまった。 …というように、言葉により印象が変わってゆくそのさまが書かれていて非常に興味をそそられた。
Posted by 


