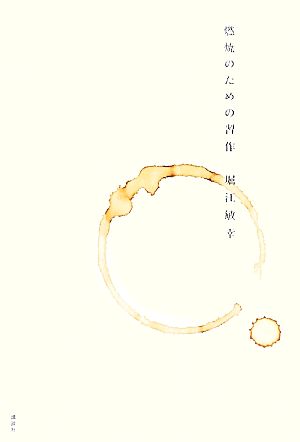
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1221-04-06
燃焼のための習作
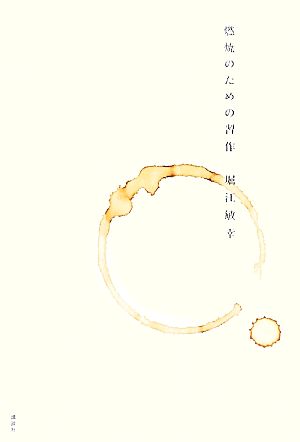
定価 ¥1,650
220円 定価より1,430円(86%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 講談社 |
| 発売年月日 | 2012/05/25 |
| JAN | 9784062176613 |
- 書籍
- 書籍
燃焼のための習作
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
燃焼のための習作
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.5
32件のお客様レビュー
[図書館] 『この30年の小説、ぜんぶ』の答え合わせのような感じで借りてみた。 …が、あの本のなかでも言われている通りこれはしんどくて最後まで読めなかった。「そういえばどこそこの誰々がこうこうこういうことをしてこんな事になって」という断片的な話を3人で変わる変わるしていくのが最後...
[図書館] 『この30年の小説、ぜんぶ』の答え合わせのような感じで借りてみた。 …が、あの本のなかでも言われている通りこれはしんどくて最後まで読めなかった。「そういえばどこそこの誰々がこうこうこういうことをしてこんな事になって」という断片的な話を3人で変わる変わるしていくのが最後まで続くという。。 これが読んでるうちにクセになる…と言えたら良かったんだけど。
Posted by 
「燃焼のための習作。すみません、もう一度、おっしゃっていただけますか? ねんしょう、は年少組、年中組のねんしょう? いえ、燃やすほうの燃焼です、しゅうさくは、美術で言うところの、エチュード。「燃焼のための習作」です。どういう意味でしょう?さあ、それが、いまだによくわからないんで...
「燃焼のための習作。すみません、もう一度、おっしゃっていただけますか? ねんしょう、は年少組、年中組のねんしょう? いえ、燃やすほうの燃焼です、しゅうさくは、美術で言うところの、エチュード。「燃焼のための習作」です。どういう意味でしょう?さあ、それが、いまだによくわからないんです、と枕木は正直に答えた。」-p.163 雷鳴が轟く荒天のある日。駅から案外距離のある、「間口の狭い四階建ての、築四十年を超えている縦長のマッチ箱のような」雑居ビルの一室。枕木という男とが探偵のようなことをしているらしいこの事務所に、ふらりと現れた熊埜御堂氏。遅れて登場する枕木の助手、鄕子(さとこ)さんという女性を含め、三人のとりとめもない会話が流れるように続いていく物語。ほとんど全ての台詞が「」ではなく文中にそのまま放り込まれているスタイルが斬新。でもそのせいでしっかり読まないと誰の台詞かすぐに見失う。 物語の冒頭は、枕木がコーヒーに角砂糖を入れてかき混ぜるシーン。この事務所がなんなのか、枕木とは、鄕子さんとは一体どういった人物なのか、情報がないままどんどん物語が進んでいって、興味をそそられる。気品のある文体にも惹かれる。著者は仏文学者とのこと。なんだかそう言われてみればまさにそんな気がします、という感じ。狭い視点からスタートし、登場人物たちの会話から徐々にいろんな情報を拾い集めていく工程は、夏頃に読んだ「最愛の子ども」を彷彿とさせた。 楽しんで読んでいたものの中盤を少し過ぎたあたりで急激に飽きがきて、かなり飛ばし読みしてしまった。何もやることがない日に一人で静かな喫茶店なんかに行って、それこそコーヒーを飲みながらじっくり読みたかった。常に誰かがなんらかの音を立ててその存在を主張している自宅で読むには、ちょっと大人しすぎた。 最後の最後、熊埜御堂氏について保留になっていた謎がついに解ける箇所は、現実味を帯びた哀愁が漂っていてよかった。あるある、あるよねそういうの、っていう。 「そういうひとことが、いちばんつらいかもしれないね、と枕木は鄕子さんの背中に向けて言った。似たような事例を、たくさん見てきたし、殺してやるとか、死んでやるとか、いままでありがとうとか、あとから分類しやすい台詞じゃなくて、相手のことをよく知っていなければ言えないことが胸に突き刺さるんだ、きっと」-P.216 それから、この本のフォントが気になる。昔からフォントが好き。学生時代、パソコンでワードをやってもパワーポイントをやっても一番楽しかったのは最後にどのフォントを採択するか決めるときだった。見慣れたゴシック体や明朝体から始まり、見慣れないフォントを選ぶとときどき平仮名が旧字体みたいになったり、漢字が化け文字みたいになったりするのが面白くて、何回も変えて遊んだ。教授によっては論文のフォントを逐一指定してくるような人もいて、世界で一番心が狭いと思った。そんな話はどうでも良くて、とにかくこの本のフォントが好き。明朝系だと思って調べたのだけど、フリーフォントのサイトでは全く同じものを見つけられなかった。気になって気になって仕方ないのでAmazonでフォント字典を検索して、ほしい物リストに入れた。いつ買おう。 ここまで書いたところでよしお終いにしようと思ったけれど、この物語全体を通して漂う雰囲気はすごく好きだったからどうも勿体無いような気がしてしまって、もう一度本を開いた。読み飛ばした後半部分を中心に再読。午前中でまだ自宅が静かだというのもあって一回目よりはスムーズに世界観に浸ることができて、新たな情報もいくらか収集できた。なんかこうやって一冊の本を何回かかけて少しずつ読み終えていくやり方もいいな、と思ったのでした。
Posted by 
どうも私にとって堀江さんは読むタイミングを選ぶ作家さんの様です。 以前『いつか王子駅で』の感想として「本を読むには、やはりそれに適した時期(というか、読み手の精神状態)があるようです。何度か読みかけては挫折したこの小説なのですが、今度はじっくり楽しみながら読むことができました。」...
どうも私にとって堀江さんは読むタイミングを選ぶ作家さんの様です。 以前『いつか王子駅で』の感想として「本を読むには、やはりそれに適した時期(というか、読み手の精神状態)があるようです。何度か読みかけては挫折したこの小説なのですが、今度はじっくり楽しみながら読むことができました。」と書いていました。 今回はそのタイミングでは無いのに無理やり読了したような気がします。 運河沿いに建つ雑居ビルの中の事務所に嵐で閉じ込めらた三人、探偵のような事をしている中年の男・枕木とその助手の郷子さん、依頼人?の熊埜御堂(くまのみどう)氏。全編、この三人の思いつくままに繋り続ける会話で出来た小説です。 一気読みする本では無いですが、それにしてもとぎれとぎれに読み過ぎました。おそらく何かの仕掛けがあるのでしょうが、それがつかめぬまま読了。 いつか読み直せば、また評価が変わる話だと思うのですが。
Posted by 



