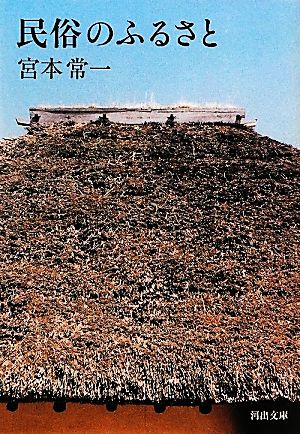
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-27-00
民俗のふるさと 河出文庫
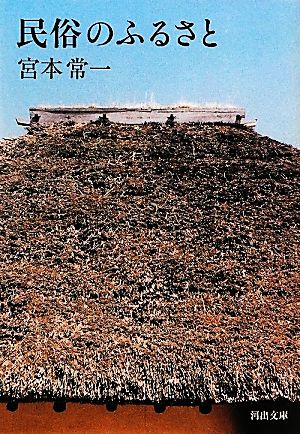
定価 ¥968
550円 定価より418円(43%)おトク
獲得ポイント5P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 河出書房新社 |
| 発売年月日 | 2012/03/05 |
| JAN | 9784309411385 |
- 書籍
- 文庫
民俗のふるさと
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
民俗のふるさと
¥550
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.5
10件のお客様レビュー
都会/田舎、町/村の成立過程や習俗の違いを著述してある書籍。 ある意味、どのような日本人論よりも濃い内容になっているように感じた。 処分日2014/09/20
Posted by 
1964年(昭和39年)東京オリンピックの年に書き下ろされて1975年に改訂されたものを底本に文庫化。 日本の都会はどうやってできていったのか、都会の暮らしはどうやってなったのかということを、村ができて、そこではどんな暮らしが営まれていたか、そして村が町になっていって、と、この順...
1964年(昭和39年)東京オリンピックの年に書き下ろされて1975年に改訂されたものを底本に文庫化。 日本の都会はどうやってできていったのか、都会の暮らしはどうやってなったのかということを、村ができて、そこではどんな暮らしが営まれていたか、そして村が町になっていって、と、この順ではないけれど自身が調査に入った村での聞き取りなどをもとに書かれている。 日本人の生きてきた様がとても興味深い。 大分県杵築市の納屋部落、世間的な秩序の外に立ち生き生きと暮らしていた漁師の話とか。 「賎民のムラ」での職業とムラの作られ方が分かりやすい。「生業の推移」も読みたいと思う。 国勢調査が始まったのは大正9年なのか。
Posted by 
日本の都市や農村で、何が変わり何が残っているのかについての重要な示唆が詰まった一冊。本書が書かれたのは戦後、都市人口が急激に膨張した時代であり、そこでは必然的に都市と農村のせめぎ合いが強く意識されたことだろう。農村コミュニティが急速に解体し都市化が進む一方で、農村国家としてのアイ...
日本の都市や農村で、何が変わり何が残っているのかについての重要な示唆が詰まった一冊。本書が書かれたのは戦後、都市人口が急激に膨張した時代であり、そこでは必然的に都市と農村のせめぎ合いが強く意識されたことだろう。農村コミュニティが急速に解体し都市化が進む一方で、農村国家としてのアイデンティティが喪われるかと思いきや、農村出身の都市居住者により辛うじて受け継がれる様々な風習に、著者は頼もしさと弱々しさを同時に感じていたことだろう。世に出て半世紀が経過する本書だが、今読んでも驚くほど違和感を感じる部分が少ない。変わったつもりでも変わらない部分の大きさに改めて驚かされる。
Posted by 

