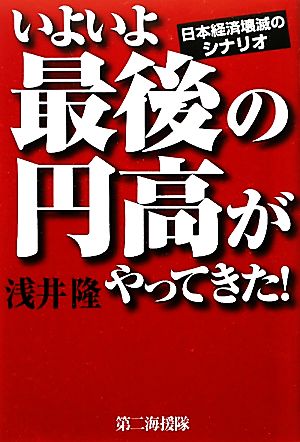
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-12
いよいよ最後の円高がやってきた! 日本経済壊滅のシナリオ
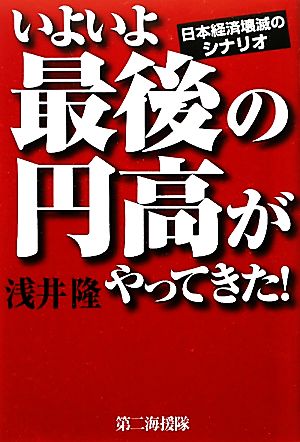
定価 ¥1,650
110円 定価より1,540円(93%)おトク
獲得ポイント1P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 第二海援隊 |
| 発売年月日 | 2011/10/14 |
| JAN | 9784863351370 |
- 書籍
- 書籍
いよいよ最後の円高がやってきた!
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
いよいよ最後の円高がやってきた!
¥110
在庫なし
商品レビュー
3
2件のお客様レビュー
著者曰く、「今の円高が最後の円高」のようです。1円 円高になると輸出企業がxx円損出とか聞くので他人事ではないです。 「円高・空洞化」→「円安・インフレ」→「国家破産」これが日本経済破滅のシナリオだ! 本書では、著者のシナリオにしたがって、予想される理由や原因を紹介してくれま...
著者曰く、「今の円高が最後の円高」のようです。1円 円高になると輸出企業がxx円損出とか聞くので他人事ではないです。 「円高・空洞化」→「円安・インフレ」→「国家破産」これが日本経済破滅のシナリオだ! 本書では、著者のシナリオにしたがって、予想される理由や原因を紹介してくれます。そして、生き残るためにはどうしたらよいか説明しています。 円高が気になる方にお勧めします。 以下は、自分が気になったポイントです。 ユーロ圏の若年層の高失業率。 円高のメカニズムは、日本円が、米ドルやユーロと比べて「発行ぺーすが遅いため」だ。 政策金利をゼロ以下にすることはできないため、デフレになると通貨の価値は高くなる。 日本の株価は、最悪5000円代まで、突入する。その後歴史駅な長期上昇トレンドへの転換点がやってくる。 日本とアメリカで、長期トレンドの逆転現象が起きる。ヨーロッパも基本的な値動きは同じ。 IT技術と金融工学の進歩は、1企業、1個人ですら世界を動かせることを証明してしまった。世界を動かすファクターが増え相互に複雑に関連し合い、その先行きも複雑に変化する。 世界的に金融政策が出口戦略に向かうとされている2014年頃が危ないと見ている。 先進国には、インフレによる債務削減しか解決策が残されていないのだ。 どこかしらで起きた金融危機が先進国の財政をさらに苦しめていき、世界は徐々に財政インフレの様相を呈していくことだろう。 ロイターの報道によると、「中国はドル高・中国人民元安を維持するため、少なくても5年間にわたり毎日少なくても10億ドル規模の為替介入を実施してきた」と指摘 何よりも大きな問題は、日本が枠組みつくりから蚊帳の外に置かれたことだ。 具滝てな資産保全対策は次の通りだ。中心になるのはやはり外貨だ。 本当に残念なことだが、日本経済は間もなく壊滅する。
Posted by 
浅井氏の本は結婚する前の1993年頃から読んでいるのですが、ある意味で論調を変えないのは評価できるのでしょうが、ずっと「これが最後の円高で、国債暴騰して円安になる」と言い続けています。 今回の円高現象も最後のもので、いずれ円安となる、資産保全のためには外貨(米ドル等)にヘッジす...
浅井氏の本は結婚する前の1993年頃から読んでいるのですが、ある意味で論調を変えないのは評価できるのでしょうが、ずっと「これが最後の円高で、国債暴騰して円安になる」と言い続けています。 今回の円高現象も最後のもので、いずれ円安となる、資産保全のためには外貨(米ドル等)にヘッジすべきというものですが、その「いずれ」とはいつなのか、35年程度しかメインで稼ぐことのない社会人にとっては重要な情報です。 円安になると信じていた時期もあるのですが、為替は絶対的なものではなく、他国との経済関係で決まるのであれば、例えば副島氏が宣言しているように円高が進むということも十分に考えられます。 但し、浅井氏がこの本で指摘しているように、食糧が採れなくなり(歴史的表現では気候変動による飢饉の発生)現金の価値がなくなった時には、一瞬にしてデフレ経済からハイパーインフレに至るという現象があり得る、というのは、年末に読んだ本(平清盛の失敗)でやっと理解できました。 今後とも両者の意見を読み比べて、自分なりの資産形成の計画を立てていこうと思いました。 この本で得られた興味ある情報として、円ドル為替の歴史を詳細に解説してくれていたことでした、歴史好きの私には最高でした。 以下は気になったポイントです。 ・円高は輸入物価が安いので海外のインフレを相殺できる、本当に怖いのは、財政破たんとそれに伴う円の価値の急落である(p14) ・今の円高の理由は、日本円が米ドルやユーロと比較して、発行ペースが遅いため、通貨供給量が少ないので価値が上がっている(p32) ・実質金利でみると、日本ではいまだデフレが続いているため、通貨の価値は下がっていない、欧米ではインフレのため、資産価値は現金で持っていると目減りするので「円買い」をする(p35) ・経済成長している場面での円高は、産業構造の改革にもつながり内外格差の縮小につながる、現在の円高は、単純に国内への投資を減らし、輸入拡大よりも輸出減少が大きく経済規模は縮小する悪いもの(p43) ・株式市場で、なぜ上がるときは三段階で、下がるときは二段階なのかは市場に参加する人間の心理的な働きが反映されているからだろう(p52) ・日経平均の長期下落トレンドは間もなく終わり、20~30年かけて続く長期上昇トレンドになる(p68) ・ゴールドはすでに高水準、次に来る商品は、穀物や食糧、世界のGDPがここ50年間で数十倍に膨らむ中で、穀物価格は数倍にしか上昇していない(p75) ・最後の円高が円安に振れた時、円高という防波堤でなんとか防いできた物価上昇の津波をもろに被ってしまう(p78) ・通貨の分散は、日本円:米ドル:豪orNZドル=1:1:2にすべきで、ユーロは保有しない、キャッシュではなく、それぞれの通貨建ての優秀なMF(p81) ・江戸幕府を倒した明治政府も金本位制を採用したものの、金流出のあおりで、結局、金銀複本位制を採用せざるを得なくなり、1878年には「銀本位制」となった(p103) ・1871年に布告された「新貨条例」により、1両=1円とし、1円金貨の金含有量を1.5グラムとした、それを1米ドルとした、超円高である(p103) ・日清戦争後には、1ドル=2円、太平洋戦争直前には、1ドル=4.25円まで下落した(p105) ・国内製造業全体の海外現地生産(生産高)比率は、1990年度には5%以下であったが、2015年度には21.4%になる見通し(p133) ・QE1(量的緩和策第一弾)はファニーメイ、フレディマックへの資金供給、QE2は米国債の買い入れ、QE3は州政府と地方自治体の債務がターゲットになる(p145) 2012年1月2日作成
Posted by 



