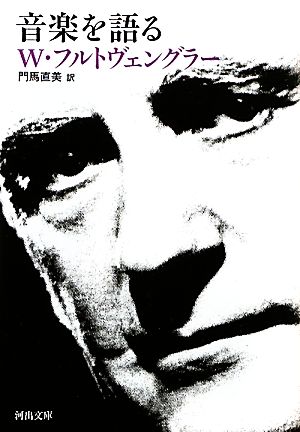
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-35-03
音楽を語る 河出文庫
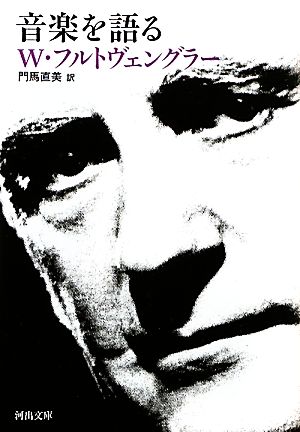
定価 ¥726
220円 定価より506円(69%)おトク
獲得ポイント2P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 河出書房新社 |
| 発売年月日 | 2011/10/06 |
| JAN | 9784309463643 |
- 書籍
- 文庫
音楽を語る
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
音楽を語る
¥220
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.5
4件のお客様レビュー
難しかった。よく理解出来ないけど、何か怒っているみたい。 キリスト教的価値観が基本にある考え方みたいなので、そこから共感していかないと共感出来ない?
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 至高窮極の指揮者、フルトヴェングラー。 楽符というテキストの限界をそのままにせず、作品の構造分析と楽興の導くところ、ダイナミックに速度・リズムを動かして生きた音楽を実現したフルトヴェングラーが追求した、音楽の神髄を克明に綴る。 ドイツ古典派・ロマン派に本領を発揮した、その理念の全貌。 [ 目次 ] 第1章 聴衆について 第2章 演奏について 第3章 劇的な音楽 第4章 ベートーヴェンの偉大さ 第5章 指揮者と試演 第6章 環境と芸術 第7章 現代の音楽 結語 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by 
本書は、1948年にフルトヴェングラーの戦後最初の発言として出版されたインタヴュー集であるが、インタヴューそのものは戦前の1937年に行なわれている。聞き手はディ・ツァイト紙の主筆を務めたこともある音楽批評家ヴァルター・アーベントロート。この文庫版に付された解説によると、当初書...
本書は、1948年にフルトヴェングラーの戦後最初の発言として出版されたインタヴュー集であるが、インタヴューそのものは戦前の1937年に行なわれている。聞き手はディ・ツァイト紙の主筆を務めたこともある音楽批評家ヴァルター・アーベントロート。この文庫版に付された解説によると、当初書き起こされた原稿には、彼の発言が多く含まれていたようだが、フルトヴェングラーはそれを削りに削って自分の発言を彫琢した。そのため本書において読者は、彼の指揮する演奏を聴くような滔々と流れる独白を読むことになる。そこにはフルトヴェングラーの音楽観が率直に示されていると言ってよい。それを貫くのは、一種の生の哲学にもとづく、形式と内容の有機的な合致が音楽を構成しているという確信である。そして、それが音楽作品の全体を貫いているのを再現するのが演奏だとする彼の演奏観は、彼自身の指揮する演奏を彷彿とさせるのみならず、現代の演奏のあり方を鋭い問いを投げかけるものかもしれない。実際フルトヴェングラーは、同時代の演奏において、装飾性の強い作品を華麗に演奏する技術に長けた演奏家が、古典的な形式性をもった作品を演奏する際には生気のない演奏しかできないことを例に、古典的な作品のもつ、形式と内容の合致した全体を把握した演奏が難しくなりつつあると述べるとともに、古典的作品を表面的な仕方で歴史的に再現しようとするような演奏を厳しく批判している。こうした発言は、ベートーヴェンを繰り返し繰り返し取り上げる、演奏におけるフルトヴェングラーの古典重視の行き方を物語るものであろうが、それ以上に重要なのは、音楽家、何よりも作曲家としての彼の立場を表明する発言であろう。彼は、人間精神の永遠の本質を表現することを芸術家の使命とまで公言し、その表現の形式として、新たに加えられた終章「現代の音楽」において調性音楽を擁護する。彼にとっては、しばしば無調音楽の予兆とされるヴァーグナーの「トリスタン」の語法も、この楽劇の世界を表現するための、調性音楽の枠内の語法にすぎない。そして彼は、調性音楽は、宇宙における人間の有機的な生に方向性を与えるのだ、と古代のピタゴラスと同時代のヤスパースの両方の思想を思い起こさせるような発言を行なっている。フルトヴェングラーにとって調性音楽の法則は、人間の有機的生活の法則であり、音楽の素材すべてはそのような調性音楽のために秩序づけられているのだ。しかも、そのことは「生物学的事実」から証明されるという。解説でも指摘されるとおり、ナチズムにも結びつきかねないこうした時代的な言葉遣いによる調性音楽の擁護は、ナチの疑似科学的な発想からは遠いとはいえ、それによって横領されかねない危うさを含んでいる。ただし、その内実、とりわけそれを貫く生の哲学は、今一度反時代的な思想として、例えば無調音楽へのオマージュに貫かれたアドルノの『新音楽の哲学』と対照させて検討されるなら、音楽そのものについて豊かな思想を紡ぎ出す契機をもたしうるかもしれない。翻訳に古さと生硬さを感じるうえ、ディスコグラフィがあまりにも古いので、文庫版にする際に改訂すべきだったと思われる。
Posted by 



