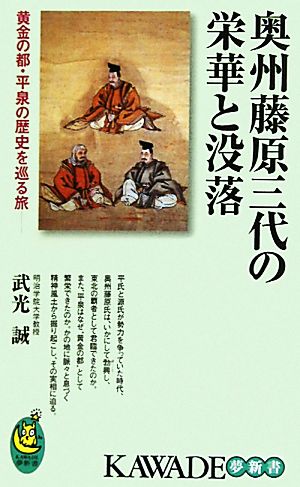
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-26-01
奥州藤原三代の栄華と没落 黄金の都・平泉の歴史を巡る旅 KAWADE夢新書
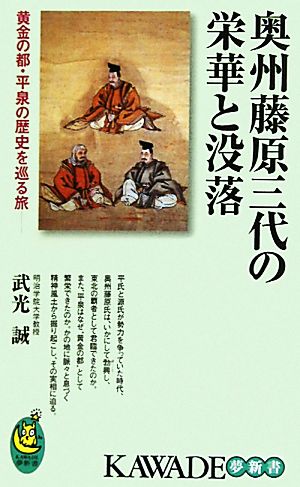
定価 ¥836
220円 定価より616円(73%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 河出書房新社 |
| 発売年月日 | 2011/08/26 |
| JAN | 9784309503844 |
- 書籍
- 新書
奥州藤原三代の栄華と没落
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
奥州藤原三代の栄華と没落
¥220
在庫なし
商品レビュー
4
1件のお客様レビュー
奥州藤原氏の時代だけでなく、前九年の役に至るまでの東北の歴史がまとめられており、わかりやすい。 前九年の役まで ・紀元前後から、水稲耕作が関東地方北部から福島県と宮城県南部に広まり、2世紀初めには青森県まで広まったが、森の中では縄文文化の伝統を守り続ける人々がいた。 ・宮城・山...
奥州藤原氏の時代だけでなく、前九年の役に至るまでの東北の歴史がまとめられており、わかりやすい。 前九年の役まで ・紀元前後から、水稲耕作が関東地方北部から福島県と宮城県南部に広まり、2世紀初めには青森県まで広まったが、森の中では縄文文化の伝統を守り続ける人々がいた。 ・宮城・山形南部までの地域では、大和朝廷成立以前に弥生文化が広まり、4世紀以降は古墳をつくり始め、国造も集中していた。 ・岩手・秋田北部より北側の地域が日本の一部と意識されるようになるのは、鎌倉政権が奥州藤原氏を討った後。 ・宮城・山形北部と岩手・秋田南部の地域の蝦夷に対する朝廷の武力による征服は6世紀末から始まり、奈良遷都の直前頃から大がかりに行われるようになった。朝廷に従った人々は俘囚と呼ばれたが、しばしば反乱を起こした。 ・730年に多賀城がつくられ、760年には桃生柵(石巻市)、雄勝柵(横手市)がおかれた。 ・769年につくられた伊冶城(栗原市)は蝦夷の首長に囲まれた位置にあったため、40年あまりの争乱を引き起こした。789年には大墓阿弖流為が出現して朝廷側を苦しめたため、802年に坂上田村麻呂が派遣されて戦乱を鎮めた。 ・蝦夷の反乱は878年の元慶の乱などがあったが、947年を最後に終わった。そののち、「蝦夷」は「えぞ」と読まれてアイヌを表すようになった。 ・10世紀半ばに平将門の乱が起こり政治が乱れたため、奥羽の政治を俘囚に任せる考え方が出て、10世紀末頃、安倍氏が六箇郡之司となった。これは、陸奥の特産品である金、皮衣、鷹、馬の交易を貴族が勝手に行うことを抑え、朝廷が支配するためでもあった。 ・平安時代の半ばに全国で土地開発がすすめられ、農民の先頭に立って農耕を行い、武装して外敵を退ける名主(武士)が現れ、有力な武士である棟梁を立てて団結した。東北地方では、安倍氏や清原氏が棟梁の役割を務めるようになった。 ・藤原氏の傍流が関東の武士の棟梁のひとつとなったが、経清は陸奥に移って亘理郡の支配を任された。 秀衡以降 ・奥州藤原氏は摂関家との関係を維持していたが、1159年の平治の乱の頃から新興の平氏との結びつきを強めていった。秀衡は1170年に鎮守府将軍に、1181年には陸奥守に任命され、源氏を背後から睨む役割を担わされたことが源氏との対立を生んだ。 ・秀衡は、源氏の勢力が伸びたときのために義経を厚遇した。しかし、平氏滅亡後、頼朝の勢力が伸びることを嫌った後白河法皇が義経を取り込んだため、対立することになった。 ・津軽地方の土着豪族だった安東氏は、鎌倉幕府が北条家に地頭職を与えると、蝦夷地との交易による利益の一部を分配する代わりに保護を受けて十三湊が繁栄した。 ・頼朝遠征の時に平泉館が焼け、鎌倉時代の半ばに毛越寺が消失、南北朝時代に中尊寺の金色堂と経蔵以外が放火によって失われた。江戸時代になって伊達家が中尊寺の寺院を復興した。
Posted by 



