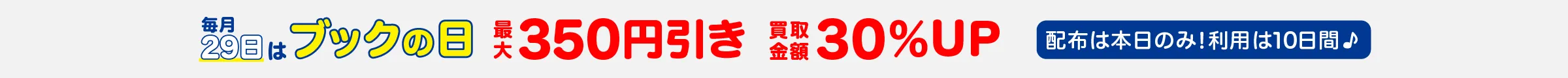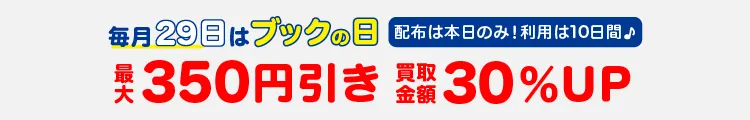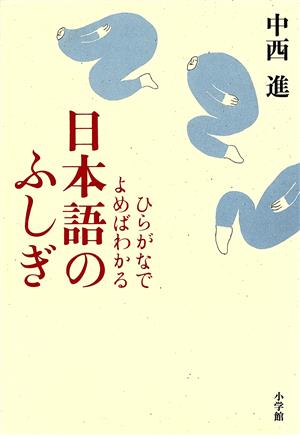
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1217-02-03
ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ
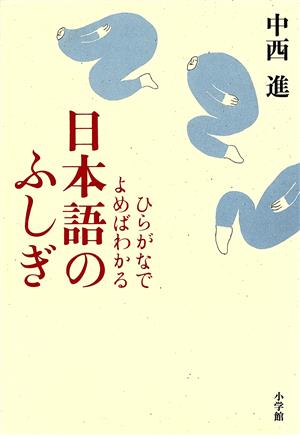
定価 ¥1,540
715円 定価より825円(53%)おトク
獲得ポイント6P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 小学館 |
| 発売年月日 | 2003/06/30 |
| JAN | 9784093874526 |
- 書籍
- 書籍
ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ
¥715
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.5
8件のお客様レビュー
若竹千佐子さんのエッセイで確か紹介されていて、読んでみたいと思った本。 やまとことばを取り上げて、目はなぜ「め」なんだろう、「目」と「芽」、「歯」と「葉」と「端」など、同じ音は同じものと捉えていたとか、そういった古代日本人のものごとの捉え方に思いを馳せる。 今私は洋書を読む...
若竹千佐子さんのエッセイで確か紹介されていて、読んでみたいと思った本。 やまとことばを取り上げて、目はなぜ「め」なんだろう、「目」と「芽」、「歯」と「葉」と「端」など、同じ音は同じものと捉えていたとか、そういった古代日本人のものごとの捉え方に思いを馳せる。 今私は洋書を読むことにちょっとハマっているけど、英語の勉強が嫌いじゃないのは高校の英語の先生のおかげで、辞書的な言葉の対応としてではなく、「この言葉はこういう概念・イメージ・気持ちを表す、だからこの訳語が一般に充てられているけれど、文脈や背景によってはもっと別の訳語がふさわしいときもあるかもしれない」というアプローチをしてもいいことを教えてもらった(テストで丸が付くかどうかはともかく)。 なんだかこの本には、そうやって知らない外国の言葉の概念を教えてもらうときのようなワクワク感があった。それでいて、まあ一応自国語だから、「わかる、わかる」というホーム感もあって、ふしぎ。 はな、あめ、はし、など日本語には同音異義語がたくさんあって、それをつかった駄洒落や謎掛けやとんちなどの言葉遊びもたくさんあって、親父ギャグ、などと見下したような言い方をすることもあるけれど、いやいや、日本語の本質に迫った遊びなのかもしれない。
Posted by 
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1910298936210030753?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
Posted by 
著者の中西進さんは国文学者で、元号「令和」の発案者のようだ。 この本は、いろいろな日本古来のことばを語源から考えて紹介している。著者は『万葉集』など古代文学の比較研究をされているだけあって、言葉の説明のために『万葉集』などから引用される歌もおもしろい。 文中で何度か登場する...
著者の中西進さんは国文学者で、元号「令和」の発案者のようだ。 この本は、いろいろな日本古来のことばを語源から考えて紹介している。著者は『万葉集』など古代文学の比較研究をされているだけあって、言葉の説明のために『万葉集』などから引用される歌もおもしろい。 文中で何度か登場する、柳田国男さんが警告した〝どんな字病〟はそのとおりで、あとから漢字を当てられているのだから、音で考えるのが道理なのだなと納得させられる。 紹介されているおもしろい例はたくさんあるが、以下に少しメモを。 ○「みち(道)」 ち=長く伸びるもの、風を意味する。「はやて(疾風)」の「て」と同義 み=尊いものに冠する接頭語 ○断り・理(ことわり)の古語「ことわり」 「こと(事)」を「わる(割る)」=分析する ○さいわいの古語「さきはひ」 はひ=ある状態が長く続くこと(けはひ、あぢはひ) さき=花が咲くの「さき」 さきはひ=心の中に花が咲きあふれてずっと続く ○ひがし にし ひがしの古語「ひむがし」 ひ(日)+むか(向)+「し」 「し」=風のこと。おそらく西の「し」も ○はる 陰鬱に覆われていた自然が晴れやかになる さあっと野山が開けて輝き始める 「冬ごもり 春さりくれば……」(万葉集) ・晴る ・張る(芽が膨らむ、強く盛んになる) ・墾(は)る(田畑を耕して開く) →総じて「明るくなる、見通しが良くなる」 ・広く平らなところ「はら(原)」も仲間 ・はる+ふ=はらう(祓う、古語は〔はらふ〕) お祓い=悪いものを取り除いてきれいにする ・冬が取り払われてやってくるのが「春」 ・新しい年が始まる大きな区切り ○ふゆ ふゆは寒くて冷える、「ひゆ(冷ゆ)」 震えるほど寒い、「ふゆ(振ゆ)」 ○あき 十分に食べられる収穫の季節。「あき(飽き)」 満ち足りる、十分すぎてもういらない、明らかにする、あきらめる(諦める)も仲間 ○なつ 語源ははっきりしない 「あつ(熱い)」が変化するとする説もある
Posted by