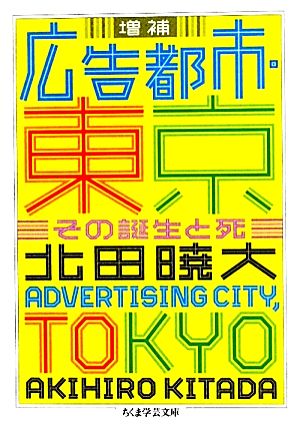
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
広告都市・東京 その誕生と死 ちくま学芸文庫
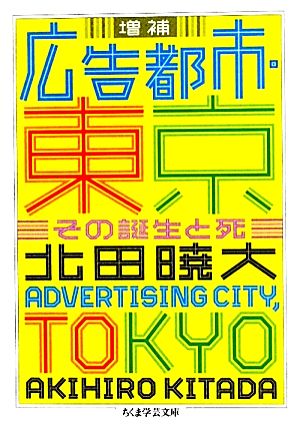
定価 ¥990
550円 定価より440円(44%)おトク
獲得ポイント5P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
12/8(日)~12/13(金)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2011/07/08 |
| JAN | 9784480093820 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
12/8(日)~12/13(金)
- 書籍
- 文庫
広告都市・東京
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
広告都市・東京
¥550
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.1
8件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
●トゥルーマン・ショー ・映画「トゥルーマン・ショー」の舞台は広告都市「シーヘブン」 ・主人公以外は全て役者とプロダクトプレイスメントされた舞台セット。それを現実と思っているのは本人だけ。 ・世界中の人間がその様子を外部から見ており、目に入るものは全て自然な広告になる。 ●近代から現代への広告の変化 ・昔は広告はもっとチンドン屋的なダイレクトな感じだった ・近代国家になるにつれそういう野蛮なものが受け入れられなくなった ・広告は潜むようになった。広告然とした広告からメタ広告へ ●80年代、広告都市渋谷 ・西武=セゾン=パルコの東急王国渋谷への挑戦 ・池袋では実現できなかった(駅直結西武が「袋」で完結) ・「公園通り」「オルガン坂」「サンドイッチロード」「スペイン通」を丸ごと広告空間に開拓。渋谷=公園通りの完成。 ・元々あった渋谷の土着感から切り離したディズニーランド的な文化感溢れる「日常からの脱出」を実現する街の演出。単なる客寄せではない文化事業を実施するのもこのため。 ・そこは閉鎖的な記号空間で、ゲスト(来訪者)はその場にふさわしい振る舞いを求められる ●90年代、失効 ・センター街、ランブリング・ストリートとコギャル、夜の街渋谷などにより渋谷のイメージが変わり、今では観光客向けの文化的幽霊としてかつての渋谷の残滓があるだけ ————————— ここまでが2002年に書かれた本の内容。それから20年経って今渋谷は2027年に向けて東急グループの再開発によって「ジャスコ的な何か」に生まれ変わろうとしているように思える。
Posted by 
1980年代とポスト80年代の広告と都市のあり方を対比的な枠組みの中で比較検討し、消費社会的な感性の変容について考察をおこなっている本です。 著者はまず、ジム・キャリー主演の映画『トゥルーマン・ショー』を読み解きつつ、広告が差異を創出することで資本主義の運動を絶え間なく駆動させ...
1980年代とポスト80年代の広告と都市のあり方を対比的な枠組みの中で比較検討し、消費社会的な感性の変容について考察をおこなっている本です。 著者はまず、ジム・キャリー主演の映画『トゥルーマン・ショー』を読み解きつつ、広告が差異を創出することで資本主義の運動を絶え間なく駆動させていくような性質を持っていることを指摘し、そのことが映画の中で「シーヘヴン」という自己完結的な空間を維持することを不可能にしたという解釈を示しています。 80年代の消費社会を領導したパルコに代表される西武セゾン・グループのイメージ戦略においては、そうした広告の持つ運動性を都市計画の中に文化的な意匠として取り込むことがめざされていました。これによって、あらかじめ一定の計画のもとに設計された都市空間を逸脱していく広告の運動が、「広告=都市」という形でキャナライゼーションされることになります。80年代の渋谷の街を歩くことは、消費社会的な主体としてみずからの欲望を水路づけることにほかなりません。著者は、こうした広告=都市が批判という外部を持たず、むしろ消費社会に対する批判的言説でさえもたちまち広告の有効な戦略として機能してしまうことを指摘します。 ところが、こうした文化的な都市空間としての渋谷のイメージは、80年代末頃から退潮を示すようになり、やがて情報量のアーカイヴの中で、相対的な優位を占める都市にすぎないとみなされるようになります。こうした「脱舞台的なまなざし」を持つ新しい世代の若者たちの行動を考察するに当たって著者は、ケータイによって「つながっていること」そのものが重要とされるようなコンサマトリーなコミュニケーションのあり方に注目します。渋谷という現実の空間も、他者との「つながり」を確保するための素材(ネタ)でしかありません。著者はここに、消費社会的な感性の大きな変容を見ようとしています。
Posted by 
北田先生の本は、「嗤う日本の『ナショナリズム』」以来の2冊目。 広告と都市 メディアと人 ここら辺のテーマは学生時代から関心テーマの一つではあったんだけど、 今曲がりなりにも仕事として広告に携わるようになってから、 広告やメディアを社会学的な観点から考えなおすとまた面白い。 ...
北田先生の本は、「嗤う日本の『ナショナリズム』」以来の2冊目。 広告と都市 メディアと人 ここら辺のテーマは学生時代から関心テーマの一つではあったんだけど、 今曲がりなりにも仕事として広告に携わるようになってから、 広告やメディアを社会学的な観点から考えなおすとまた面白い。 広告都市としての東京、特に渋谷の話は、 個人的には全くリアルタイムでないどころか、 東京で働くようになった現時点でさえ完全に縁遠い自分にとっては、 (まさにただの情報アーカイブでしかなくて、渋谷でなくちゃいけない意味を感じたことがない) はーそういうものだったのか、というぐらいの歴史物語でした。 そういう「広告都市」の流れを知ることができたこと、 その時代における消費社会論や(文化)記号論の態度を知れたこと、 この2点は知識として読んで良かった。 考えるべきテーマとしても面白かったのは、 広告とは本質的にメディア寄生性を持つものである、という点。 いや、これはテーマというより前提なんだけど。 補遺でインターネットにおけるコミュニティについても触れられていたけど、 その進化、深化について考えたり、 またはソーシャル化(ソーシャルメディア)というテーマを考えるのも面白い。 ソーシャルメディア上での広告、マーケティングのあり方、 それに対する個人の受け止め方、 企業と個人の関係性について、 などなど。 ここら辺考えてみようと思うけど、 その前にもっかい記号論ちょっとだけ勉強したい。 あ、でもその前に「オトナ帝国」もっかい観たくなった。
Posted by 


