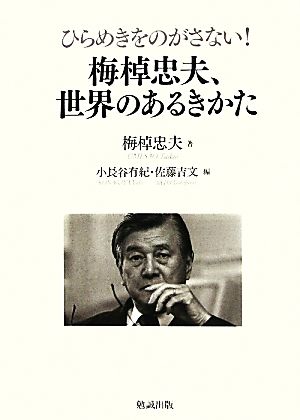
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-07-00
ひらめきをのがさない!梅棹忠夫、世界のあるきかた
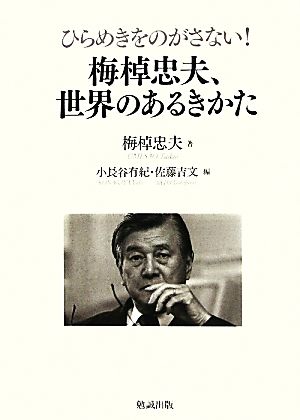
定価 ¥2,420
770円 定価より1,650円(68%)おトク
獲得ポイント7P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 勉誠出版 |
| 発売年月日 | 2011/05/01 |
| JAN | 9784585230076 |
- 書籍
- 書籍
ひらめきをのがさない!梅棹忠夫、世界のあるきかた
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ひらめきをのがさない!梅棹忠夫、世界のあるきかた
¥770
在庫なし
商品レビュー
4
4件のお客様レビュー
10年前に出版されている。どういうわけか、途中まで読んで、そのままベッド横の本棚に差し込まれていた。それをふと思い立って取り出し、最後まで読んでみた。半分は写真で、文章は短いのであっというまであった。しかし、この大量の写真はありがたい。岩波写真文庫の復刊を願っているが、たぶん難し...
10年前に出版されている。どういうわけか、途中まで読んで、そのままベッド横の本棚に差し込まれていた。それをふと思い立って取り出し、最後まで読んでみた。半分は写真で、文章は短いのであっというまであった。しかし、この大量の写真はありがたい。岩波写真文庫の復刊を願っているが、たぶん難しいだろうから。とはいえ印象に残ったのは、「中洋」ということばと出会ったころ乗っていたフォルクスワーゲンの写真と、石毛料理長がかっこうよくくわえタバコでナイフをにぎっている写真なのだが。それと最初の方に記載されているいくつかのスケッチ。さすがに絵心がある。カメの写真に付されている文章にこうある。「狩猟採集民は採集なんてしない。あるときに食べる。取りながら食べる。集めておくということがない。カメが手に入ればそのときに食べ、明日はまたどうなるかわからない。そういう貯蔵のない食生活を目の当たりにして、幸福を論じた。」幸福を論じた。それをきっとどこかで読んでいると思うのだが、もう一度読んでみたい。いったいどこに書かれているのだろうか。「梅棹はひとつの学問分野を構築したわけではない。しかしながら、著書に対する反響の手紙を見れば、その社会的インパクトがいかに甚大であったかがわかる。日本全体の知的基盤に対しておおいに寄与した、といえよう。」まったく同感であるし、私自身ほんとうに大きな影響を受けてきた。梅棹の数々の著書と出会っていなければ、いまのようなものの考え方はできなかっただろうと思う。
Posted by 
本書をアマチュアで研究らしきことをやっている人、これからやってみたい人に一読することをお勧めしたい。今日の情報化社会においては、誰もが日常的かつ気軽な気分で知的生産活動に取り組むことができる。本書のエッセンスを知っているか否かで、自らが発信する情報の質がかわってくるだろう。 ま...
本書をアマチュアで研究らしきことをやっている人、これからやってみたい人に一読することをお勧めしたい。今日の情報化社会においては、誰もが日常的かつ気軽な気分で知的生産活動に取り組むことができる。本書のエッセンスを知っているか否かで、自らが発信する情報の質がかわってくるだろう。 また、まとまった文書を執筆する上での、スケッチの大切さを気づかされた。スケッチがそのまま論文に反映されることは少ないかもしれないが、分析対象を掌握するためには広くこのスケッチ作業を行う必要があるという。
Posted by 
梅棹忠夫氏の活躍を知らない世代なので、偉人伝のように書かれている文章は素直に読めなかった。しかしながら、今のようにパソコンやデジカメがない時代であったがゆえに、洗練されていた以下の技術の高さを感じずにはいられなかった。どのように記録を残すのか、特に言葉の使い方、ディテールの描き方...
梅棹忠夫氏の活躍を知らない世代なので、偉人伝のように書かれている文章は素直に読めなかった。しかしながら、今のようにパソコンやデジカメがない時代であったがゆえに、洗練されていた以下の技術の高さを感じずにはいられなかった。どのように記録を残すのか、特に言葉の使い方、ディテールの描き方、写真と文章の組み合わせ方、など。ただ単に、写真を追うだけでも楽しい。
Posted by 



