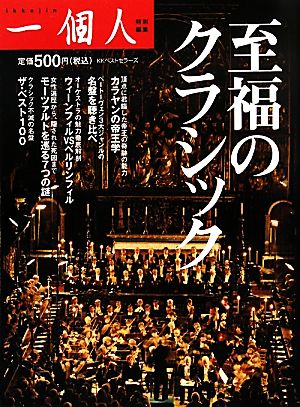
- 中古
- 書籍
- 書籍
至福のクラシック
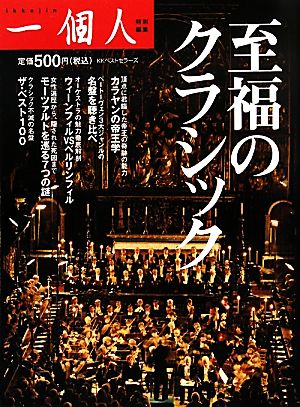
定価 ¥590
110円 定価より480円(81%)おトク
獲得ポイント1P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ベストセラーズ |
| 発売年月日 | 2011/04/18 |
| JAN | 9784584166208 |
- 書籍
- 書籍
至福のクラシック
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
至福のクラシック
¥110
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3
2件のお客様レビュー
変形A5版、127ページの薄い小冊子で500円。クラシック音楽愛好家向けではなく、一般読者層向けのムック本なので、スルーしてきたが、特集の目玉である「クラシックの不滅の名盤ザ・ベスト100」に何が挙げられているか見てみたくなり、購入した。 記事の内容はひとまず置いておいて、本書...
変形A5版、127ページの薄い小冊子で500円。クラシック音楽愛好家向けではなく、一般読者層向けのムック本なので、スルーしてきたが、特集の目玉である「クラシックの不滅の名盤ザ・ベスト100」に何が挙げられているか見てみたくなり、購入した。 記事の内容はひとまず置いておいて、本書の特徴として挙げられるのは、まずオールカラーということ。これは見栄えがするので良い点である。次に気付く特徴は、文字が小さいということ。これは大きな欠点である。記事によって文字の大きさが違うが、記事の8割方は、かなり文字が小さい。CDのライナーの文字サイズと同様か、それ以上の小ささである。普通の本や雑誌では、なかなかお目にかかることのない小さなフォントサイズで驚いた。 私は一応全ての記事を読んだが、このように細かい文字でびっちりと段組してあるこの構成を一目みただけで、内容云々の前に、読む気がなくなる人も少なくないと想像される。 内容は、個人的には、執筆陣もお馴染みの人がほとんどで、既にどこかで何度も読んでいて、知っているばかりだったが、門外漢向けの入門書としては悪くないのではないかと思えた。 ただ、「クラシックの不滅の名盤ザ・ベスト100」は、入門者には適さないセレクトになっている点は要注意だ。名盤の選者は5人で、その内の3人は「レコード芸術」誌の人気企画「名盤名盤」の常連であり、名盤を選ぶことには慣れている人たちだが、それでこの結果か?と訝しんでしまう。 おそらく本書の編集者は、5人の選者たちに、これが一般読者層向けの本であり、入門者向けの特集だということを考慮して選んでくださいとは依頼しなかったのではないだろうか。 交響曲の第1位は、ワルター指揮コロンビア響による1958年録音のベートーヴェン:交響曲第6番「田園」である。これが交響曲の第1位になっているのには驚いた。このワルター盤は、もちろん世に広く知れ渡っている名盤には違いがない。何度も再発売され、リマスターも何度も行われているので、私もマスター違い、盤違いで、5枚も持っているほどで、名盤中の名盤であると思う。しかし、それは「田園」の名盤に限っての話である。 「田園」の名盤を選ぶという企画で、ワルター盤が1位に選ばれているのなら、それは大いに結構であるが、交響曲の第1位としてベートーヴェンの交響曲第6番「田園」がふさわしいかどうか?そこが問題である。たとえ、ベートーヴェンの交響曲だけに限ったとしても、「田園」が1位にくるということはないと思うのだが。 協奏曲の第1位はチョン・キョンファの「四季」である。この場合、ヴィヴァディの「四季」が1位というのは、曲としては順当なものであると思える。が、チョン盤が1位というのは客観的に見ていかがなものかと思う。10人の選者が選ぶレコード芸術の「名曲名盤」の企画で、過去3回分を見直しても、10人の内、誰一人もトップ3に選んでいない盤である。なぜ、その様なチョンの「四季」が協奏曲の第一位に選ばれたのか。それは、宇野功芳氏のイチオシの盤であり、この盤が37ポイント獲得しているということは、宇野氏が1位の20点を付け、この選者のメンバーなら、あとは許光俊氏がたまたま17点を付けたからということになるだろう。 この結果を見るとランキングの選考方法について考えさせられるものがある。本書の選考方法ではランキングとしては不完全すぎる。 本書の選考方法は、交響曲、管弦楽、協奏曲、器楽曲、室内楽の5ジャンルごとに、5人の選者にベスト20を選出してもらい、1位から20位にそれぞれ20ポイントから1ポイント振り当てポイントを集計するというもの。 5人の選者が同じ盤を1位に選べば満点の100点になるが、この選考方法では、選択範囲が広くなりすぎてしまい、票がバラけてしまうのは必至である。事実、多くの票を集められたのは、器楽曲で72ポイントを獲得したグールドのゴルトベルグ変奏曲(1981年盤)しかいない。したがって、誰にとってもあまり有用でないランキングとなってしまっている。 では、どのような選考方法にすれば有用なものになっただろうか?私なりに考えてみたのだが、同じく5人の選者に依頼するとしたら、まずそれぞれのジャンルごとに、入門者に聞いてもらいたいおすすめの名曲を10曲選んでもらう。そして、その選ばれた名曲の上位5曲に対して名盤を1位から3位まで3枚選んでもらい、それぞれ3点から1点を付ける。そして、誰が何を選んだか明記し、集計して発表したなら、一般層に向けた有用なランキングになったのではないだろうか。
Posted by 
コンビニの雑誌棚に陳列されていてふと手に取ったら、この奥深さ。読み応えあり。「カラヤンの帝王学」ではクラシック音楽を映像化させることで新たな世界を切り開いたイノベーターとしての姿、そして完璧主義と言われるまでの「こだわり」をオーケストラと共に追究し実現させた統率力が描かれている。
Posted by 



