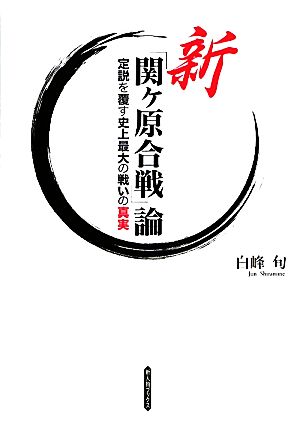
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-07
新「関ヶ原合戦」論 定説を履す史上最大の戦いの真実
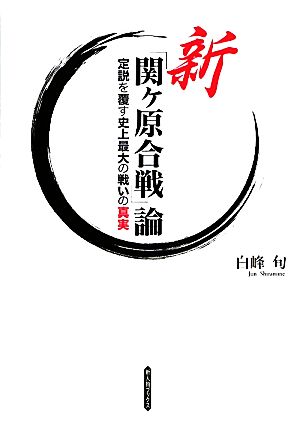
定価 ¥1,540
715円 定価より825円(53%)おトク
獲得ポイント6P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新人物往来社 |
| 発売年月日 | 2011/03/24 |
| JAN | 9784404039927 |
- 書籍
- 書籍
新「関ヶ原合戦」論
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
新「関ヶ原合戦」論
¥715
在庫なし
商品レビュー
3
2件のお客様レビュー
惣無事令体制の崩壊と私戦の復活というのはこれまでにない見方かな。結果としての二重公儀体制については笠谷本で既読だったが、その背景・経緯の確認ができた。 直江状も原本が存在せず21回も書き写しがあり、元々は家康への挑戦状ではないという解釈も興味深い。 著者らの功績の結果、今現在は関...
惣無事令体制の崩壊と私戦の復活というのはこれまでにない見方かな。結果としての二重公儀体制については笠谷本で既読だったが、その背景・経緯の確認ができた。 直江状も原本が存在せず21回も書き写しがあり、元々は家康への挑戦状ではないという解釈も興味深い。 著者らの功績の結果、今現在は関が原への見方も多様性が出てきているので7年前の出版当時はよかったのかもしれないが、今読むと「従来の見解」とされているのもやや偏見かなという気はする。ただし、三成悪人論は下火にはなったと思うが、家康が9回裏に大逆転という認識までには至っていないような。
Posted by 
最近は有名な歴史上の事件の真相解明に関する研究が進んでいるようで、多くの事件には、歴史上で伝えられてきたものとは異なることがあるようです。 桶狭間の戦いや本能寺の変もそうなのでしょうが、この本では江戸幕府を開くのを決定的にした「関ヶ原の戦い」について研究された本です。 堺屋太...
最近は有名な歴史上の事件の真相解明に関する研究が進んでいるようで、多くの事件には、歴史上で伝えられてきたものとは異なることがあるようです。 桶狭間の戦いや本能寺の変もそうなのでしょうが、この本では江戸幕府を開くのを決定的にした「関ヶ原の戦い」について研究された本です。 堺屋太一氏が20年以上前に書かれた「巨いなる企て」を読んで、石田三成の企画力の凄さを感じましたが、この本を読んで感じたことは、少なくとも彼は当時の政権の権力や権威に基づく行動を起こしていて、徳川家康の行動こそが「クーデター」だったと思います。 また、関ヶ原の戦いを9月15日の一日だけの戦いではなく、長期の戦い(5か月)と捉えるのは興味ある視点でした。 以下は気になったポイントです。 ・関ヶ原の戦いは、善(家康)と悪(三成)の単純な戦いを意味するのではなく、石田三成・毛利輝元を中心とする反家康グループと、家康とそのシンパの武将を中心とする家康グループの当時の国政の最高レベルの熾烈な権力闘争である。(p9) ・本書における新しい視点は、1)石田三成~関ヶ原の戦いまでの政治体制を石田・毛利連合政権である(家康は公儀から外されている)、2)東軍西軍ではなく、家康vs反家康グループの戦い、3)戦い前夜は「私戦の復活=惣無事令体制の崩壊」である(p11) ・6月16日に家康が上杉討伐のために大阪城を出陣してから、9月15日の本戦を経て、各地(東北、九州)での戦いが終息する11月頃までの5か月の長期の戦いであった(p23) ・関ヶ原の戦い(本戦)に対する支戦としては、1)伊達、最上が関係した東北での戦い、2)前田が関係した北陸での戦い、3)黒田、加藤が関係した九州の戦いがある(p26) ・家康の大阪城出陣から1か月後の7月17日に大阪三奉行(長束、増田、前田)が出した「内府ちかひの条々」13ヶ条を諸大名に出して家康を政治的に弾劾したので、家康が公戦に偽装したのが失敗した(p37) ・石田・毛利連合政権は、2大老(毛利、宇喜多)と4奉行(石田、長束、増田、前田)という体制で政権中枢が構成されている、これは家康が秀吉の後継者である秀頼を見捨てたので、家康を豊臣公儀から排除したことを天下に明示した(p95、98) ・毛利輝元が大阪城西の丸に入城して、それまで残っていた家康の留守居500人が追い出されて伏見城へ移っている、その後、石田・毛利連合軍が伏見城を攻め落とした(p99、103) ・細川忠興の改易処分は連合政権の成立直後に実施された、但馬・丹波国の諸大名は丹後国への出陣を命じられている(p105) ・南宮山に展開していた毛利秀元などの部隊は、大垣城の救援(石田軍が籠城を続けた場合の後詰)が目的であり、関ヶ原の戦いには参加していなかった(p156) ・徳川家康の動員兵力は、76,700人を超えるが、秀忠別働隊(38,000)を差し引くと、関ヶ原の戦いに参加した家康直属軍は38,710人となる(p164) ・石田軍の人数は少なく(寝返り分を加えても46,000)、家康連合軍(87,000:南宮山への備えた人数を差し引いた数)の半分程度であったので、決着が1日でついてしまった(p165) ・江戸城普請における公儀普請奉行は合計8名であるが、秀忠から4名、大御所から2名、豊臣から2名であり、慶長11年当時の公儀が二重体制であったことを明確にしている(p182) 2011/8/13作成
Posted by 



