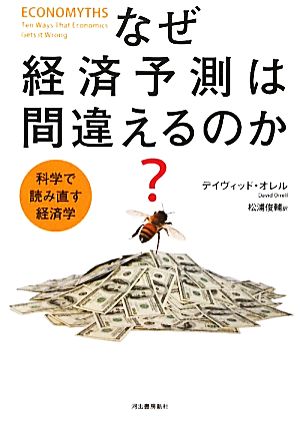
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-12
なぜ経済予測は間違えるのか? 科学で問い直す経済学
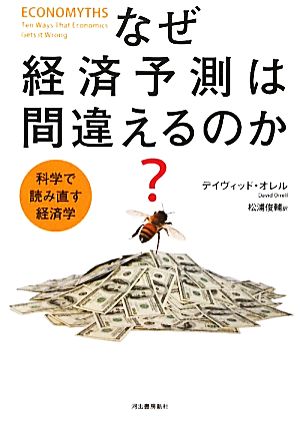
定価 ¥2,640
220円 定価より2,420円(91%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 河出書房新社 |
| 発売年月日 | 2011/02/24 |
| JAN | 9784309245416 |
- 書籍
- 書籍
なぜ経済予測は間違えるのか?
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
なぜ経済予測は間違えるのか?
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.3
6件のお客様レビュー
新古典派経済学の理論の前提は市場が善であることのようである。個人は個別に最適な行動を取るとか、需要と供給は最適な点で均衡するとか。実際の事象はそうではないのに。リーマン危機で、金融業界の論理が倒錯していることがよく分かった。
Posted by 
『なぜ経済予測は間違えるのか?』デイヴィッド・オレル(河出書房新社) 150年もの間、常識とされていた経済学の基礎をなす理論に致命的な欠陥があったとしたら、どうだろう? この本は、そのような仮説のもとに非線形力学、ネットワーク科学、複雑系理論、生態学、人間行動学、神経経済学な...
『なぜ経済予測は間違えるのか?』デイヴィッド・オレル(河出書房新社) 150年もの間、常識とされていた経済学の基礎をなす理論に致命的な欠陥があったとしたら、どうだろう? この本は、そのような仮説のもとに非線形力学、ネットワーク科学、複雑系理論、生態学、人間行動学、神経経済学など、比較的新しい科学を用いて従来の経済学にアプローチし、ほころびを指摘していく内容となっている。 主張が正しければ日本をはじめ、ほとんどの国が間違えた(ネズミ講に酷似した)システムで経済を回転させていることになる。ある意味、怖い。思い当たる節が多くて。 それにしても、翻訳本は読みづらい。経済学と自然科学は特にその傾向が強く、日本語になっていない文章が目立つ。専門分野になると和訳も限界があるのはわかるが、もう少し何とかなるまいか。
Posted by 
この手の本はいくつかあるが、経済学に身を置く以外の著者としてとても新鮮さを放っている。 そしてそれと同時に、経済学がどのようにして現在の理論体系まで発展したか、といった歴史的な考察も含めかなり正しく描写されている。 とりわけ現在の経済学の基礎が「物理学」を目指して作られた、という...
この手の本はいくつかあるが、経済学に身を置く以外の著者としてとても新鮮さを放っている。 そしてそれと同時に、経済学がどのようにして現在の理論体系まで発展したか、といった歴史的な考察も含めかなり正しく描写されている。 とりわけ現在の経済学の基礎が「物理学」を目指して作られた、という点は誰もが感じていて(今でも大部分の経済学者はそうしたことを念頭において「正確」な理論を作ろうとしている)が そうしたアプローチが現実をモデルに投射するのではなく、モデルを先に作って現実を見るということをしてきたと指摘している。 全くこの点には同感で、僕は経済学が社会「科学」とは呼べないと思う理由もそこにある。 かといって、それと同時に、それを覆すような別の枠組みが出てきていないのも事実だ。 仮説(理論)はデータを集めてきたからといって棄却はされず、新たな仮説、パラダイムがでてくることによって初めて覆される。 本書はそんな新たなパラダイムの萌芽をいろいろな分野の研究をもとにフィーチャーしている。 著者は社会科学として経済をとらえると、統一的な理論ではなく、「つぎはぎだらけでもいいので」使える理論でいいのではないかと投げかける。 それは美しさがない分かっこはよくないが、社会科学としての目的を考えるとどちらであるべきか、というのは明確である。 まさにそうした新しいフェーズに移ろうという時期にさしかかっているという印象を感じた。 そしてそれをまさに進めるのが僕たちのような存在なのではないかということも同時に感じた。
Posted by 



