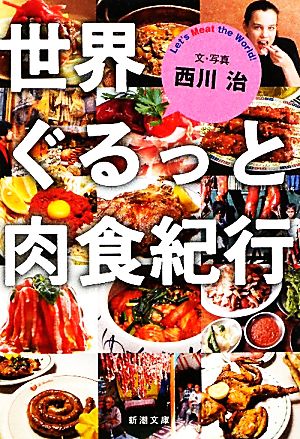
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
- 1224-06-04
世界ぐるっと肉食紀行 新潮文庫
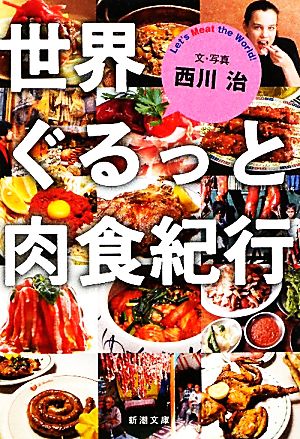
定価 ¥693
110円 定価より583円(84%)おトク
獲得ポイント1P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:12/9(火)~12/14(日)
店舗到着予定:12/9(火)~12/14(日)
店舗受取目安:12/9(火)~12/14(日)
店舗到着予定
12/9(火)~12/14

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
12/9(火)~12/14(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社 |
| 発売年月日 | 2011/01/28 |
| JAN | 9784101333533 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
12/9(火)~12/14(日)
- 書籍
- 文庫
世界ぐるっと肉食紀行
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
世界ぐるっと肉食紀行
¥110
在庫あり
商品レビュー
4
10件のお客様レビュー
とにかく肉・ニク・にきゅ❤ モンゴルで羊1頭を屠って、余すところなく食すとか。 ウィーンのウィンナシュニッツェルとか…ステキだ! 『朝食紀行』も面白かったけど、この『肉食紀行』も、良いですね~。
Posted by 
読書録「世界ぐるっと肉食紀行」3 著者 西川治 出版 新潮社 p76より引用 “ いろいろなところで、いろいろな食べ物 を撮影していると、遠く離れた国同士にどう してまったく同じような調理法や加工品がう まれたのだろうと、不思議におもうことがあ る。” 目次より抜粋引用 “...
読書録「世界ぐるっと肉食紀行」3 著者 西川治 出版 新潮社 p76より引用 “ いろいろなところで、いろいろな食べ物 を撮影していると、遠く離れた国同士にどう してまったく同じような調理法や加工品がう まれたのだろうと、不思議におもうことがあ る。” 目次より抜粋引用 “牛を食う 豚を食う 鶏を食う 羊を食う 内臓を食う” 写真・文筆家・画家でありながら、料理研 究家としても多くの著作を持つ著者による、 多くの国で食べてきた肉料理について記した 紀行エッセイ。 スーパーで手に入るような身近な肉から各 国現地でした食べられないような肉まで、一 冊丸ごと肉尽くしな内容となっています。 上記の引用は、世界で美味しいと言われる 生ハム三種について書かれた一文。 元の肉が同じような物であると、美味しく食 べる方法も同じように収束するのかもしれま せんね。似たような環境で生きる生き物が、 似たような姿かたちに進化するという話を思 い出しました。 ずっと肉肉肉、一冊通して読もうとすると、 疲れる・胸焼けする人もいるかもしれません。 他の食材の本と合わせて読むと、その日の食 事メニューのアイデアも浮かんで良いのでは ないでしょうか。 ーーーーー
Posted by 
文章に独特のリズムがある気がする。 著者西川さんのものを読むのはこれが最初。 写真家が本業というだけあって、ふんだんな写真がこうきしんをそそる。 韓国の焼肉、モンゴルの羊料理、イタリアのモツ料理、ベトナムの蛇やカエルの料理などなど、様々な国の肉料理が紹介される。 モンゴルなんぞ...
文章に独特のリズムがある気がする。 著者西川さんのものを読むのはこれが最初。 写真家が本業というだけあって、ふんだんな写真がこうきしんをそそる。 韓国の焼肉、モンゴルの羊料理、イタリアのモツ料理、ベトナムの蛇やカエルの料理などなど、様々な国の肉料理が紹介される。 モンゴルなんぞは、おそらくそのうち仕事で行かねばならないことになりそうなんだけど。 羊料理は、残念ながらやはり匂いがダメなのだけれど、現地で認識を改めることができればいいな。 この手の本を読むたびに、自分の食に対する偏狭さが身に染みて感じられる。 ついでに小さくなっていく自分の胃袋にも若干の不安を覚えつつ…。
Posted by 
