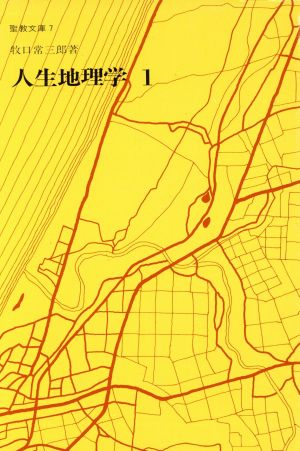
- 中古
- 書籍
- 文庫
人生地理学(1) 聖教文庫
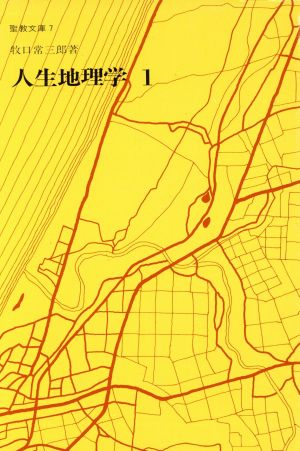
定価 ¥491
440円 定価より51円(10%)おトク
獲得ポイント4P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 聖教新聞社 |
| 発売年月日 | 1993/11/01 |
| JAN | 9784412002630 |
- 書籍
- 文庫
人生地理学(1)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
人生地理学(1)
¥440
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
明治36(1903)年の刊行。 人間と自然との関係を定性的に記述している。思考法がアクチュアルで、軍事、文明、宗教、気性についての記述が優れているのではないか。 国体、大和民族に言及した部分など時代の制約を感じるが、例えば日本についても単なる宣揚ではなく、その欠点も挙げ、全体...
明治36(1903)年の刊行。 人間と自然との関係を定性的に記述している。思考法がアクチュアルで、軍事、文明、宗教、気性についての記述が優れているのではないか。 国体、大和民族に言及した部分など時代の制約を感じるが、例えば日本についても単なる宣揚ではなく、その欠点も挙げ、全体的にはバランスが取れている。 時代を考えれば、驚くほど偏見に陥ることなく、断定的な物の言い方を避けている。世界はおろか宇宙を取り上げ、視野も広い。 1巻は、「人生地理学」という学問、書の題名の解題から始まって、郷土の重要性を説き、各論に入っていく。 この時期には日蓮に帰依していなかった牧口だが、日蓮への記述に加えて、様々な内外の宗教家への言及が敬意をもって行われているのに好感を抱いた。 ・「吾人は郷土を産褥として生まれ、かつ育ち、日本帝国をわが家として住し、世界万国を隣家として交り、協同し競争し、和合し衝突し、もってこの世を過しつつあるものなることを自覚する」「その起発点としての郷土観察が、公平に世界を達観する上において、はた正当に各自生活の立脚点を自覚する上において、欠くべからざる」 ・郷土とはなんぞや。その範囲は観る人の立脚地により異なる。居室→村→県→国→現世。 ・「慈愛、好意、友誼、親切、真摯、質朴等の高尚なる心情の涵養は、郷里を外にして容易にうべからざことや」 ・吉田松陰「地を離れて人無く、人を離れて事無し。人事を論ぜんと欲せば、まず地理を審らかにせざるべからず」 ・宗教的交渉:吾人は他の一切の万物とともに、整然たる秩序が存在。吾人の勢力は微弱なり。畏怖と敬虔とは胸中に溢れ集まる。 ・「島民は鞏固なる愛国心、愛郷心に富み、一朝外患の迫るにあたっては、一致団結その身を君国に捧ぐるの概あり。」 【目次】 緒論 一 地と人との関係の概観 二 観察の基点としての郷土 三 いかに周囲を観察すべきか 第一編 人類の生活処としての地 第一章 日月および星 一 日光と人生 二 温熱と人生 三 太陽と精神的人生 四 日本人と太陽 五 太陰ならびに星と人生 第二章 地球 一 地球の形状と人生 二 地球の大きさと人生 三 地球の運動と人生 四 地球の部分と人生 五 水界および陸界 第三章 島嶼 一 島国の特質 二 島の種類と人生 三 貿易上および国防上における島 四 島と英雄および罪人 五 開明時代における島 第四章 半島および岬角 一 半島の特質および成因 二 半島と文明 三 半島の配置ならびに運命 四 半島の利用 五 岬角と人生 第五章 地峡 一 地峡の種類ならびに地峡と人生 二 地頸に対する近世の努力 第六章 山岳および渓谷 一 山の高度と人生 二 山の各部と人生 三 山の集合と人生 四 山脈の方向と人生 五 山脈の成因と人生 六 火山と人生 七 渓谷と人生 八 約論 九 開明人に対する山 第七章 平原 一 平原と人生 二 平原の区別 三 高原と人生 四 河谷低原と人生 五 海浜低原と人生 六 各種平原の分布
Posted by 
著者は創価教育学会(創価学会の前身)の創立者にして会長。そして,本書は明治36(1903)年に発行。日本で初めての地理学の学会は1879年創立の東京地学協会だが,まだ制度的な地理学は確立しておらず,この頃日本人によって書かれた地理学書といえば,明治27(1894)年に『地理学考』...
著者は創価教育学会(創価学会の前身)の創立者にして会長。そして,本書は明治36(1903)年に発行。日本で初めての地理学の学会は1879年創立の東京地学協会だが,まだ制度的な地理学は確立しておらず,この頃日本人によって書かれた地理学書といえば,明治27(1894)年に『地理学考』の書名で出版された内村鑑三の『地人論』や同じ年に出された志賀重昂の『日本風景論』(その前1889年に『地理学講義』あり)などがある。 一昨年度の講義で『地人論』を扱った際,本書も一緒に買ってちょっと読んでいたが,今回きちんと通読した。「人生」とは「人の生活」のことであり,人生地理学とは人文地理学とほぼ等しい。しかし,志賀や内村の書と同様に,その内容は現在の人文地理学とは異なり,自然地理学的な内容をかなり含んでいる。ということで,本書は5分冊のうちの1冊目だが,目次は以下の通り。 緒論 第一編 人類の生活処としての地 第一章 日月および星 第二章 地球 第三章 島嶼 第四章 半島および岬角 第五章 地峡 第六章 山岳および渓谷 第七章 平原 19世紀ドイツの地理学者フンボルトの晩年の著作は『コスモス』と名付けられた。それを想起させるようなスケールの大きな目次。しかし,その内容は常に人間との関係が主眼にあり,太陽の光と熱がなければ動物としての人間の生命が維持されないということや,太陽暦にせよ,太陰暦にせよ,人間の生活の規則性を決めているのが天体の動きである。 まあ,そんな感じで,現代の私たちが理科や社会科の時間に習うような,地球の自転や公転,地軸の傾き,地形の成り立ちについて説明され,それらがいかに人間の生活に作用しているのかということを大胆に解釈していく。そう,『地人論』を読んでいても思ったが,かれらのいわんとする土地と人間の関係は,地図スケールで大地を見渡し,それをそのスケールに抽象化された生活様式の特徴とを関連づけるという,ある意味構造主義的な記号論に近い。 地理学という学問が日本にさほど根付いておらず,志賀や内田や牧口は狭い意味での地理学に囚われず,米国の地理学的なものを吸収しながら自由な発想で議論を展開しているといえる。ただし,本書については志賀からの引用が多いのは気になる。ともかく,思ったよりも読み応えのある本でした。機会があれば,2冊目以降も読んでみようと思う。
Posted by 



