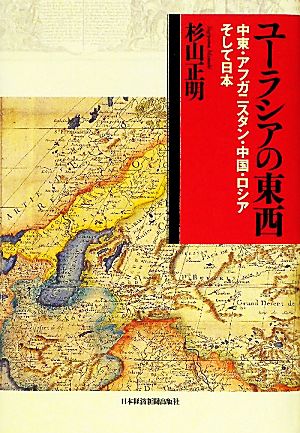
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-02-00
ユーラシアの東西 中東・アフガニスタン・中国・ロシアそして日本
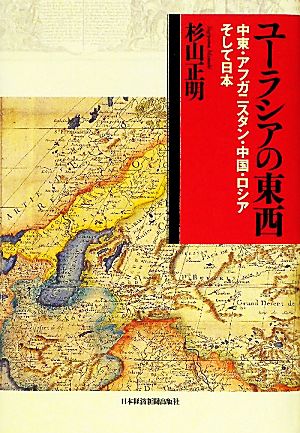
定価 ¥1,980
385円 定価より1,595円(80%)おトク
獲得ポイント3P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本経済新聞出版社 |
| 発売年月日 | 2010/12/18 |
| JAN | 9784532167714 |
- 書籍
- 書籍
ユーラシアの東西
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ユーラシアの東西
¥385
在庫なし
商品レビュー
4.3
5件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
地理的なものがそこにすむ民族の性質をつくりあげるのに関わっているということは分かるような気がする。 学校では西洋から見た歴史を習ってきたけれど、ユーラシアの真ん中あたりから世界史を見るとどうなるか。 イランのあたり、トルコのあたり、モンゴルのあたり、モスクワのあたり、北京のあたり、それらが力を持つと周囲に押し出してきた。東西、南北。 力を持つものが影響力を持つのは自然のことか。権力を集中させることによって発展させてきたものがあることは確か。 できれば楽していい思いしたい→権力に群がる→権勢の交代→古いものの粛清。どこを切ってもおんなじ金太郎あめみたい。 力づくで得たものはいつか奪われると学べれば歴史学というものはとても意味がある。 水が高いところから低いところに行くように、良いものが穏やかに広がっていく時代にそろそろなっているのかな。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2010年刊。 モンゴル帝国史を専門にする著者が、ユーラシアを軸に展開する歴史エッセイ。 ①モンゴルはユーラシア大陸における巨大陸上帝国➡現代の同様の帝国という意味での露中論(主に露)。 ②モンゴル帝国研究は東洋史・西洋史という日本的世界史研究の区分を超克・融合する上、国史と世界史という近代的国境線で区分する歴史研究の射程範囲の狭さを雄弁に語る素材であって、明治移入期の宿唖を克服できぬ現代日本の史学研究に痛烈なカツを。 ③モンゴル帝国と日本との同時代史と、日元交流・貿易に光を当て得る者として後醍醐天皇を提示。 ④上山春平京都大学名誉教授との対談、 そして ⑤国家という枠組みを超越した視座を持つ上で、世界各地に散らばる碑刻・拓本研究の重要性(そこで必要とされる多言語を操る力) が語られる。 歴史研究における国家単位を超えた複眼的・重層的な視座と、時代毎の比較の意義など、ナショナリズムという狭い視野に止まりがちな歴史研究の狭小さをこれでもかと感じさせるエッセイである。 著者は京都大学大学院文学研究科教授。 なお、世界史における銀産出とその移出入の意義に注目する要あるか。
Posted by 
一時期チンギス・カーンに関して読み漁ったことがあった。 その下地があるので杉山氏の言説はよく理解できた。 世界史のあり方、これまでの東洋史、日本史の諸先生方、いろいろと言い分があるのであろう。 大いに言って下さい。
Posted by 



