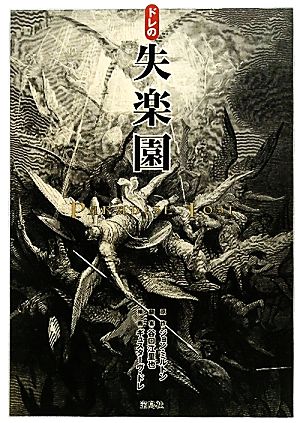
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1222-02-07
ドレの失楽園
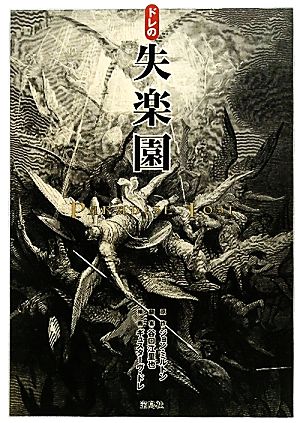
定価 ¥1,571
1,430円 定価より141円(8%)おトク
獲得ポイント13P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 宝島社 |
| 発売年月日 | 2010/11/11 |
| JAN | 9784796677295 |
- 書籍
- 書籍
ドレの失楽園
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ドレの失楽園
¥1,430
在庫なし
商品レビュー
3.7
7件のお客様レビュー
「失楽園」はミルトンによる17世紀イギリスを代表する叙事詩。この楽園を追放されるアダムとイヴの物語を題材に、19世紀の画家ドレが美しい銅版画を作成した。この版画が本書のベースである。但し物語の方は、ミルトンの叙事詩を大きく改編している。たまたま持っていた岩波文庫版の「失楽園」と読...
「失楽園」はミルトンによる17世紀イギリスを代表する叙事詩。この楽園を追放されるアダムとイヴの物語を題材に、19世紀の画家ドレが美しい銅版画を作成した。この版画が本書のベースである。但し物語の方は、ミルトンの叙事詩を大きく改編している。たまたま持っていた岩波文庫版の「失楽園」と読み比べて、違いに驚いた。 神に反逆し深淵に落とされたサタン(本書ではデビルと呼ばれる)が、楽園エデンに忍び込み、イヴを唆して禁じられた知恵の実を食べさせ、そのためアダムとイヴがエデンを追われる、という大筋には沿っている。しかし個々の場面や、サタンを初めとする登場人物の心理描写、振る舞い、その解釈など、ミルトンの作品から受ける印象との隔たりは大きい。版画と齟齬のある場面まである。ミルトン作品のダイジェストではなく、あとがきにあるように、谷口江里也による物語と捉えなければならない。 ドレの版画作品を楽しむのには良い本であるが、ドレにインスピレーションを与えたミルトンの叙事詩の調子を味わうには適していない。特にそのキリスト教的世界観を、正確には伝えていないと思う。その前提で、物語としては面白く読めた。
Posted by 
ギュスターヴ・ドレは19世紀後半に活躍したフランスの画家・彫刻家である。特に、端正で緻密な版画は、数多くの古典や童話、詩の挿画として広く世間に知られ、生前から国際的に有名な画家であったという。「聖書」やダンテの「神曲」では、壮大なスケールでその世界を描いている。 「ドレの○○」...
ギュスターヴ・ドレは19世紀後半に活躍したフランスの画家・彫刻家である。特に、端正で緻密な版画は、数多くの古典や童話、詩の挿画として広く世間に知られ、生前から国際的に有名な画家であったという。「聖書」やダンテの「神曲」では、壮大なスケールでその世界を描いている。 「ドレの○○」シリーズは宝島社から刊行されており、古典作品をドレの絵と抄訳で紹介しようというもので、私は前に、『ドレの神曲』を読んだ。訳構成はいずれも谷口江里也。 『神曲』のときはさらさらっと読んでしまったのだが、本書は序盤から躓いた。 いや、ものすごく読みやすいのだ。しかし読みやす「すぎる」。まるでSFアニメ超大作だ。いや、SFアニメはアニメでいいのだが、えっと、ミルトンは本当にこう書いたのか・・・? 何と言っても冒頭の神々や場所などの名称がすごい。超宙空(パシオン)、創造神(オウエイ)、大善童神(ビルティーニョ)、美貌神(ルチフェル)、という具合。 ストーリー的には、ルチフェル(=ルシファー、デビル、サタン)が神に叛逆を企て、敗れた結果、「超深淵」に堕とされるのだが、楽園エデンに暮らす人間を陥れることで復讐を果たす。そして人間が楽園を追放されるまでの物語である。 のだが。読み進めるにつれて違和感が高まる。 そもそもミルトンはイギリス人なのに、ビルティーニョってスペイン語じゃないのか・・・? 神々の持つ「神力」に「フォース」ってフリガナが振ってあったら、それは某SF映画シリーズなんじゃ・・・? オウエイなんて聞いたことないけど、あ、もしかして「ヤハウェ」のこと・・・? 「超深淵」から抜け出したルチフェルがエデンに向かう様子はどうも宇宙を飛んでいるみたいだけど、ミルトンの宇宙観ってどうなっていたんだ・・・? 謎が深まるうち、某所のカスタマーレビューや宝島社のHPを見ていて、はたと気が付いた。これはいわゆる「超訳」というやつか! そもそも表紙に「翻案」と書いてあるじゃないか。 ・・・いや、これは不注意だった。そもそも「失楽園」の原作がちょっとボリュームありそうだから、そしてドレの絵も見たいし、という動機が不純だった。 これはミルトンの失楽園を下敷きに、ドレの挿画も使って、谷口氏が1つの世界を描いてみたわけで、これが「ミルトンの失楽園」だと思ってはいけないわけだ。用語にスペイン語が使用されているのも、解説を読むと、谷口氏が長年暮らしていたことによるらしい。 えーと、いずれにしても、これではミルトンがどのような世界を描いていたのかがさっぱりわからない。サタンの叛逆が描きこまれているのは確かなようだが、それが創造者に疑問を突き付けているということなのか、そしてそのこととミルトン自身の経歴とどう関わりがあるのか等、もう少し考えてみたいところだ。 ドレの絵はすばらしかったが、収録されているのは「失楽園」だけでなく、「旧約聖書」からのものもあるのではないかと思う。 とにもかくにも、お手軽に済ませようと思っていた自分がバカだった、の一言。 急がば回れ。 近いうちにオーソドックスな版を読もうと思う。 *1つ勉強になったのは、ビルティーニョの別名がエルニーニョなんですが、これを読んでいて脳内は海水温上昇と異常気象に(^^;)。もちろんエルニーニョ現象を指しているわけではなくて、エルニーニョというのはもともとスペイン語で「男の子」の意味なんですね。ですから「the boy」=「幼子」、つまりキリストを指すわけです。気象用語となったのは、毎年、クリスマスの頃、ペルー沿岸で発生する暖流をそう呼んでいたことからきているようです(ちなみにラニーニャは女の子)。
Posted by 
本を読んで泣くなどありえない私だが、そして本書を読んで泣いたわけでもないのだが、飲み会翌日の寂しさを抱えながら歩く道すがら、膝を抱えたルチフェルの姿を思い出しうるっときてしまったよ。 前向きな人生観から離れよう離れようとしてきたが、齢約30にして初めて「ルネサンス」(再生)の実...
本を読んで泣くなどありえない私だが、そして本書を読んで泣いたわけでもないのだが、飲み会翌日の寂しさを抱えながら歩く道すがら、膝を抱えたルチフェルの姿を思い出しうるっときてしまったよ。 前向きな人生観から離れよう離れようとしてきたが、齢約30にして初めて「ルネサンス」(再生)の実感を得たような気がする。 敗北者と自覚することで始まる物語。 創造主も天使も堕天使も人間も。 生まれたからには伸びずばなるまい。 生きるとは常に可能性を更新し続けることだ。 楽園を失う=追放される=解放される。 悲しみや絶望と、喜びや希望が、限りなく重なり合っている。 ここから遡るようにしてイエスの存在も書き換えられる。 ミルトン作、谷口氏(うさんくさい)翻案(ほぼ創作に近いとのこと。うさんくさい言語感覚乱発)、ドレ画。 これは必ず岩波に進まねば。 花の香りを含んだ一陣の風がわれわれの背後に。
Posted by 



