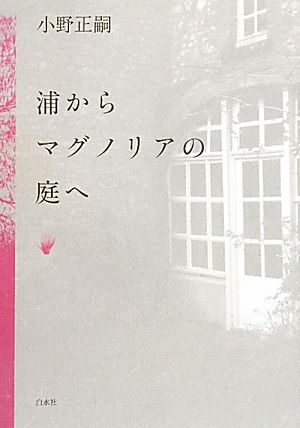
- 中古
- 書籍
- 書籍
浦からマグノリアの庭へ
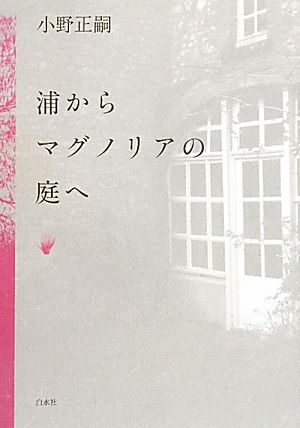
定価 ¥2,420
2,365円 定価より55円(2%)おトク
獲得ポイント21P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 白水社 |
| 発売年月日 | 2010/08/25 |
| JAN | 9784560080863 |
- 書籍
- 書籍
浦からマグノリアの庭へ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
浦からマグノリアの庭へ
¥2,365
在庫なし
商品レビュー
3.3
4件のお客様レビュー
フランス滞在記は面白かった 書評がわかる人にはわかるという書き方なので作品がわからないと少しつらい。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
小野正嗣氏のエッセイ『浦からマグノリアへ』を読了。小説家ではある著者が書いたエッセイであり、書くという事の源泉に関していくつかの観点から触れたエッセイ集となっている。 エッセイに寄ると著者が最初の小説を書いたのもオルレアンに居たときだそうで、自分が居た大分の生家近辺の集落の末尾に浦という一文字がついていた故故郷を浦とよび一報フランスオルレアンの庭にあったのがモクレン科のマグノリアの花ということで、著者の人生で二つの大事な時期を切り取った二つの言葉からこの本タイトルが出来ている。 いくつかのエッセイの中で多くを割いているのが彼の人生の中で作家となるための人生の基盤となった生活経験であるフランス オルレアンにおいての大学教授クロードとその妻エレーヌと一緒に暮らした(暮らしたというより居候をさせてもらっていたというのが正しいが)日々に関する回想だ。クロードとエレーヌは博愛主義の見本のような方達で日本人である著者のみならず困っているアフリカからの移民や地元でも生活苦の老人まで幅広く助けている人素晴らしい夫婦で、彼達の人類愛あふれるエピソードが次々と語られていく。 その次に多くページが割かれているのは書く事と読む事の関係に関してだ。著者は読む事は書く事にとっての大事なベースになるものだとしている。大江健三郎や中江健次を引っ張りだして彼達の著作に大きく関わっただろう先人が綴った作品に関しての分析を進めている。また自分自身でも普遍的な文学を書こうとした時に彼は世界の文学に触れるべきとして、ラテン・中国・ロシア・アメリカなどなどの様々な文学に触れる事を自分に課している。以前の日本文学といえば欧米文学および日本文学であったが、いまは世界の人たちの作品が手に入るので広くそれらに触れるべしとしている部分には共感を覚えた。翻訳物を毛嫌いしていたがこれからはちょっと色々な国の文学に触れようと思った、 もう一つ面白かったのが歴史的作品の翻訳に関しての考察で、翻訳という物の難しさ、奥の深さをラブレーを訳した渡辺一夫氏と宮下志朗氏の翻訳を詳細に比較しながら語ってくれていてこのエッセイもかなりインパクトがあり自然と唸らされた。 これらの教養触れる文学を志す人の綴ったエッセイと呼ぶのは少し軽く聞こえすぎるくらいの深い著者の考察を数々を読むBGMに選んだのがChick Coreaの"Piano inprovisation Vol .1" なまピアノのチックはいいなあ。 https://www.youtube.com/watch?v=WKdYFAhHJOs
Posted by 
とある書店に併設してある喫茶店で本をよく読む。今までいろんな本をそこで読んでいるはずなのだが、とりわけその喫茶店と紐づけて思い出されるのが、小野正嗣さんの『森のはずれで』なのである。なぜなのかはわからないが… これは小野正嗣さんのエッセイ集。小野さんのものを読むのは久しぶりだ。 ...
とある書店に併設してある喫茶店で本をよく読む。今までいろんな本をそこで読んでいるはずなのだが、とりわけその喫茶店と紐づけて思い出されるのが、小野正嗣さんの『森のはずれで』なのである。なぜなのかはわからないが… これは小野正嗣さんのエッセイ集。小野さんのものを読むのは久しぶりだ。 経歴や文章で引用される書籍から見ても、どうしても堀江敏幸さんのようなエッセイを多少想像していたのだが、そこにはやはり作家なりの微妙な差異があると感じた。小野さんという人は、どうも人なつっこい人のような気がする。果敢に外に飛び出して、外の人間と接触するのが好きで、相手にも好かれるような人のような気がした。そして、それがいい方向に働いた文章たちがここにはある気がする。読んでいて非常に爽やかな気持ちになる。作家への素直な敬意が感じられるからだ。 ボルヘスについての文などを起点に考えると、小野さんは「書く人」であるよりも「読む人」であるという基本スタンスのようだ。「書く」という行為が、膨大な「読む」という行為を礎にしているその在り方がとても興味深い。普通は自分の作品を「見て見て」となるような気もするのに、そういう感じがあまり感じられないのである。そういうスタンスで自身を文学の海とつなげようとしているように思われる。扱う作家も自分がよく読んでいたものがけっこうあり、そこもまた嬉しい。 渡辺訳のラブレーと宮下訳のラブレーってそんなに違うのか… 渡辺訳を昔読んだのだが宮下訳でまた読んでみてもいいかもなあ。
Posted by 



