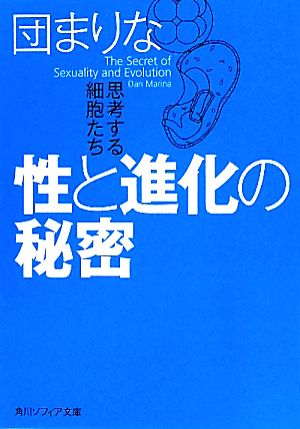
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-24-05
性と進化の秘密 思考する細胞たち 角川ソフィア文庫
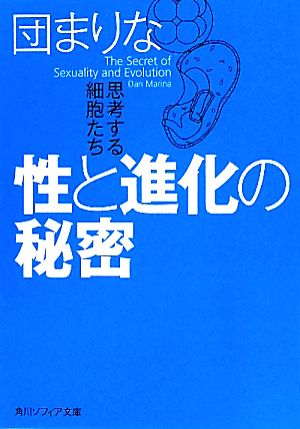
定価 ¥775
440円 定価より335円(43%)おトク
獲得ポイント4P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 角川学芸出版/角川グループパブリッシング |
| 発売年月日 | 2010/08/24 |
| JAN | 9784044094270 |
- 書籍
- 文庫
性と進化の秘密
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
性と進化の秘密
¥440
在庫なし
商品レビュー
3.8
5件のお客様レビュー
なかなかピンと来ない。発生の様子は「形の生物学」の方が分かりやすかった。階層性についても何とも言えない。遺伝するのはDNAではなく細胞質も含めた生物システム全体と言うのは結構耳にする説明。シンプルな自然選択以外の原動力が進化にはあるとしているが、それが何かは分からない。 ひとつ...
なかなかピンと来ない。発生の様子は「形の生物学」の方が分かりやすかった。階層性についても何とも言えない。遺伝するのはDNAではなく細胞質も含めた生物システム全体と言うのは結構耳にする説明。シンプルな自然選択以外の原動力が進化にはあるとしているが、それが何かは分からない。 ひとつ面白かったのは卵の細胞分裂について。まだ卵が小さい生物は普通の細胞同様に全割する。進化とともに卵が栄養を蓄えるようになって大きくなると全割は無理なので、部分割を工夫するようになる。しかし哺乳類になってまた卵が小さくなると、それまでの創意工夫はケロッと忘れて全割に戻る。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読み応えのある本である。 題名だけ見たときは、なぜオスはメスに惹かれるかなんてことを遺伝子と引っかけて書いてる本かと思っていたのだが、さにあらずである。養老孟司が「読み応えのある本ですから、懸命に読んでくださいね」と書くぐらいである。 本の主題は、生物の階層性(自然界にある物質の性格であり、上位の階層は下位の階層にない機能を持つ)と言う事である。原核細胞があるとき真核細胞にステップアップしたのであるが、真核細胞は飢餓状態になると合体して飢餓状態を乗り越えることをシステムとして行うことができるようになったのであります。 一単位の真核細胞はハプロイド細胞、合体したのがディプロイド細胞とよぶのだが、ディプロイド細胞は染色体を二組持つ。ハプロイド細胞もディプロイド細胞も構造はほとんど同じなのに、ディプロイドになると細胞間で仕事の役割分担ができるようになる。私たちが普段目にする生物は自分自身を含め大抵はディプロイド細胞でできている。コケ類や藻類の中にはハプロイド細胞が集まっただけの生物もいるらしい。 ところが、ハプロイド細胞が際限なく細胞分裂を繰り返すことができるのに対しディプロイド細胞は細胞分裂に制限回数があって制限回数に達すると死んでしまうのである。なぜかは不明。人間の細胞の場合52回ほど分裂すると死んでしまうらしい。 これを克服するために生まれたのが減数分裂によってハプロイド状態にもどってから再度合体する方法。このことは、生物が自分のアイデンティティを変えずに(人間なら人間、変えるならカエルという種で有り続けながら)複雑さの違う単位、階層の間を行き来するということである。同じものであり続けながら自分の複雑さを変えるというような事は自然界では外には見られないことである。 教科書では「遺伝子の組み換えが、有性生殖の本質である(目的である)」と書かれているが「有性生殖とは、生物が自分の『種』としてのアイデンティティを保ったまあm、ディプロイドとハプロイドという二つの階層を行き来して、ディプロイド細胞が運命づけられている、分裂の限界を克服するためのしくみ」というのが正しいという事だそうだ。その仕組みの中に次第にDNAを繕ったり組み替えたりする仕組みを重ねてきたという事である。 次の主題は、「DNAが決めていることは種よりもずっと階層的に下のレベルのことで、そこがいくら変わっても、上のレベルの種までは影響がおよばない」という事。 大腸菌に人間のインシュリンの遺伝子を入れるとインシュリンを生成する大腸菌ができるが大腸菌が大腸菌で無くなるわけではない。 種とはもっと複雑なもので、遺伝子から種の謎に迫ることはできない。 さらに「私たちはDNAだけでなく、配偶子という二匹の細胞の合体によって、ヒトとしての基本的内容のすべてを遺伝している」遺伝的プログラムが意味するものは、DNA上の情報などより遙かに複雑で多岐にわたる。 遺伝プログラムは、DNAではなく、細胞質、又は細胞構造そのものに書き込まれている。「ヒトとしての基本的な内容の全て」に至る鍵の多くは、受精卵の細胞質部分に潜んでいるはず。 と言う事で、遺伝というのは卵子=女性の細胞で引き継がれており、男性はそれにDNAという些末な情報を提供しているに過ぎないという事であります。
Posted by 
養老先生は解説で、団まりなさんの話は面白くて、よくわかると書かれている。同じ著者の本を3冊読んでいるが、私にはどれも難しい。イメージしやすいようにとの配慮で、いろいろなたとえを使って書かれているのだけれど、映像として頭に浮かぶことはない。そんな中、今回2ヶ所だけ線を引いた場所があ...
養老先生は解説で、団まりなさんの話は面白くて、よくわかると書かれている。同じ著者の本を3冊読んでいるが、私にはどれも難しい。イメージしやすいようにとの配慮で、いろいろなたとえを使って書かれているのだけれど、映像として頭に浮かぶことはない。そんな中、今回2ヶ所だけ線を引いた場所がある。代謝がうまく回るようになった細胞についてのくだり。外から物質をどんどん吸収するうちに身体が大きくなり割れる。「子どもを残そうとか、数を増やそうとして生殖が始まったのではないでしょう。そうではなくて、自分のシステムを保持するためには、割れて、適正な大きさを保たなければならない。これが生殖の根源的な意味だろうと思います。」「・・・分裂をくり返すうちにDNAに傷がたまったり、削り減ったりするらしいのです。このためディプロイド細胞は、ある程度以上分裂をくり返すと、それ以降は分裂できなくなって、死んでしまいます。・・・不思議なことに、減数分裂を通過するとその限界がはずれて、分裂の能力が元にもどるのです。・・・」何回も読んでる話しが出てくるのだけれど、理解は進まない。1回、映像を見せてもらいながら、講演でも聴く方が早いのかもしれない。あとがきが良い。これだけで1冊にしてほしい。実業家で男爵の祖父は団琢磨、発生生物学者の父は団勝磨。書かれていないけれど作曲家の団伊玖磨はいとこのようです。最後まで読むと養老先生が解説で書かれている。「読み応えのある本ですから、懸命に読んでくださいね。」そう易々と読める本ではないということだったのだろう。
Posted by 



