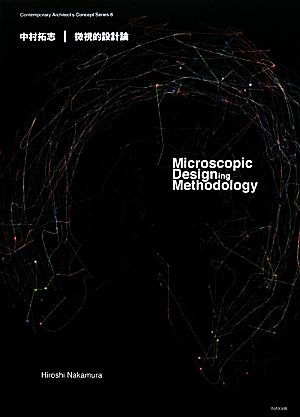
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1212-01-39
中村拓志 微視的設計論 現代建築家コンセプト・シリーズ6
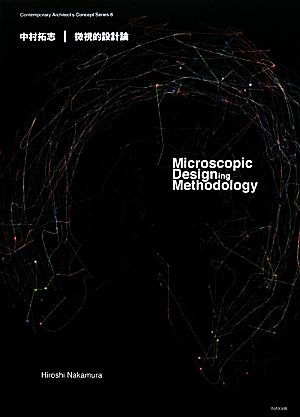
定価 ¥1,980
1,375円 定価より605円(30%)おトク
獲得ポイント12P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | INAX出版 |
| 発売年月日 | 2010/03/24 |
| JAN | 9784872751598 |
- 書籍
- 書籍
中村拓志 微視的設計論
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
中村拓志 微視的設計論
¥1,375
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.8
4件のお客様レビュー
建築をつくる上で身体に寄り添うことの大切さを学んだ。ただ、身体的な要素から全体をつくり出すことができるのは十分に建築の基礎をおさえてからだなと感じた。とてもあたたかい建築ばかりで、読んでいて楽しかった。
Posted by 
人が使うものを作る以上に、人に寄り添って作るのは当然だが、それが難しい。 仮にそのときの最高のものができたとしても、 次の瞬間には、人はすでにそれを体験した後なのだから、 その経験値が違う動きを許容するのである。 既存を経て、そこを超越し、未知に挑む。 それしか良いプロダクト...
人が使うものを作る以上に、人に寄り添って作るのは当然だが、それが難しい。 仮にそのときの最高のものができたとしても、 次の瞬間には、人はすでにそれを体験した後なのだから、 その経験値が違う動きを許容するのである。 既存を経て、そこを超越し、未知に挑む。 それしか良いプロダクトを作り続けることはできないと思った。 (以下抜粋) ○人も自然も物質も、遠くから眺めているだけでは、静止した退屈なオブジェクトである。しかし、対象に近づけば近づくほど、静止した全体のように見えていたものが、実は活き活きとした動的な存在であり、様々な関係性の中にあることがわかるようになる。 微視的設計論は運動の中から手掛がかりを見つけ出し、人の廻りに豊かな関係を作るための設計論である。(P.6) ○アールヌーボーのデザインに見られる、階段の手すりに絡まる蔦の装飾がつくるリズムと、人の昇降運動が同期したときに生まれる独特の感覚。ゴシックの教会の垂直線を強調した壁が誘引する目線の上昇運動と、それによって生成される崇高な感覚などは、建築の暗黙知がもたらす豊かなコミュニケーションである。(P.7) ○色は対象の表面にくっついていて、常に一定のものだと思いがちだが、絶対的なものではない。人間の網膜が特定の波長の光に対して受けた刺激を、脳で処理した結果である。テクスチャーや太陽高度などの環境条件、見る人の脳や網膜などの身体条件など、さまざまな関わりの中に存在するものなのだ。つまり、いつも同じに見える色も、実際は常に揺れ動いている。微視的方法論は、色の絶対性を否定し相対性をあぶりだす。その時、色は固定した物質から現象へと昇華するのだ。(P.23) ○微視とは、マクロ分析が導く抽象的で平均的な思考とは対照的に、個別的で動的な事象を微細に観察する行為だ。(P.66) ○物性へのアプローチが、建物の新しい機能や空間、現象へと至ること。それが使用者の知覚を喚起し、人と建築のコミュニケーションに発展しなければならないのだ。(P.66-67)
Posted by 
建築家・中村拓志による、「微視的設計論」について。 とても興味深い内容だった。 どこまでもどこまでも、絡み合う諸所の要素を考慮し、 それでいてかつ、決してただ調整的・予定調和的なアウトプットに陥らず、 あくまでも人。その機微により尽くした視点=微視的視点を重んじる。 受ける印...
建築家・中村拓志による、「微視的設計論」について。 とても興味深い内容だった。 どこまでもどこまでも、絡み合う諸所の要素を考慮し、 それでいてかつ、決してただ調整的・予定調和的なアウトプットに陥らず、 あくまでも人。その機微により尽くした視点=微視的視点を重んじる。 受ける印象は「理」 おそらく、超絶に頭がいいんでしょう。 左脳で考えて、右脳で出す人という印象。 その二つを、バランスしていく感覚がすばらしい。 いろいろな発見がありました。
Posted by 

