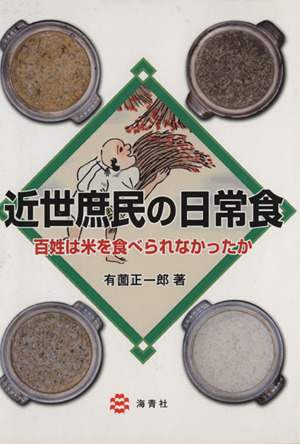
- 中古
- 書籍
- 書籍
近世庶民の日常食
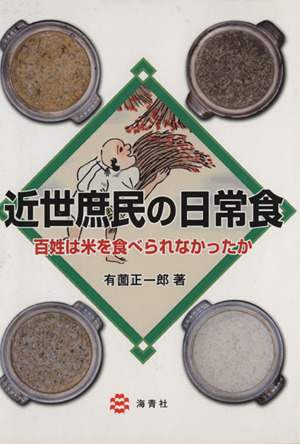
定価 ¥1,980
1,155円 定価より825円(41%)おトク
獲得ポイント10P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 海青社 |
| 発売年月日 | 2007/04/01 |
| JAN | 9784860992316 |
- 書籍
- 書籍
近世庶民の日常食
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
近世庶民の日常食
¥1,155
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
米を庶民が食べていたかの考察で滋賀、伊賀、山形秋田、信濃、薩摩、大村、沖縄翁長と来て、茄子と大根の原産地と気候型、人肥の話まで。方法論になっているところが教科書らしい。 サツマイモ食にご家族が賛同してくれないというのが心から同意できた。いや、それを続けさせてくれるだけで大したものだから。
Posted by 
副題は「百姓は米を食べられなかったか」 今回の伊豆旅行に携帯し宿で読書した。 2007年の刊。おそらく東京で購入したものと思われるが長らく 積読状態であったもの。 最初は懐疑的に読んでいたが、読み進むにつれて引き込まれて行った。 「百姓は米を食べられなかったか」という疑...
副題は「百姓は米を食べられなかったか」 今回の伊豆旅行に携帯し宿で読書した。 2007年の刊。おそらく東京で購入したものと思われるが長らく 積読状態であったもの。 最初は懐疑的に読んでいたが、読み進むにつれて引き込まれて行った。 「百姓は米を食べられなかったか」という疑問に対し著者は、滋賀県、 伊賀の国、山形県、秋田県、信濃国、九州大村領、沖縄県の事例を分析 して答える形で進めていく。 「百姓は米を食べられなかったか」というのは支配者側の視点だという。 宮澤賢治の詩に「1日に4合の玄米と味噌と少しの野菜を食べ」とあり働く百姓は飯を大食いして体力を維持していたという。 著者の推定によると、ハレの日には白米を食べ、日常的には米が半分位入ったかてめしを食べていたとする。 なぜかてめしを食べていたのか。米の消費量に対し生産量が低かったことが原因のようだ。当時は、田1反歩で玄米1石とれるのが普通であったという。(現在では1反歩で玄米3石とれるのというので3分の1だった。) 滋賀、伊賀、山形、秋田は米どころで、平均より多くの米を食べていた。 信濃は6割くらいが米で、残りを粉物で補う。 九州大村領や沖縄は米が少なく、さつまいもを食べていたという。 さつまいもの栄養価は高く、栽培が始まった事により人口が増えているそうである。 都市住民は米を食べていたが、これは米が1番安価な穀物であったからだそうだ。(手間賃、燃料費を考慮すると米が1番安価であった) 市場の流通網が未発達であった近世では地産地消が原則であった。ゆえに米どころでは、百姓も米を多く食べたという見方は面白かった。 (不満をあげれば、信濃の米食のデータが南信に偏っていたことか)
Posted by 



