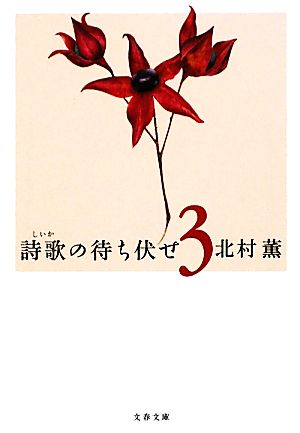
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1225-02-02
詩歌の待ち伏せ(3) 文春文庫
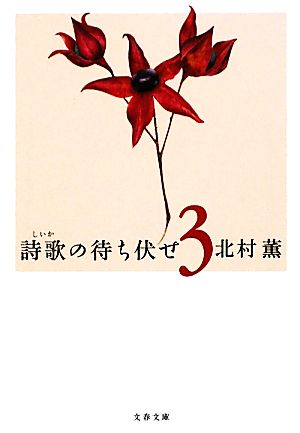
定価 ¥576
495円 定価より81円(14%)おトク
獲得ポイント4P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋 |
| 発売年月日 | 2009/12/10 |
| JAN | 9784167586065 |
- 書籍
- 文庫
詩歌の待ち伏せ(3)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
詩歌の待ち伏せ(3)
¥495
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.3
5件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
知らない作家の初めて見る作品ばかりで、新鮮でした。 普段読んでいる小説とは文体も使われる言葉も違っていて、調べながら読むのに苦労しました。そのぶん、新しい語や作家を芋づる式に知る良い機会になり、見聞が広がった気がします。 プレヴェールの邦訳を5つ挙げた初めの節が、予備知識がなくとも「詩って面白い」と思わせる導入になっていて、まさに待ち伏せされたという感じです。 橋本治の桃尻語訳は、紹介の上手さもあって読んでみたくなりました。引用があった中では、天野慶の短歌「君たちが……」がいちばん好きかもしれません。 浅学のため書いてあることの上辺すら理解できたとは思えませんが、なんとなくで楽しめました。 惜しむらくは、引用された文献を読もうにも、一般には入手困難な書籍が多そうです。「因果応報」の新訳をここで読めたのは、かなりラッキーなのかもしれないと思いました。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
もったいないからもうちょっと読まずに取っとこう、と思っていたのに…… 今回もすぐ読んでしまった、大好きなこのシリーズ。 『詩歌の待ち伏せ 3』 北村薫 (文春文庫) やっぱりいいです。 心が洗われるよホント。 日常いかに無駄に忙しがってせかせかと生きているのかということに改めて気付かされます。 大人の優雅な遊びという感じ。 ちょっぴり贅沢な気分になれる。 この本は、雑誌に発表されたものがまとめられているのだが、全体を通して印象的なのは“翻訳”というテーマである。 フランスの詩人プレヴェールの詩「朝の食事」の五人の訳者による訳詩が一度に読めるのが圧巻。 内藤濯(あろう)、小笠原豊樹、平田文也、北川冬彦、大岡信。 それぞれの訳を全部引きたいぐらいだが、そんなことをしていたら終わらないのでやめておこう(笑) 五者五様、これほどまでに雰囲気の違うものなのかと感心する。 「今これをお読みのあなたなら、どの訳を選びますか。」 と北村さん。 北村さんご本人は、自身が一番最初に接した内藤訳がやっぱり好きなのだそうだ。 私は北川訳が好きだな。 読んだときのリズムがいいし、強い感じ、毅然とした感じがするのがいい。 (これは北村さんと逆のようで面白い) さて、もう一つ楽しかったのが、“和歌の翻訳”である。 ここで言う翻訳とは、意味を知るための“解説”ではなく、あくまでも“訳す”ことを指す。 今回北村さんは、佐佐木幸綱と橋本治の百人一首の翻訳を紹介している。 佐佐木幸綱は、訳者が思うところのポイントをデフォルメして、単なる内容の移しかえとは違う、それ自体一つの作品となり得るような訳をしているところがすごい。 それは形式にとらわれることなく、のびのびと詠われる。 佐佐木幸綱編「百人一首をおぼえよう」(さ・え・ら書房) という若い読者向けの本の中からいくつか紹介されている。 すごく個性的で面白い。 百人一首にはあんまり興味はないが、この本はちょっと欲しいかも。 さて一方、橋本治の桃尻語訳は、なぜか頑なに五七五七七にこだわる。 しかも、できる限り一句目は一句目として訳すという。 北村さんいわく、「難敵に挑む荒武者のよう」なのである。 例えば、小野小町の 「花の色は うつりにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせしまに」 が、 「花の色は 変わっちゃったわ だらだらと ひとりでぼんやり してるあいだに」 と訳されている。 変わっちゃったわだらだらと、というのがいいですねー。 天智天皇の 「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は つゆにぬれつつ」 は、 「秋の田の 刈り入れ小屋は ぼろぼろで わたしの袖は 濡れっぱなしさ」 となる。 分かりやすー。 おまけにもういっちょ。 これは本書には引かれていないが、喜撰法師の 「わが庵は 都のたつみ しかぞ住む 世をうぢ山と 人はいふなり」 は、こうなります。 「俺の家 都の東南 住んでます 名前はしかし ウジ山だってさ」 「わが庵」が「俺の家」… 確かに…(笑) しかも、「だってさ」って(笑) この本には翻訳の他にも、藤原実方と藤原行成の仲の悪さとが、夏目漱石にまつわるエピソードに対する堀口大学の思い込み、ドイツの女流詩人ドロステの海賊の詩についても詳しく書かれている。 上田秋成のホラーな詩の、描かれざる部分の怖さ、というのもすごかったし、天野慶の痛々しい作品たち、木村信子の「ひつじ」なども忘れ難い詩である。 北村さんは、世の中で一番多く行われている“翻訳”は、“読む”ことだという。 「AであれBであれ、読者の頭に浮かぶのは、実は合同のAやBではありません。読者それぞれによって変形されたCなのです。」 読書って翻訳なんですね。 ということは、この詩歌シリーズは、北村薫という名翻訳家による素晴らしい翻訳集ということになるではないか。 やっぱり贅沢だ!
Posted by 
待ち伏せに気付くためには、その下地となる知識が必要だよなあとしみじみ思い知らされます。 詩歌の楽しみ、その広がりを教えてくれます。それは詩歌に限らない世界との付き合い方かも知れません。
Posted by 



