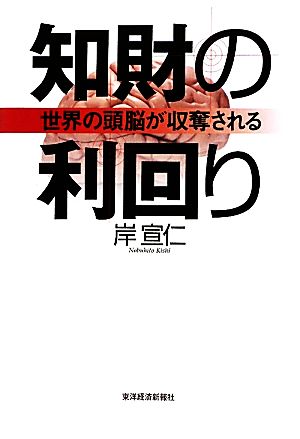
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-05
知財の利回り 世界の頭脳が収奪される
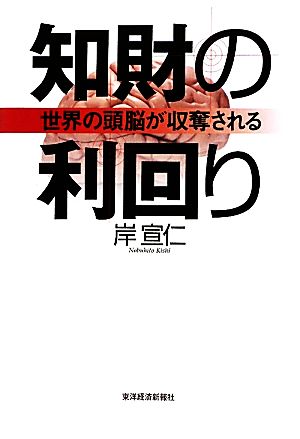
定価 ¥1,870
220円 定価より1,650円(88%)おトク
獲得ポイント2P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 2009/12/10 |
| JAN | 9784492761830 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
知財の利回り
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
知財の利回り
¥220
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.6
8件のお客様レビュー
知的財産を証券として扱うファンド、延いては市場が、イノベーションに如何なる影響を持ちうるかを、取材に基づき論じた本。 知的財産権が、ライセンス料というキャッシュフローを生み出す以上、これを証券と同様に扱う見方が生まれるのは必然であり、唯一の障害は、十分な流動性が担保される市場が...
知的財産を証券として扱うファンド、延いては市場が、イノベーションに如何なる影響を持ちうるかを、取材に基づき論じた本。 知的財産権が、ライセンス料というキャッシュフローを生み出す以上、これを証券と同様に扱う見方が生まれるのは必然であり、唯一の障害は、十分な流動性が担保される市場が存在しないことであった。本書の主な取材対象であるインテレクチュアル・ベンチャーズ(以下IV)は、そのような市場の到来を見越しつつ、知財でポートフォリオを組むファンドである。本書の記述が事実であるならば、1号ファンドは2009年時点で投下資本1千億円で年あたりライセンス料が1千億円あり、今後5千億円程度になる可能性があるという。その場合、投下資本に対する年利回りは100%前後となり、リスクが限定的であるとすれば驚異的な成績であるから、新規参入が相次ぐことが予想され、知財市場の創設は時間の問題となる。 本書における論点は、このような市場やファンドが多く創設された場合、イノベーションに寄与するか否か、である。IVは、知財が証券として整備され、流動性が高まれば、イノベーションへのインセンティブが高められるから、イノベーションは加速すると論じる。一方で、キャノン顧問の丸島氏などは、イノベーションとは、特許に含まれるアイディアだけで発生するのではなく、製品の製造や流通、ビジネスモデルまでが一貫性を以って実施されて初めて生まれるものであるため、知財を売るために「アイディアが記載された書類」が量産されることはあっても、イノベーションが促進されることはないと見る。むしろ、知財は独占権を以って他者の事業運営を妨害するものであるから、事業を運営していない組織がこれを持つことは、イノベーションを遅延させる効果しか持たない、とさえ言えるだろう。 本書の発行から4年以上過ぎた現在、IVを取り巻く現状を見る限り、丸島氏を始めとする懐疑派に分があるようである。2011年には複数の企業を相手に訴訟を起こし、米国の新聞や週刊誌からはパテント・トロールと詰られ、発明を促すことも、発明者に報いることもしていないと非難され、リターンもIRR2.5%程度であり著しくないとされている。ついには、資金ショートを起こしており、従業員を5%レイオフするという報道まで出た。IVが主張するインテレクチュアル・キャピタルの時代は、まだ来そうにない。 本書の発行から4年後の現在においても未だ不透明性が漂う領域に、丁寧な取材と著者独自の観点に基づく考察というメスを入れた好著。☆4つ。
Posted by 
発明〜特許取得〜ライセンスビジネス という知の集積を図る新しいビジネスモデルで出資を募るIV社の評価。 著者の危機感は過剰とも思えるが、それほどのインパクトを感じさせられるもの。
Posted by 
インテレクチュアル・ベンチャーズ(Intellectual Ventures)について書かれた本。興味があって読みました。 仕組みや活動、歴史は分かったものの、将来についてはやはり未知数と言った印象。 日本はオープンイノベーションに対応できるのだろうかと不安になる。。。 もう2年...
インテレクチュアル・ベンチャーズ(Intellectual Ventures)について書かれた本。興味があって読みました。 仕組みや活動、歴史は分かったものの、将来についてはやはり未知数と言った印象。 日本はオープンイノベーションに対応できるのだろうかと不安になる。。。 もう2年くらい前の内容で少々古くなっています。(2年で古くなるのも驚きですが…)
Posted by 


