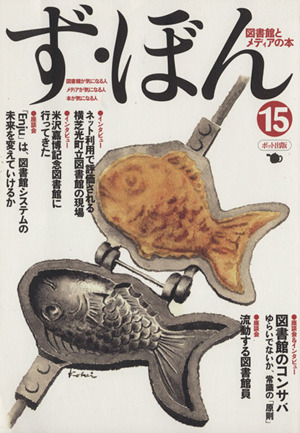
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-01-00
ず・ぼん(15) 図書館とメディアの本
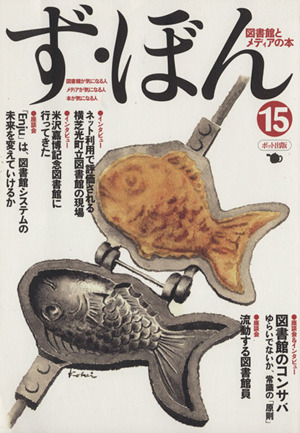
定価 ¥2,200
220円 定価より1,980円(90%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | スタジオ・ポット |
| 発売年月日 | 2009/11/21 |
| JAN | 9784780801378 |
- 書籍
- 書籍
ず・ぼん(15)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ず・ぼん(15)
¥220
在庫なし
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
『ず・ぼん』という雑誌(のように見えるが、ISBNがついているから本扱い?)は、これまで全部とは言わないが、ほとんど読んでいる。「図書館とメディアの本」で、「図書館が気になる人、メディアが気になる人、本が気になる人」と表紙にある。どれも気になる。 あるとき気が付いたら、発行して...
『ず・ぼん』という雑誌(のように見えるが、ISBNがついているから本扱い?)は、これまで全部とは言わないが、ほとんど読んでいる。「図書館とメディアの本」で、「図書館が気になる人、メディアが気になる人、本が気になる人」と表紙にある。どれも気になる。 あるとき気が付いたら、発行しているポット出版のサイトで、バックナンバーのかなりの部分が読めるようになっていた。 →ず・ぼん全文記事(書き手の了解があるもののみ) http://www.pot.co.jp/zu-bon/ この『ず・ぼん15』は冊子体と電子書籍版で販売しているらしい。私は図書館で借りてきたので冊子体。手は編み物をしながら読んでいると、手もなかなか止められず、読むのもなかなか止められず、3日ほどでほぼ全部読んでしまった。 どの記事もおもしろかったが、とくに私がぐいぐい読んだのは、「「Enju」は、図書館システムの未来を変えていけるか」という座談会と、「ゆらいでないか、常識の「原則」─もう一度問い直す、図書館の原則」という座談会。 「Enju」は、オープンタイプの図書館管理システムで、その開発メンバーが、開発過程のことやその可能性、現行の図書館管理システムのことをいろいろと話していて、あー、こういうところに図書館員もそうやけど、本や図書館に関心があり、今のシステムもうちょっとどないかならんのかと思ってる人が関わると、変わっていくかもしれんと思えた。 私がふだん使っている市立図書館も、私が昨春まで勤めていた別の図書室も、管理システムは○○通とか○○Cといった大手の業者のご立派なやつが入っている。目録カードでやってます、というようなところでなければ、たいがいの自治体は似たり寄ったりのシステムを入れてるはずである(たまに、ヨソの自治体の図書館の蔵書検索をすると、そっくりデザインのところがいくつもある)。 勤めていた図書室では、どうも検索がおかしいとか、資料を当たるのに使いづらいというところが色々あったのだが、それを「さわってもらう」には、いちいち業者をよんで、お金がかかるとかかからんとか(お金がかかることは、まず実現しない)、とにかく、いいとは思えないが、これを使うしかない、という状態だった。 利用者として使っている市立図書館は昨年「システム入れ替え」があった。私はほぼ毎日図書館のサイトを使うので、多少使い勝手が悪くても慣れていく、というのはあるが、今でも、なんだか表示がおかしかったり、検索結果が怪しかったりはときどきある。このシステム入れ替えで、図書館で働く人たちの仕事がよりスムーズになったのかどうか、図書館を使う市民にとってよくなったのかどうか、正直ビミョーな気がする。 そういう実感もあるので、この「Enju」の話は、いいんちゃうか?と思えた。こういうのに興味ある人が市立図書館の職員にいるといいけどなーと思った。費用が安いのもあるが(たぶん今システムを入れてる業者の値段と1桁か2桁違ってくるだろうという話、逆に大手のシステムにこれだけの金が必要なのか?ともいえる)、図書館員が自分の手でデザインできる、カスタマイズが簡単にできる、というところに魅力を感じる。 図書館の常識の話は、「読書履歴の秘密を守る」「リクエスト批判」「図書館の無料の原則」「公共性」をキーワード員した座談会。それと同じテーマで図書館協会の人のインタビューも入っている。 無料の原則のところを読んでいて、「路上文庫」をやっている木村道子さんの話を思い出す。(木村さんの話は、松本哉ほかの『さよなら下流社会』に入っている→『We』 158号で紹介した) 「路上文庫」の話を読んだときに、ああそうやな、誰でも公平に情報にアクセスできる、というのが図書館のキモやな、大事やなとつくづく思った。だから図書館はタダなのである。 公共性の話は、これは『私のだいじな場所』(http://www.hands-on-s.org/blog/2005/11/daiji.html)と同じやなー、「公共施設の市民運営を考える」というあの本のココロに通じるところやと思いながら読んだ。 この号は、ネット利用の話も随所に出てきて、横芝光町町立図書館の坂本成生さんのインタビュー(この人は百貨店勤めのあとに図書館員になったという流動派で、そこもおもしろかった)や、ポット出版の沢辺さんの「ジャパニーズ・ブックダムの夢」の話には、ツイッターを使ってこんなことをしているという話もあって、図書館や本はこれからどうなっていくんやろうなーと思いながら読んだ。それはべつに(どうなるんやろ…)と悲観するわけではなくて、なにかおもしろそうなワクワク感があったのだった。 沢辺さんのツイッター http://twitter.com/sawabekin
Posted by 
2009 12/13 読。 横芝光町立図書館、米沢嘉博記念図書館、Project Next-Lの記事を読んだ。 ・・・おお、どの記事も一部は密かに、一部はおおっぴらに図書館系ブロガーの関連しているものばかりだ。 影響力大きいなbiblioblogger。 みんなブログやってるだけ...
2009 12/13 読。 横芝光町立図書館、米沢嘉博記念図書館、Project Next-Lの記事を読んだ。 ・・・おお、どの記事も一部は密かに、一部はおおっぴらに図書館系ブロガーの関連しているものばかりだ。 影響力大きいなbiblioblogger。 みんなブログやってるだけって言えばそれまででもあるが。
Posted by 

