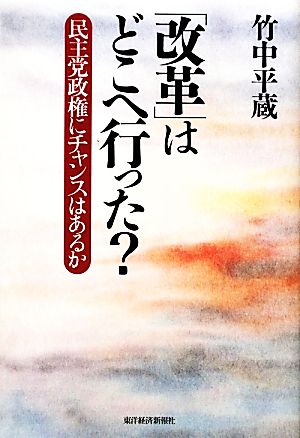
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-00
「改革」はどこへ行った? 民主党政権にチャンスはあるか
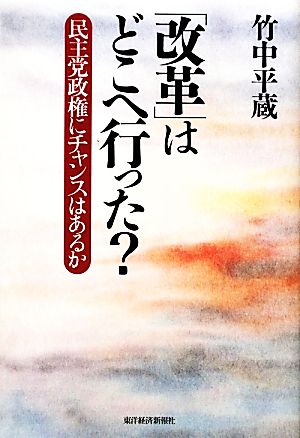
定価 ¥1,650
110円 定価より1,540円(93%)おトク
獲得ポイント1P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 2009/11/26 |
| JAN | 9784492395202 |
- 書籍
- 書籍
「改革」はどこへ行った?
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
「改革」はどこへ行った?
¥110
在庫なし
商品レビュー
4.1
9件のお客様レビュー
Policy to help と Policy to solve を学んだ。著者の論旨はいつも明快ですっきりする。この人にだったら政治を任せてもいいと思える。
Posted by 
【ソーシャルライブラリーから引っ越し中】 ここ半年ぐらい読んだ本の中で一番読み応えがあった。 竹中氏はとても正論を述べていると思う。その正論については好き嫌いはあるだろうが。個人的にはわりと好きである。 経済の専門家であり、国会議員として大臣をつとめただけあって多面的視野でものご...
【ソーシャルライブラリーから引っ越し中】 ここ半年ぐらい読んだ本の中で一番読み応えがあった。 竹中氏はとても正論を述べていると思う。その正論については好き嫌いはあるだろうが。個人的にはわりと好きである。 経済の専門家であり、国会議員として大臣をつとめただけあって多面的視野でものごとを語っていると思う。大きな政府の背景説明、政治的空間など、自分が気になっていたことについての指摘もたくさんあった。 竹中氏は、いま困っている人たちに対して反感を持たれてもhelpよりsolveが大事との立場である。それは正論。でも、国民が政治家にそれを求めているかというと?きっとsolveよりhelpがいいのであろう。国民がsolveを求め、政治の世界に正論が通じるようになる日が来ると信じたい。
Posted by 
小泉政権下で郵政民営化担当大臣をしたこともある竹中氏による著作で、特に麻生政権あたりから始まった規制緩和を元に戻すような動きに対して警鐘を鳴らしています。 規制緩和のやり過ぎで格差が広がったのか否かの議論では、どちらが正解なのか私は分かりませんが、竹中氏は規制緩和の程度が中途...
小泉政権下で郵政民営化担当大臣をしたこともある竹中氏による著作で、特に麻生政権あたりから始まった規制緩和を元に戻すような動きに対して警鐘を鳴らしています。 規制緩和のやり過ぎで格差が広がったのか否かの議論では、どちらが正解なのか私は分かりませんが、竹中氏は規制緩和の程度が中途半端のために現在の状態になってしまったという意見を持っているようです。 規制に守れて幸運な生活をしている人は多くいると思いますが、将来にわたって多くの人が幸福になれるような政策をとって欲しいと思いました。 以下は気になったポイントです。 ・小泉政権の5年5ヶ月で実現できた大きな改革は、公共事業削減、不良債権処理と郵政民営化、道路公団民営化に限られている、労働市場改革や医療問題は未解決(p9) ・今年のアメリカの成長率はマイナス2.8~3%、1932年はマイナス13%、失業率も9.4%に対して25%であり、「100年に一度の危機」ではない(p19) ・ユーロ及びポンドは実際の実力よりも過大評価されてしまい、購買力が高まった結果、多くの消費をしてしまった(p21) ・製造業の時価総額ランキングにおいて、日本企業はベスト100に8社のみ、アメリカ:44、イギリス:11と比較してモノづくりでも優位性は無い(p25) ・株主は、役員がよくやっているかを事後的にチェックして、株主総会で評価を示すもので、日々の経営判断に口を出すべきではない(p30) ・かんぽの宿において、2000億円投じたものを100億円で売ることを議論しているが、100億円の価値しか無いものに2000億円かけてしまったことを問題にすべき(p34) ・民営化のやり方に、1)特殊会社化(民間会社であるが特別な公的な目的をもっている、根拠法、資本金保有などあり)、2)民間法人(政府出資なし、根拠法あり)、3)完全民営化、の3種類がある(p41) ・政策投資銀行と商工中金は完全民営化すること決めたが、現在は特殊会社であり、役所が管轄である(p42) ・政府の歳入の主なものは税金と国債、2008年度において歳入83兆円のうち、国債発行による収入は30%を占める(p51) ・地方交付税を切り捨てたので地方経済が悪くなったというのは誤り、基準財政需要額(減らしていない)と基準財政収入額の差額が地方交付税、交付税が減ったのは地方税が増えたから(p66) ・派遣は雇用者全体の2.6%を占めるのみ、5%台という失業問題は正規雇用者が守られすぎていることで非正規労働者が増えたことにある(p70) ・派遣の仕組みをなくすと、正規雇用が増えるのではなくて、昔の請負が増えるのみ、請負のほうが使用者責任が及ばない(p73) ・日本では競争による格差ではなく、制度の歪による格差が真の問題である(p75) ・政策論において民間には知恵は殆どない、不良債権処理、郵政民営化をやるときに知恵は出てこなかった(p89) ・小泉改革では、予算の前に政策をつくって(6月の経済諮問会議による骨太の方針)から予算をつけるようにした、官僚が起案した政策以外も議論できるようになった(p110) ・日本の真産業創出の予算はGDP比でアメリカの2倍なのに成果がでない、その理由はアメリカでは減税があるので(p113) ・日本の銀行が悪くなった理由として、1)銀行の株式保有、2)貸出金利の上限金利規制、3)リスク管理(企業や事業に対する目利き)ができていない、がある(p131) ・アジア通貨危機が起きたときに日本は巻き込まれなかった理由として、1)国内に大きなプラスの貯蓄あり、2)輸出産業による黒字の経常収支、である(p149) ・日本が強い経済を目指すための政策として、1)法人税減税、2)ハブ空港、3)東京大学民営化、4)農地法の改正、5)インフレ目標の導入、である(p161) ・納税者番号でプライバシーが侵害されるとしたら、戸籍を先になくすべき、戸籍という制度をもっているのは数カ国程度、戸籍に記載されている内容はまさにプライバシー情報(p164) ・民主党は野党時代から、予算の総額そのものを変える自らの案を提案することを放棄してきた(p188) ・1993年に自民党が下野したときは衆参両院において比較第一党で あり、また野党として選挙を戦っていないので今までと異なる(p196)
Posted by 



