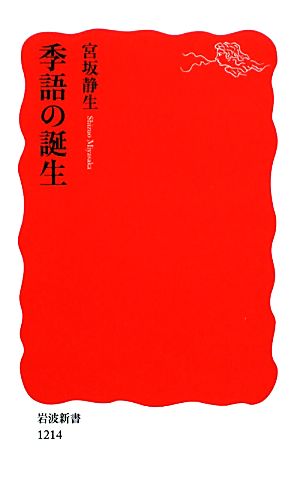
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-36-01
季語の誕生 岩波新書
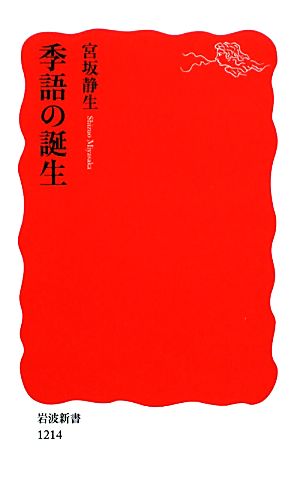
定価 ¥770
220円 定価より550円(71%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2009/10/20 |
| JAN | 9784004312147 |
- 書籍
- 新書
季語の誕生
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
季語の誕生
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.7
4件のお客様レビュー
俳人の宮坂静生による季語の考察。季語とは、日本人が古代から蓄積してきた共通の美意識が言葉となって凝縮されたものだという。いわば凝り固まった意識を解きほぐし、新たな光を当てたのが、芭蕉の功績だとする。さらに、季語の中でも重要な雪・花・月について進められる検討は、新しい発見があり、ス...
俳人の宮坂静生による季語の考察。季語とは、日本人が古代から蓄積してきた共通の美意識が言葉となって凝縮されたものだという。いわば凝り固まった意識を解きほぐし、新たな光を当てたのが、芭蕉の功績だとする。さらに、季語の中でも重要な雪・花・月について進められる検討は、新しい発見があり、スリリングだった。
Posted by 
[ 内容 ] 季語はどのようにして生まれたのか。 従来は、花・月・雪などの題目が揃った平安時代の美意識に起源をもつといわれてきた。 しかし、季語誕生の底流には、縄文人以来長い間に蓄積された生活意識が民俗的伝承としてあったのではないか。 芭蕉を季語の歴史を変革した先駆者と位置づけな...
[ 内容 ] 季語はどのようにして生まれたのか。 従来は、花・月・雪などの題目が揃った平安時代の美意識に起源をもつといわれてきた。 しかし、季語誕生の底流には、縄文人以来長い間に蓄積された生活意識が民俗的伝承としてあったのではないか。 芭蕉を季語の歴史を変革した先駆者と位置づけながら提言する新たな季語論。 [ 目次 ] 1 季語の歴史―どう考えられてきたか(季語はどのように生まれたか―和歌の時代;季語の本意の成立―連歌の時代;季語の本意の見直し―俳諧の時代) 2 季語の世界(雪・月・花という季語はどのように生まれたか;雪;花;月) 3 季語再考―縄文人の生活意識から探る(いのちを感ずる;季語の見直しにむけて;季感の定着まで;はるかな縄文人の声) 付録 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by 
季語はどのようにして定型化してきたので、あろうか。地域によって季語と季節に乖離のあることもあるが、どのように受け止めると良いのであろうか。答えを用意している意欲的な提案。 季語の起源を縄文の生活意識からさぐり、平安時代の歌語が起源になって誕生したとする説(207p)を深化さ...
季語はどのようにして定型化してきたので、あろうか。地域によって季語と季節に乖離のあることもあるが、どのように受け止めると良いのであろうか。答えを用意している意欲的な提案。 季語の起源を縄文の生活意識からさぐり、平安時代の歌語が起源になって誕生したとする説(207p)を深化させる。他方で、「季語の地貌化という視点」(同)を掲げる。季語「平安貴族によって山城盆地を中心とする近畿文化圏の風土の中なかで誕生し、育まれたもの」が、江戸時代に芭蕉の旅の体験を通じて「確立した不易流行の造化感は季語のもつ拘束を自在にした」とも、読む。 季語の中核に、花月雪があり、これに鶯と紅葉が加わる。季語は北緯30度ー40度地帯にあてはまり、遠く縄文の意識に拘泥される。読んでいて、わかりやすい。
Posted by 



