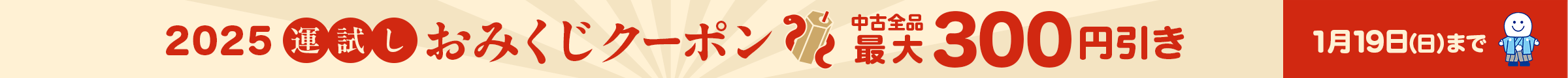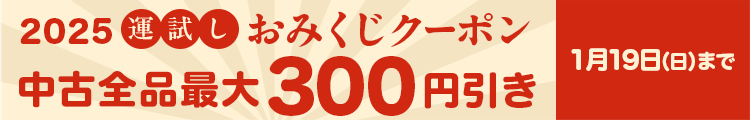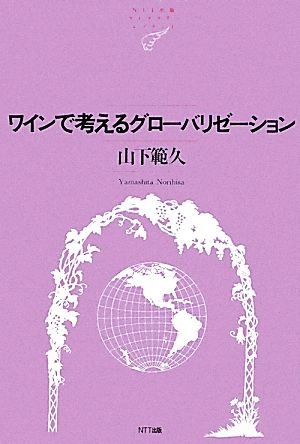
- 中古
- 書籍
- 書籍
ワインで考えるグローバリゼーション NTT出版ライブラリーレゾナント
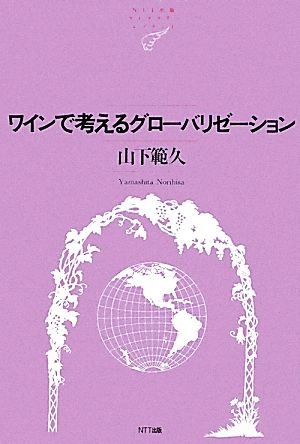
定価 ¥1,870
220円 定価より1,650円(88%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | NTT出版 |
| 発売年月日 | 2009/10/29 |
| JAN | 9784757142275 |
- 書籍
- 書籍
ワインで考えるグローバリゼーション
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ワインで考えるグローバリゼーション
¥220
在庫なし
商品レビュー
4
3件のお客様レビュー
久し振りに新刊で購入した本。といっても、発行はすでに4年前ですが、外出先で読んでいた論文コピーを読み終えてしまい、急遽書店で購入。でも、今回はこの本を買うと決めていました。というのも、購入したのが有楽町の三省堂だったのだが、本書を刊行語まもなく見つけたのがこの書店だったので、思い...
久し振りに新刊で購入した本。といっても、発行はすでに4年前ですが、外出先で読んでいた論文コピーを読み終えてしまい、急遽書店で購入。でも、今回はこの本を買うと決めていました。というのも、購入したのが有楽町の三省堂だったのだが、本書を刊行語まもなく見つけたのがこの書店だったので、思い出して本書を探した。その頃からレイアウトが変更されてしまったが、NTT出版の「ライブラリー レゾナント」というシリーズの1冊だったので、比較的容易に見つかった。 著者である山下範久さんの本は『現代帝国論』(NHKブックス)以来2冊目。その読書日記にも書いたが、私より1つ年下の彼とは一応面識がある(あちらは忘れていると思うが)。あれはおそらくまだ20世紀だったと思うが、彼が世話人をしていた東大の研究会に何度かお邪魔していたのだ。一度は報告もさせてもらって、その打ち合わせと称し、調布駅からちょっと離れた小さな喫茶店で一緒の時間を過ごしたこともある。身なりにも気を遣うような男性だったので、彼がワイン通であると知っても驚くことはなかった。でも、その趣味を活かして1冊の本を書き上げるとはさすがだ。まずは目次から。 開講にあたって 第一部 ワインのグローバル・ヒストリー 第一講 モノから見る歴史 第二講 旧世界と新世界 第三講 ワインにとってのヨーロッパ 第四講 ワインにとって近代とは何か 第五講 ワインの「長い20世紀」 第二部 ワインとグローバリゼーション 第六講 フォーディズムとポスト・フォーディズム 第七講 ワインとメディア――ロバート・パーカーの功罪 第八講 テロワールの構築主義 第九講 「テロワール」をひらく 第三部 ポスト・ワイン 第十講 ワインのマクドナルド化? 第十一講 ローカリティへの疑問 第十二講 ツーリズムとしてのワイン 第十三講 ワインの希望 本書の構成は講義録の様になっている。大学の半期の講義は15回程度なので、初回のイントロダクションも含めて14章に分かれているのはそのせいである。でも、書き振りは大学の講義というより一般市民講座。あとがきを読むと、確かに本書の内容は大学の講義やさまざまな市民を相手にした講演が基になっているようだが、本書自体は書き下ろしだそうだ。 ですます調で書かれ、社会科学者ならよく知っている学説についても丁寧に、そして端的に解説される。本書はワインという素材を親しみのあるとっかかりとして、グローバル化という難しい問題を考えるという趣旨で書かれているが、本書を通じてさまざまな新しい社会学理論のエッセンスを学ぶことができるようになっている。古いところではギデンズの近代論、アーリの観光論、新しいところではハーヴェイのポストモダン論、ラトゥールのアクター・ネットワーク理論、リッツァのマクドナルド化論など。目次にある「長い20世紀」ってのはアリギの著書のタイトルだし、「構築主義」はもちろん社会構築主義のこと。当然ウォーラーステインの弟子である著者だから、世界システム論についてはわざわざ語ることもなく、ネグり・ハートの『〈帝国〉論』やブローデル『地中海』なども思考の基礎にある。 私はそうした社会学理論も選り好みをしてしまい、リッツァの本なんて読もうとも思わない。その一方で気に入ったものがあれば、それに批判的に向き合えなくなってしまったりするが、山下さんの場合は前著を読んだ時も感じたことだが、そういうものに選り好みせずに向き合い、消化して自分なりの言葉で語ることができる。どんな理論でも長所と短所を見極めたうえで、短所はさらっと批判し、より長所を引き出す感じの書き方です。 さて、本書の内容ですが、もともとワイン好きということで、学生用の講義の素材に使ったりしていたようですが、本書執筆のためにさらに勉強を重ね、ソムリエの資格も取り、というところは本当に頭の下がる徹底ぶり。そして、本書を読む限り、グローバル化を考える上でワインという素材がまたマッチしています。それは単なる人間の営為ということだけではなく、人間が自然と向き合ってきたという歴史、そして土地に固定された自然環境というものが地域の特質を生む、という考えが生じ、変化し、利用されるということがよく理解できます。それが故に、ワインというモノが移動し、人々が移動し、観念が移動するというグローバル化の原動力となるという論理。それは、グローバル化によって世界が均質化するのではなく、より場所の個性というものが要求されるという、ハーヴェイのポストモダン論を例証しています。ともかく、いろんな意味でよく書けている本でした。
Posted by 
・再帰性の高まりとポストフォーディズムによってワインの生産・消費のスタイルが大きく転換。リロケーションによる低価格化と高品質化の二極化が起こるかに見えたが、パーカリゼーションによってそれも変わる。 ・グローリズム(=メディアによる消費の記号化)とテロワールという巷でさけばれてる...
・再帰性の高まりとポストフォーディズムによってワインの生産・消費のスタイルが大きく転換。リロケーションによる低価格化と高品質化の二極化が起こるかに見えたが、パーカリゼーションによってそれも変わる。 ・グローリズム(=メディアによる消費の記号化)とテロワールという巷でさけばれてる対立図式を脱構築しなけれなばならない。なぜなら、イデオロギーとしてのテロワールは、「文化」と「自己」に閉じてしまっているからである。それを考える上で有効なのがリッツァのマトリックス。 ・無⇔存在、グロースバル化⇔グローカル化 再帰性=自己を対象化すること 差異志向と本物志向→相互承認=価値の共有
Posted by 
[ 内容 ] 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート資格をもつ歴史社会学者によるグローバリゼーション入門講義。 [ 目次 ] 第1部 ワインのグローバル・ヒストリー(モノから見る歴史;旧世界と新世界;ワインにとってのヨーロッパ ほか) 第2部 ワインとグローバリゼーション(フォ...
[ 内容 ] 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート資格をもつ歴史社会学者によるグローバリゼーション入門講義。 [ 目次 ] 第1部 ワインのグローバル・ヒストリー(モノから見る歴史;旧世界と新世界;ワインにとってのヨーロッパ ほか) 第2部 ワインとグローバリゼーション(フォーディズムとポスト・フォーディズム;ワインとメディア―ロバート・パーカーの功罪;テロワールの構築主義 ほか) 第3部 ポスト・ワイン(ワインのマクドナルド化?;ローカリティへの疑問;ツーリズムとしてのワイン ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by