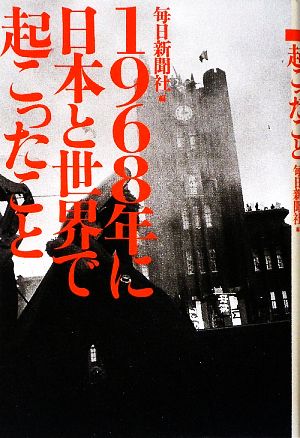
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-12
1968年に日本と世界で起こったこと
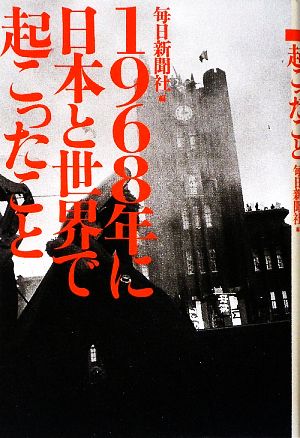
定価 ¥2,640
1,430円 定価より1,210円(45%)おトク
獲得ポイント13P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 毎日新聞社 |
| 発売年月日 | 2009/06/30 |
| JAN | 9784620319339 |
- 書籍
- 書籍
1968年に日本と世界で起こったこと
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
1968年に日本と世界で起こったこと
¥1,430
在庫なし
商品レビュー
2.5
2件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
全共闘、安保闘争、べ平連、このあたりの単語にようやくアレルギーがなくなってきて、この時期と現在の共通点・違いなどが分かるようになってきた。 ただ、どうしても経済を勉強している関係上、「なぜ日本では68年運動が諸外国と違い継続しなかったのか」みたいな疑問には「経済が順調やったからやろ」と考えてしまう。 オイルショックの影響が先進国で数字上は最も少なく、アメリカと貿易摩擦が発生するまでに自動車が作られて。 また自動車ってとこがミソで、波及がでかかった。こんな時に運動なんかしてるのは生粋の人なわけで、けど当時の参加者の大半は「空気」的に参加してた人も多かった。 と、なると継続されない。 にしても、この運動ってのがこんなにロジックが必要とされてたのか思った。考えすぎちゃうか?とも思うけど。 そこは意外。
Posted by 
面白いし、時代の主人公のインタビューを中心に構成されているのはさすが新聞。 その半面で、やや深みに欠ける。 歴史を重層的に取られるということなのでそれでいいのかもしれないけど、なんだかすごい食材で安っぽい料理を作ったみたいな感じ。 この時代を扱ったものとしては標準的な出来...
面白いし、時代の主人公のインタビューを中心に構成されているのはさすが新聞。 その半面で、やや深みに欠ける。 歴史を重層的に取られるということなのでそれでいいのかもしれないけど、なんだかすごい食材で安っぽい料理を作ったみたいな感じ。 この時代を扱ったものとしては標準的な出来だし、どこかで読んだような内容が続くのだけど・・・ その反面、こんな叙述方法でいいのだろうかと思う。 現場を取材し、それをコメンテータが解説する。最後に出てくるのはやっぱり構造主義だったり脱構築だったり、現在への視点だったり。 1960年代は現実問題としてまだ歴史になりきっていないのだから仕方がないのかもしれないけど、歴史に向かい合う峻厳さに欠ける気がするのだ。 この、歴史の峻厳さというものについてもうちょっと書く。 ちょっと嫌味な見方かもしれないけど、学者とかジャーナリスト(マスコミの上のほうまで出世)とか現在でもネームバリューを持つ評論家とか、結局この時代の生き残りレースの最終走者というか、出世した人によって書かれたものという感じがする。この本だけじゃなくて、1960年代を書いたものはどれもそうだ。 その意味で、当時および現在の政治的スタンスがどこにあろうと、けっきょく勝者の視点なのであり、「正史」なのである。 これは、この時代が名実ともに「歴史」になって、「歴史学」的な手法によって洗われたときに、一斉に瓦解するように思う。 たとえば、べ平連の米兵脱走運動。それは確かに、運動の方法としては斬新だと思うし、現実的だと思う。また巻末の座談会でゲマインシャフト(家族)の参加という視点からも分析されていて、なるほど、とは思う。 しかし、そうして脱走した米兵は、その後どうなったのだろうか。 どの国に脱走した? おそらくいまだに米国には帰れないと思うが、それを当の本人たちはどう思っているのだろう。自分たちがプロパガンダに使われたと思っているのだろうか。それともいまだに感謝しているのだろうか。 鶴見俊輔氏や小田実氏は、彼らのその後のことを思ったことがあるのだろうか? 当時から死ぬまで彼らは莫大なテキストを残したわけだが、そんなこと書いているのだろうか。書いていたとしても、なにかの行動を起こしたのだろうか。 そしてそれは、後世の人間に分析される。されないわけにはいかないだろうな。 今我々が100年前の日露戦争直後の政党政治家に対して、容赦なく分析していくみたいに、いずれこの本に載っている人たちによる、あえてこの言葉を使うが、「勝ち組」によって記述された文章は、いずれ厳しくさらされ、いろいろな角度から見られるだろう。 浅間山荘事件を警察側で指揮した佐々淳行氏はこれで飯を食っているようなものだけど、最終的に右も左もみんなひっくるめてこのカテゴリに入れられそうに思う。 このとき、後世の人々によって評価されるのは、案外、日大全共闘議長の秋田明大氏かもしれない。私の目から見て、この人が一番、自分のしたことを「総括」していると思う。
Posted by 



