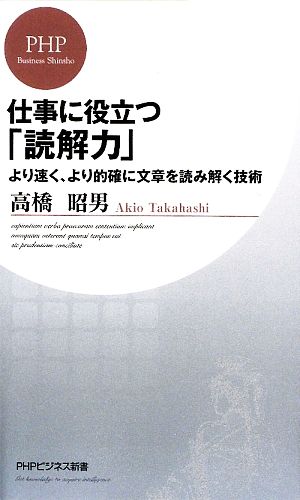
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-18-13
仕事に役立つ「読解力」 より速く、より的確に文章を読み解く技術 PHPビジネス新書
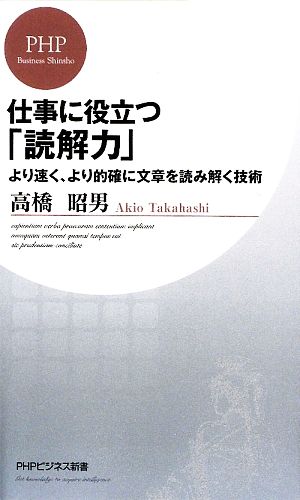
定価 ¥858
220円 定価より638円(74%)おトク
獲得ポイント2P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/7(水)~1/12(月)
店舗到着予定:1/7(水)~1/12(月)
店舗受取目安:1/7(水)~1/12(月)
店舗到着予定
1/7(水)~1/12

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/7(水)~1/12(月)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | PHP研究所 |
| 発売年月日 | 2009/06/01 |
| JAN | 9784569707617 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
1/7(水)~1/12(月)
- 書籍
- 新書
仕事に役立つ「読解力」
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
仕事に役立つ「読解力」
¥220
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3
3件のお客様レビュー
主語のあとには「は」を使うべしとだけ認識していて、「が」には多くの用法があって混乱を招くので今までは使用することを控えていました。この本によって両者の違い(「が」は「こそ」と同様、強調するときに使うもの)が分かってこの本を読んだ収穫があったと思いました。また各接続詞についての解説...
主語のあとには「は」を使うべしとだけ認識していて、「が」には多くの用法があって混乱を招くので今までは使用することを控えていました。この本によって両者の違い(「が」は「こそ」と同様、強調するときに使うもの)が分かってこの本を読んだ収穫があったと思いました。また各接続詞についての解説があり、これも私にとっては参考になりました。 以下はためになったポイントです。 ・助詞「が」は、事柄に対する疑問を表現したいときに使う、後の内容のほうを重視する(p21) ・世の中の詐欺は、事実と意見の境界にグレーゾーンを設けて、読み手を誘いこむのが常套手段、文を読むときには事実と意見(書き手の希望的観測)を明確に分離する習慣をつける必要あり(p26) ・「~は」は、主語ではなく、主題と考えるべき(p43) ・「が」は、排他強調したいとき使う助詞である(p49) ・文章の道しるべとしての接続詞として、1)具体例を教える(従って、そこで、その結果等)、2)反対意見や限定(しかし、逆に、一方等)、3)理由や説明(なぜなら、つまり等)、4)強調(とくに、大事なことは等)、5)情報の追加(および、しかも、さらに等)、6)仮定、7)類似、8)例示、9)言い換え(つまり、すなわち)、10)転(ところで、つまり、さて、では)がある(p78) ・三段論法の内容が適切であるかを検証するには、1)大前提の主部のキーワード=小前提の述部のキーワード、2)小前提の主部のキーワード=結論の主部のキーワード、3)大前提の述部のキーワード=結論の述部のキーワード、を確認すること(p87) ・序破急とは、「転」の情報を、「破」と「急」に入れ込んだと解釈するのが適当(p89) ・ポリフェノールが心筋梗塞に効果があるという結論を出すまでに取ったことは、フランスと同様に心筋梗塞による死亡率が少ない国はどこかを検証したことであった(p152)
Posted by 
読解力を飛躍的に向上させる方法など盛りだくさん。 三段論法のチェック法は役立つな。 なるほどなるほどなるほどなぁぁぁぁぁ!!
Posted by 
【内容】 著者は、テクニカルライター ドキュメントを読んで理解するための入門書。の位置付けだそうです。 【話の展開】 ドキュメントを読みとくための話題が、5~6ページぐらいずつかいてあります。 【コメント】 自分の部屋で積ん読になっていたものを発掘。 これを手にしたのもやっぱ...
【内容】 著者は、テクニカルライター ドキュメントを読んで理解するための入門書。の位置付けだそうです。 【話の展開】 ドキュメントを読みとくための話題が、5~6ページぐらいずつかいてあります。 【コメント】 自分の部屋で積ん読になっていたものを発掘。 これを手にしたのもやっぱり本のタイトルが気になったから。 この本は、わりとさらっと読めてしまいます。 気になるところだけ飛ばし飛ばしで気楽に読んでもよいです。 エセ三段論法の見分けかたのところは参考になった。 最後の文学作品の話題は読解の話しというよりは、著者の 趣味の話しかな?この章を読んでて、著者は好きなんだろうなぁ と感じました。こちらは作品自体の紹介にとどまらず、 作家たちの人間関係やら生き方みたいなところまで 語られていて、そこまで含めて興味深かった。 ふだん夏目漱石や芥川龍之介など読まないけど、 機会があったら読んでもいいかもね。
Posted by 


