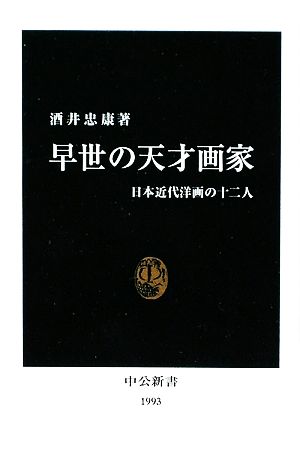
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-35-01
早世の天才画家 日本近代洋画の十二人 中公新書
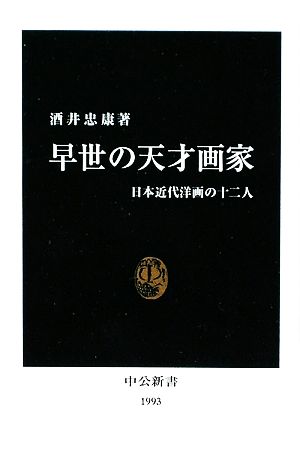
定価 ¥1,034
220円 定価より814円(78%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 2009/04/25 |
| JAN | 9784121019936 |
- 書籍
- 新書
早世の天才画家
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
早世の天才画家
¥220
在庫なし
商品レビュー
2.7
4件のお客様レビュー
取り上げられている12人の画家のうち佐伯祐三と岸田劉生くらいしか知らなかったが、フォービズム、未来派、シュールレアリズムといった現代美術の洗礼を受けた大正・昭和期の日本洋画界の一断面を知ることができる興味深い本だ。と同時に「美術評論」という日本特有のジャンルの良く言えば個性だが、...
取り上げられている12人の画家のうち佐伯祐三と岸田劉生くらいしか知らなかったが、フォービズム、未来派、シュールレアリズムといった現代美術の洗礼を受けた大正・昭和期の日本洋画界の一断面を知ることができる興味深い本だ。と同時に「美術評論」という日本特有のジャンルの良く言えば個性だが、その限界を併せて垣間見たような気もする。 「日本の近代美術は人生や生活から独立する力に欠けていた」と著者は言うが、それは日本の近代美術の限界であるとともに魅力である。そしてそうした魅力に寄りかかって書かれていることに、この本の魅力があり、またつまらなさがある。一言で言えば、あまりに文学的であり、私小説的なのだ。著者自身が自覚するように、著者の主観的な思い入れが文章に色濃く反映しているだけでなく、各章で画家の自画像を論じていることにも表れているが、画家の「内面」や「人格」に過度に密着した鑑賞は、絵画を絵画として楽しみたい向きにはうるさく感じられるだろう。評者としても高階秀爾や若桑みどりのようなアカデミックな美術史家による、作品そのものを顕微鏡でなめ回すような犀利な分析のほうが肌に合っている。 もちろん絵画というものを「知的」に「読む」ことばかりでは、これまたつまらないのも確かだ。日本の近代文学には「人格の完成」や「個性の確立」を理想とした太い水脈がある。特に「白樺派」にその傾向が強いが、ヨーロッパの文学が「大人の文学」だとすれば、それは言ってみれば自分探しの「青春の文学」だった。絵画においてそれを実践しようとしたのが岸田劉生だが、日本の近代絵画もある意味で「青春の芸術」と言えるかも知れない。著者が本書で取り上げたように綺羅星のごとく早世の画家達が出現したのも、このことと無関係ではないだろう。
Posted by 
画集は眺めるようにしています。ある程度の量を眺めたつもりです。理屈が欲しくなってきました。しかし、難しいですね。僕には、知性がないのです。それとも、なれでしょうか。後者であることを祈ります。地元の図書館で読む。興味深い本でした。ある画家を論じた部分に興味を持ちました。その画家に初...
画集は眺めるようにしています。ある程度の量を眺めたつもりです。理屈が欲しくなってきました。しかし、難しいですね。僕には、知性がないのです。それとも、なれでしょうか。後者であることを祈ります。地元の図書館で読む。興味深い本でした。ある画家を論じた部分に興味を持ちました。その画家に初めて出会ったのは石橋美術館です。衝撃的でした。それ以来、色々な美術館で、その画家の作品を眺めました。いつも面白いと思いました。意外だったのは、その研究熱心なことです。天才画家だと思っていました。違うんですね。元々、川端康成が持っていたものなんですね。正直、何故、この美術館という違和感を持ちました。そういうことなんですね。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 印象派、フォービスム、キュビスムと、新しい理論、テーマ、技法が次々と流入してきた大正・昭和期。 画家たちは強い影響を受けつつ、模倣を脱し、自らの表現の確立に挑戦する。 苦闘の果て、彼らはどのような地平に到達したのか。 『裸体美人』で知られる萬鉄五郎、『麗子像』を描き続けた岸田劉生、画像と詩魂を結合させた村山槐多、幻視の画家関根正二ら、日本の洋画史に不滅の足跡を刻んで逝った十二人の青春の光芒を描く。 [ 目次 ] 雲のある自画像-萬鉄五郎 写実の森のなかで-岸田劉生 運命の画家-中村彝 心象の回路-小出楢重 宿命の十字路-村山槐多 幻視の画家-関根正二 造形の思索者-前田寛治 半開きの戸口-佐伯祐三 抒情詩圏の画家-古賀春江 透明な響きを-三岸好太郎 呪術師の部屋-靉光 暗い歩道に立つ-松本竣介 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by 



