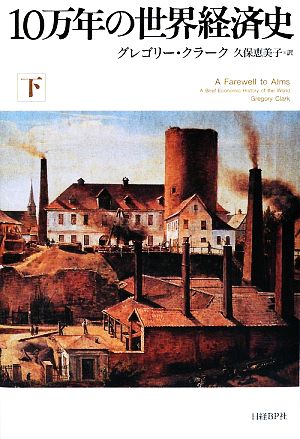
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-05
10万年の世界経済史(下)
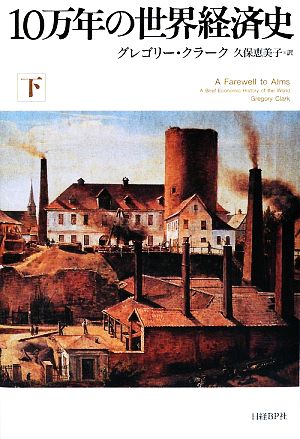
定価 ¥2,640
1,650円 定価より990円(37%)おトク
獲得ポイント15P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗到着予定:2/22(日)~2/27(金)

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/22(日)~2/27(金)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日経BP社/日経BP出版センター |
| 発売年月日 | 2009/04/27 |
| JAN | 9784822247423 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/22(日)~2/27(金)
- 書籍
- 書籍
10万年の世界経済史(下)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
10万年の世界経済史(下)
¥1,650
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.4
14件のお客様レビュー
本書は、何故産業革命が1800年代に始まったのか(人類の長い歴史の中で何故もっと早く始まらなかったのか)、何故他の地域でなくイギリスで始まったのか、そして何故国家や社会間の格差が広まったのか、この3点についての関連について解説がなされている。 第1部ではマルサス的経済モデルの概説...
本書は、何故産業革命が1800年代に始まったのか(人類の長い歴史の中で何故もっと早く始まらなかったのか)、何故他の地域でなくイギリスで始まったのか、そして何故国家や社会間の格差が広まったのか、この3点についての関連について解説がなされている。 第1部ではマルサス的経済モデルの概説がなされ、狩猟採集時代から農耕社会へ移行しても豊かにならない状況、また人口の増減が安定的に推移する状況が示される(産業革命以前までは)。何故ならば、マルサス的経済モデルでは物質的生活水準が上昇すれば各社会の出生率は上昇し、死亡率が減少し人口の増加を伴うが、これにより生活水準が下落するという循環を産んでいたからだ。 第2部では、イギリスで始まった産業革命の原因について、よく説かれている石炭産業や宗教改革、啓蒙運動ではなく、特にイギリスでは中世から比較的社会が安定していたこと、それにより中産階級的な層が何世代も生殖に成功したこと、また自然淘汰の圧力の変化人口動態の変化(富裕層のあいだでの出生率の著しい上昇)が生じたことであることを主張している。 そして第3部では、産業革命によって生じた社会・国家間の格差増大、いわゆる「大いなる分岐」は何故起こったのかを解説する。ここでは、社会的安定性が継続している地域とそうでない地域の勤勉性の違いが先進国と途上国の生産効率の比較などで説明され、その地域での勤勉な中産階級的な層が自然淘汰に勝ち残っているか否かであると結論づけている。 最後の結論には、私にはやや唐突な印象を受ける。そもそも、地域により勤勉な中産階級が沢山いる地域とそうでない地域がなぜ存在するのか。文化や習俗の違いによるのか、それとも分子遺伝学的なメカニズムによるのか。まさか後者ではあるまいし、前者であったとしても「文化や習俗にの違いによるものだから格差は仕方ない」という結論に至るわけでもないだろう。このあたりのモヤモヤとした印象が残る読後感。
Posted by 
経済成長率は、資本量、土地面積、生産の効率性のそれぞれの成長率に、それぞれの係数を掛けたものの合計で表される。近代経済においては、土地の重要性が極めて低く、資本量の係数は0.24で、効率性の向上の影響が大きい。 ポメランツは、ヨーロッパが経済の均衡状況から脱出した要因を石炭と植...
経済成長率は、資本量、土地面積、生産の効率性のそれぞれの成長率に、それぞれの係数を掛けたものの合計で表される。近代経済においては、土地の重要性が極めて低く、資本量の係数は0.24で、効率性の向上の影響が大きい。 ポメランツは、ヨーロッパが経済の均衡状況から脱出した要因を石炭と植民地に求めている。人口の多い地域から容易に到達できるところに石炭の鉱山をあったこと、アメリカ大陸で生産された食料や原料を大量に輸入することができたことで、環境的な制約を打破することができたという。 著者は、イギリスで1200~1800年に文化的、遺伝的に経済的成功者の価値観が社会全体に急速に広まったことにあると推測している。1800年の時点で、土地、労働力、資本市場の各面で、中国はイギリスとほとんど同じ状況にあったが、中産階級社会の成立に関連する指標である教育水準や利子率の水準は、イギリスはアジアの国々より優位に立っていた。 消費活動には、予算と時間の2つの制約がある。所得が増えて予算の制約が緩むと、時間の制約が重要になり、消費者の購入対象は、消費にかかる時間が短い財にシフトする。子供は必要とされる時間が極端に長いため、所得の増加に伴って子供の数が減っていく。夫婦の望む子供の数は所得とは無関係で、望まれる存命の子どもの数が常に2~3人だったとも考えられ、死亡率の低下とともに出生率も低下した。 一人当たりの所得が国によって異なる要因も、経済成長の要因と同じだが、資本が各国間を容易に移動できる世界では、資本量そのものが各国の効率性の違いに応じて決定されるため、効率性の違いが各国間の所得格差のほぼすべてを説明できる要因になっている。効率性に違いが生じたのは、主に技術を有効に活用できなかったこと、生産活動で労働力を有効に活用できなかったことである。この労働生産性の格差は、各国の生産活動における労働力の質の違いから生じたと考えられる。その質の違いの大きな要因は、その国の社会的環境に求められる。
Posted by 
産業革命はなぜ起こったのか、豊かな国と貧しい国の格差は何故なくならないのかについて論じている 上巻と同じようにデータを並べながら解説していて、下巻よりは面白いけど相変わらず難しい 貧しい国では人件費の安さから、効率を上げるために雇用する人数を増やすことができて、その結果一人当...
産業革命はなぜ起こったのか、豊かな国と貧しい国の格差は何故なくならないのかについて論じている 上巻と同じようにデータを並べながら解説していて、下巻よりは面白いけど相変わらず難しい 貧しい国では人件費の安さから、効率を上げるために雇用する人数を増やすことができて、その結果一人当たりの生産は増えないことは分かった。しかし、そこから結論の幸福度の話になったのはやや急な展開な気がした また現代の産業はミスがその後の工程に大きく影響したり、ミスした製品は取り返しがつかない状態になるものが多く、ミスが多くなるくらいなら安い人員を大量に確保することを選ぶため、貧しい国の効率は上がらないとあったが、もう少し詳しく書かれても良かったかと思う
Posted by 


