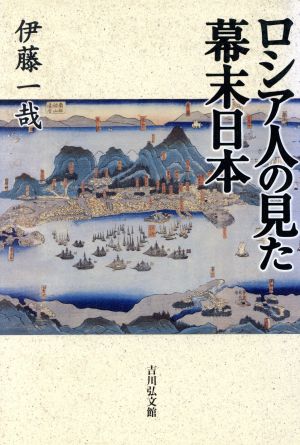
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-09
ロシア人の見た幕末日本
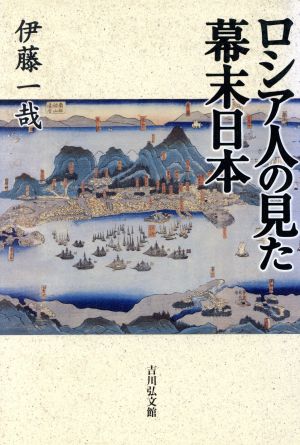
定価 ¥3,080
2,750円 定価より330円(10%)おトク
獲得ポイント25P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 吉川弘文館 |
| 発売年月日 | 2009/04/01 |
| JAN | 9784642080200 |
- 書籍
- 書籍
ロシア人の見た幕末日本
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ロシア人の見た幕末日本
¥2,750
在庫あり
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
文久の遣欧使節団の世話をした謎の日本人「ヤマトフ」は、光太夫や津太夫同様の漂流民です 幕末の年前から「日本語学校」をロシアに立てたロマノフ王朝 グローバル時代の魁ですが、幕末の日本とクリミア戦争などを挟みながら付き合ってくれました 「あ、こんな風に見ていたんだ」
Posted by 
幕末、初代駐日領事として箱館に駐在したゴシュケビッチが残した書簡などを通して、その時代の日露外交を照射した書。国内で唯一の領事館が箱館に設置された背景にはロシアの対日外交が英米仏との対抗と緊張があったこと、箱館奉行が意外(失礼!)に毅然とした外交的対応をしていることなど今まであま...
幕末、初代駐日領事として箱館に駐在したゴシュケビッチが残した書簡などを通して、その時代の日露外交を照射した書。国内で唯一の領事館が箱館に設置された背景にはロシアの対日外交が英米仏との対抗と緊張があったこと、箱館奉行が意外(失礼!)に毅然とした外交的対応をしていることなど今まであまり明らかにされてこなかった興味ある史実が多数。特に対馬占領事件(ロシア艦が対馬藩治下の対馬に上陸し軍事基地化を狙って数か月も居座った事件。1861年に勃発)を巡る箱館での交渉の経緯などは迫真。 ========== 以下は本書発行後間もなく、別のサイトに書いた書評(再録) 函館の開港前後の歴史を知る上で必読の書がタイミングよく上梓された。表紙には開港当時の函館の鳥瞰絵図を配している。 著者は北海道新聞記者伊藤一哉氏(現網走支局長)。氏がモスクワ特派員だった4年間に外交史料館などで発掘した未公開のゴシケビッチ(初代箱館領事)書簡などから得られた知見をまとめたものだ。 函館における外国の中でもロシアは特異なポジションを占める。ハリストス正教会、ロシア極東国際総合大学函館校、ロシア領事館など、現在も活動中の施設、さらにはロシア人墓地、旧領事館などの遺跡も多い。 最近は極東大の中に日本で最初のロシアセンター(ロシア情報の発信)が開設された。旧領事館建物の修復・再利用の計画も進んでいる。 それにしても、なぜ幕末の開港条約の下で、他の4か国(米・英・蘭・仏)が横浜に領事館を設置するなかでロシアのみが箱館に領事館を設置したのか。 それは私にとっても、長年の疑問であった。 1858年、開港を翌年に控えたこの年に、初代駐日領事、ゴシケビッチが函館に到着、ロシア領事館を開設してから1873年(明治5年) までの間、函館はロシアが領事館を置く唯一の都市であり続けた。 当時の政治の中心であった江戸から遠く離れた箱館に領事館をおいたことで、ロシアは日本の政治上の大変革期に外交的圧力を加えることもなく終わった。ゴシケビッチの名前も幕末の外交史の中では影が薄い。 従来、この箱館のロシア領事館設置の理由として、ロシアの東洋艦隊の寄港地としての函館の地理的条件があげられてきた。しかし この本を読むと、もっと別の理由が浮かび上がってくる。 この本の中に出てくる、「函館は(江戸に近い横浜と違って)ロシアの宗教的・文化的優位性を発揮するには好適な場所である」という当時のロシア外務省筋での議論がそれだ。 実際、ゴシケビッチは赴任にあたり、軍人のみならず、医者、神父ら多数のスタッフを帯同し、着任後も精力的に教会、学校、病院の建設を推進した。それらの努力の跡が今日の函館におけるロシアのプレゼンスには色濃く残されている。 モスクワから3か月にもおよぶシベリア縦断、そしてウラジオストックからの船旅。そうした過酷な度の先にある僻遠の地での勤務の中で、「生真面目な官僚」であったゴシケビッチが何を思い、どう行動したか、妻の病気への心配も含め、この書の随所に人間「ゴシケビッチ」の苦悩も伝わる。 圧巻は、幕末最大の対外事件ともされる露艦による対馬占領(未遂)事件の際のゴシケビッチの活動。そして、妻を同伴しての外国人として初の陸路の東北縦断だろう。 21日の道新夕刊で、東大教授の保谷氏が、この書を「幕末史の研究者には待望の一書」と賛辞を書いている。決してお世辞ではないと思う。特に函館の開港当時を知る上での貴重な同時代の証言として。
Posted by 



