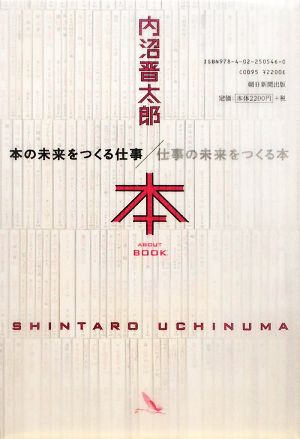
- 中古
- 書籍
- 書籍
本の未来をつくる仕事/仕事の未来をつくる本
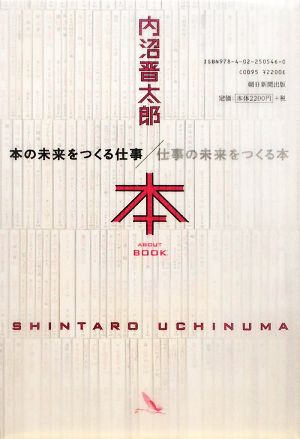
定価 ¥2,420
¥770 定価より1,650円(68%)おトク
獲得ポイント7P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞出版 |
| 発売年月日 | 2009/03/19 |
| JAN | 9784022505460 |
- 書籍
- 書籍
本の未来をつくる仕事/仕事の未来をつくる本
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
本の未来をつくる仕事/仕事の未来をつくる本
¥770
在庫なし
商品レビュー
4.2
50件のお客様レビュー
ブックコーディネーター内沼晋太郎さんが、2009年、28歳の時に書かれた本。 右から開くと「本の未来をつくる仕事」。左から開くと「仕事の未来を作る本」だ。 「仕事の未来をつくる本」では、1980年生まれ、「就職氷河期」を経験し、「ロスジェネ」と呼ばれた世代の著者だが、会社の仕事が...
ブックコーディネーター内沼晋太郎さんが、2009年、28歳の時に書かれた本。 右から開くと「本の未来をつくる仕事」。左から開くと「仕事の未来を作る本」だ。 「仕事の未来をつくる本」では、1980年生まれ、「就職氷河期」を経験し、「ロスジェネ」と呼ばれた世代の著者だが、会社の仕事がどうしても合わず、2ヶ月で退職して、そこから新たな生きる道を模索した話。 ポイントは「自分のやりたいこと」と「お金を貰うこと」を分けて考えることということ。そして、著者が進めているのは「お金をら貰う仕事」をしながら「お金を貰わない」仕事もするべきということ。何故かというと「お金を貰う仕事」は初めはそれが「やりたい事」であっても、ビジネスとして加速するうちに「やりたい事」=「お金を貰う事」に変わって行ってしまう可能が高いから。やりたい事は「お金を貰わない仕事」としてやったほうが、自由度が高く、そしていつかそれが「やりたいことをやってお金まで貰えてしまう仕事」にもなりうるから。そしてこの「お金を貰えない仕事」はボランティアとかではなく「仕事」として行わないとダメだという。 ちょっと分かりにくいのだけれど、実際、著者は様々なユニットを組んで、本に関する斬新なプロジェクトを次々行っておられる。 その実績を紹介したのが、右側からの「本の未来をつくる仕事」。 あるテーマの元に本を展示しながら...(それも展示の仕方そのものがすごくアーティスティック)、遊びながら売る。“遊び”という点では、斬新にも本を切ったり、書き込んだりということもあって、そういうのはイヤなんだけど…。でも、書店から出版社に返品される本は年間5億冊もあり、そのうち1億冊も断裁処分になるなら、それよりはずっと有意義と言われれば、そうかもしれないが。 以下、共感出来た言葉 「出版も不況だからといって、なんだか同じような造本のものに、ただテキストを流し込みました、みたいな本が続々溢れてきている。当然コストは安く上がるんだけれど、そういうものはもうすぐ、デジタルで十分になる。…いま、できるだけ本らしい本、残るべくして残る本をつくろうと考えるなら、プロダクトとして気の利いたものにするべきだ。それは、お金をかけるということではなくて、コンテンツに合わせて、もっとも相応しい形でプロダクトにする。」 「本を面白くする、あるいは面白がる人を増やすには!インターネットの面白さを本に還元するのではなく、本の面白さをインターネットに還元するようなことをしなければならない。僕は買った後の本を楽しく読むためのサービスをそろそろもっと盛り上げていくべきだと思っている」…ブクログがそうですね。家の本棚には入りきらず、はみ出たり、手放したりですが、読んだ本と聴いた音楽で出来た仮想本棚が美しくて、宝物です。
Posted by 
”Dainさんブログで「スゴ本」として紹介。両A面の一冊。 まずは「仕事の未来をつくる本」から読む。→読み終わった 続いて「本の未来をつくる仕事」を読み始め。→読み終わった --- T: P: O: --- <About WORK> ・「お金をもらわない仕事」と「お金をもらう仕事...
”Dainさんブログで「スゴ本」として紹介。両A面の一冊。 まずは「仕事の未来をつくる本」から読む。→読み終わった 続いて「本の未来をつくる仕事」を読み始め。→読み終わった --- T: P: O: --- <About WORK> ・「お金をもらわない仕事」と「お金をもらう仕事」の両方をやる (p.014) ・古くからの友達相手でも、積極的にあたらしくはじめた「お金をもらわない仕事」について説明しましょう。(p.20) ・「なんでこういうものがないんだろう?あったら面白いのに」と思うようなものをみつけて、それが社会貢献にならなくても、ビジネスになりそうになくても、ただ、「あったら面白い」という目的だけで、ひとつの活動として、自分で勝手に立ち上げてしまうことです。 #SE×図書館司書とか?(p.23) ・その全貌を、まずは表面的な知識としてでかまわないので、なるべくきちんと勉強することです。(p.32) #本屋業界×児童教育業界 ★仕事マップ (p.46) お金をもらう仕事(もらうための、もらえてしまう)・お金をもらわない仕事×時間でお金をもらう仕事・成果でお金をもらう仕事 #このマップ、おもしろそう。つくってみよ?! ・「時間」は有限ですが、「成果」は無限です。(p.47) ・何度か誰かにパクられたくらいになってやっと、自分で「あたためたほうがいいアイデア」と「話したほうがいいアイデア」の区別がつくようになるのではないか、と思っています。(p.63) ・自分に合うコミュニティを持ったバーや飲み屋を見つけること (p.71) ・自分のリックスをできるだけ人に覚えてもらいやすいようにしておく(p.72) <About BOOK> ・WRITE ON BOOKS (p.16-17) 本というものは、印刷された段階ではマスプロダクトであるが、何かしらの書き込みが加わった時点で、世界に一冊しか存在しないオリジナルなものとなる。 #書き込むことで商品価値があがるかも、という実験。ここ MediaMarker もそうなんだろうね。 #★家にある書き込みバリバリ本、売ることできるのだろうか…。 ・encounter. (p.24-) #2回ほど遊びに行った ・honnobutai(p.52) 本に登場する舞台を地図上にマッピングして共有するWebサービス http://honnobutai.org/ ・自分の古本を自らの手で売るという行為はまた、独特の楽しみがある。そしてふつうは、なかなかそういう機会はない。(p.77) ★本に関する3つの世代(p.79-80) 「本を読むのがあたり前の世代」 「本を読まなきゃいけないとどこかで思っている世代」 「本を自分とは関係ないと思っている世代」 ・本のリズム、暮らしのテンポ 角田光代さん 「本のリズムと自分の生活のリズムが合わないからに違いない」 ・本屋自体に強い「伝えたい」メッセージがまずあって、それを中心に本の品揃えが構成されていて、そこにあてはまらないものは置かない、などという本屋は少ない。(p.87) ★たとえばそこに、そのホテルのブランドと顧客層に合わせて選ばれた良書が詰まった、大きな本棚があったらどうだろう。(中略)読みかけで眠ってしまったら、冷蔵庫のドリンクのように、チェックアウト時に買うことができてもいい。(p.92) #これ、おもしろい!! ・ぐっと我慢してぜひ、あなたが一番好きで、なくなると困る本屋で、なるべく買うように心がけましょう。という運動を、ぼくは広めようとしています。(p.94) #賛成!! ・本は選びにくいものだ 買う前の段階で、人に入ってくる情報が多いから。(p.101-100) ・インタビュイーを募集して「ぜひ自分をインタビューしてほしい」という人が集まらない ・インタビューには批評が無い。()”
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
どのジャンルの棚に置かれるのか、あるいは二つのジャンルの棚に置かれるのかを実験するためにあえて本についての本と仕事についての本の二つが合体した本。デザインが面白い。 本についての方では、内沼さんの仕事の実例から、本ってこんな使い方があるんだと視野が広がった。 また、「本を自分とは関係ないと思っている世代」が出現しており、業界不況に拍車をかけているとの危惧から、その解決の糸口として子供、そしてその親が本を面白いと思ってもらえるような工夫が必要なのではないかとの話に確かに思ったのでもっと考えたい。 仕事についての方では、お金にならない仕事の重要性が説かれている。お金をもらうための仕事とバランスを取りながら徐々に実績と実力をつけていき、お金をもらえてしまう仕事にシフトしていく戦略には希望が持てる。と同時に時間でお金をもらう仕事から成果でお金をもらう仕事へシフトしていくことで時間の自由を得ることができる戦略を学べた。この戦略で行くとなにものかになること、よくわからない人になることを実現でき、さらに面白い仕事を呼び込み、仕事が楽しくなるという良い循環が生まれる。 それから、常連の店をつくること、都心の近くに住むメリットの話もなるほどなと思った。
Posted by 

