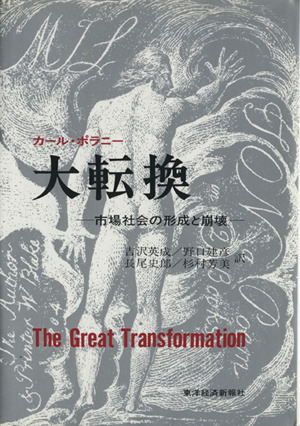
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-12
大転換 市場社会の形成と崩壊
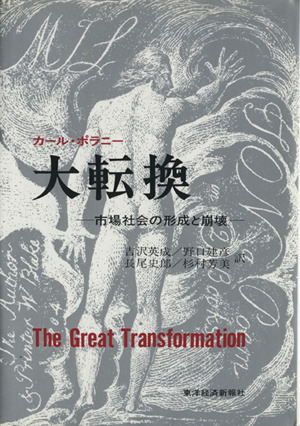
定価 ¥3,960
2,695円 定価より1,265円(31%)おトク
獲得ポイント24P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 1975/04/01 |
| JAN | 9784492370292 |
- 書籍
- 書籍
大転換 市場社会の形成と崩壊
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
大転換 市場社会の形成と崩壊
¥2,695
在庫なし
商品レビュー
4
3件のお客様レビュー
「産業革命にともなう大きな悲劇は、資本家の利潤追求の無情さ・貪欲さによってもたらされたものでなく、統制されないシステムである市場経済の生み出す社会的惨害によってもたらされたのである。」 と、翻訳されている。 文章が分かりにくいけれど、ここでポラニーが見落としているのは、人間の...
「産業革命にともなう大きな悲劇は、資本家の利潤追求の無情さ・貪欲さによってもたらされたものでなく、統制されないシステムである市場経済の生み出す社会的惨害によってもたらされたのである。」 と、翻訳されている。 文章が分かりにくいけれど、ここでポラニーが見落としているのは、人間の意識状態の未熟さである。 どんなに完璧に思えるシステムを持ち込んだとしても、所詮道具でしかない。 それを使う人間の意識状態によって、毒にも薬にもなるのが道具であり手段である。 もしも当時の民衆の意識が、その強欲と依存性を包み込めていたら、その生産による利益を十分に活用してより良い道具を導き豊かな共生社会を育てただろう。 利益を時空間に逆らって力尽くで奪って溜め込んでいる歪んだ重さと違って、利益を活用していれば複利のように物質面だけに限らず精神面の幸福感をもたらしていただろう。
Posted by 
目次 著者序言 序文 R・M・マッキーバー 第一部 国際システム 第1章 平和の百年 第2章 保守の20年代、革命の30年代 第二部 市場経済の勃興と崩壊 Ⅰ 悪魔のひき臼 第3章 「居住か進歩か」 第4章 社会と経済システム ...
目次 著者序言 序文 R・M・マッキーバー 第一部 国際システム 第1章 平和の百年 第2章 保守の20年代、革命の30年代 第二部 市場経済の勃興と崩壊 Ⅰ 悪魔のひき臼 第3章 「居住か進歩か」 第4章 社会と経済システム 第5章 市場パターンの進化 第6章 自己調整的市場と擬制商品――労働、土地、貨幣 第7章 スピーナムランド――1795年 第8章 スピーナムランド法以前と以後 第9章 貧民とユートピア 第10章 社会の発見と政治経済学 Ⅱ 社会の自己防衛 第11章 人間、自然、生産組織 第12章 自由主義的教義の誕生 第13章 自由主義的教義の誕生(続)――階級利害と社会変化 第14章 市場と人間 第15章 市場と自然 第16章 市場と生産組織 第17章 損なわれた自己調整機能 第18章 崩壊への緊張 第三部 トランスフォーメーションの進行 第19章 大衆政治と市場経済 第20章 社会変化の始動 第21章 複合社会における自由 原典に関する注解 ⅰ バランス・オブ・パワー――政策、歴史法則、原理、システムとして ⅱ 平和の100年 ⅲ 断ち切られた黄金の糸 ⅳ 第一次大戦後の振子の揺れ ⅴ 金融と平和 ⅵ 「社会と経済システム」への文献ノート抜粋 ⅶ 「市場パターンの進化」への文献ノート抜粋 ⅷ スピーナムランドについての文献 ⅸ スピーナムランドとウィーン ⅹ ホイットブレッド法案も悪くない ⅺ ディズレーリの「二つの国民」と有色人種問題 ⅻ 補注・救貧法と労働の組織 訳者あとがき
Posted by 
ポランニーが生涯を通じて追求したテーマは、200年の歴史を持つ近代経済学が前提としてきた枠組み―その人間観から形式に至るまで―が人類の歴史の視野から見て、非常に特殊なものである、ということだった。 近代経済学が追求してきた市場社会の自己調整システムは、社会制度を市場に従属させ...
ポランニーが生涯を通じて追求したテーマは、200年の歴史を持つ近代経済学が前提としてきた枠組み―その人間観から形式に至るまで―が人類の歴史の視野から見て、非常に特殊なものである、ということだった。 近代経済学が追求してきた市場社会の自己調整システムは、社会制度を市場に従属させるほど強力なものだったが、19世紀のヨーロッパはまさしくそのような市場社会であった。経済学はその枠組みを使用し、普遍化し人類とその歴史を市場社会のまなざしから眺めていたのである。 それに対してポランニーは、マリノフスキーやトゥルンバルトといった人類学の研究を土台に、それがまったくのフィクションであることを突きつけたのである。彼の言葉を使えば、市場社会が登場する以前の多くの社会では、経済は「社会に埋め込まれていた」のであり、市場社会のように、「社会から突出した経済」が逆に社会を従属させ、自己調整的にふるまうという事態こそが、人類史においてまったく新しい出来事だったのだという。 19世紀には国家を含む何者も市場メカニズムを犯してはならないという自由主義の思想が功利主義的な思想とともに絶対視されていた。ところが実際の市場社会の内部では、本来市場によって決定されるにはそぐわない人間(労働)や自然(土地)が擬制として商品化されていため、理想とは裏腹に混乱と悲劇が引き起こされていた。ポランニーは市場の破壊的側面を、W・ブレイクの詩を引用して「悪魔の碾き臼」と好んで揶揄している。したがって、イデオロギー的には自由放任であるはずの市場は、社会の要請によって規制を要請され、世界の方向性はその間をめぐって揺れ動いていたのである。 そして20世紀の初頭に入り、自己調整的な市場が成立するための根本的な条件が相次いで破られ、ついに100年の自由主義イデオロギーのユートピアが転換期を迎えるのである。金本位制の崩壊、ソ連の計画経済、アメリカのニューディール、そしてファシズムの出現は、いずれも市場社会の根本的な矛盾に由来する解決案だった。 以上が1944年に出版され、それまで30年間の研究が結集したと評されるポランニーの主著、『大転換(The Great Transformation』の趣旨である。 http://www.geocities.jp/persypersimmon/politic_economic/Kpolanyi00.htm
Posted by 



