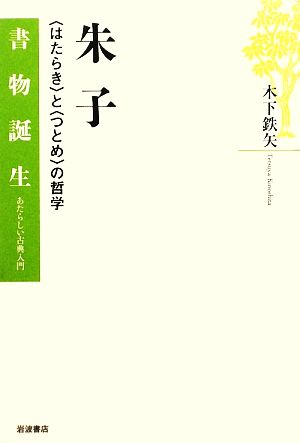
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1220-03-02
朱子 “はたらき"と“つとめ"の哲学 書物誕生あたらしい古典入門
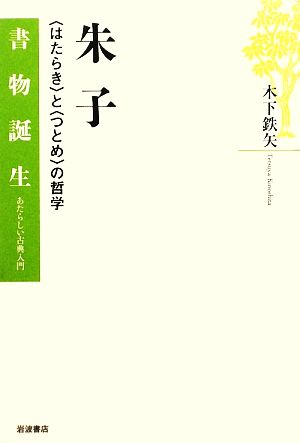
定価 ¥2,310
1,430円 定価より880円(38%)おトク
獲得ポイント13P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2009/01/21 |
| JAN | 9784000282871 |
- 書籍
- 書籍
朱子
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
朱子
¥1,430
在庫なし
商品レビュー
3.3
4件のお客様レビュー
本書は第一部で朱子の人生とその生きた時代を外観し、第二部で著作を読み解くという標準的な入門書の体裁をとりつつ、第二部の解釈では第一部の内容を無視するという大変奇異な内容の入門書となっている。というのも、本書で実践されているものは「朱子学」そのものだからだ。皮肉にも、プロローグに...
本書は第一部で朱子の人生とその生きた時代を外観し、第二部で著作を読み解くという標準的な入門書の体裁をとりつつ、第二部の解釈では第一部の内容を無視するという大変奇異な内容の入門書となっている。というのも、本書で実践されているものは「朱子学」そのものだからだ。皮肉にも、プロローグにおいて「『朱子』の語と尊崇されてきた言語テキストを『朱子学』の観点から読むのではなく、一人の人間として時代と歴史の中に生死した『朱熹』の側から捉え直す」と宣言されているにもかかわらず、である。著者は根本的に誤解しているようだが、朱子学とは朱子の思想に沿って儒学を実施するという「方法」の問題であって、「朱子学」として固定化された解釈の「内容」の問題ではない。いかに朱子の思想を歴史に沿って再構築したとても、儒学を行うかぎりそれは「朱子学」であることに変わりない。朱熹のテキストが「古典」になりうるとしても、「朱子学」が現代において価値を持ちうることは決してありえない。著者の試みは最初から達成し得ないのである。以下、本書が「朱子学」であることを示す。 『中庸』における朱子の「命猶お令のごときなり。性即李なり」という注釈について、著者は、「朱熹は董仲舒の『命なるものは天の令なり』の持つ重大な意義を程頤の『性は即ち理なり』によって完璧に受け止め、成就したのである」(102ページ)とする。ここで著者は「令」を『呂氏春秋』によって「いつ、誰にということがパーソナルには設定されていない「きまり」、あるいはそのような「きまり」を公開するという形でのオープンな指示」(106ページ)の意味ととる。さらに、これを「令」(りょう)に比定して北宋時代の「天聖令」を引き「令」は職務条項であるとした上で、「性」に結びつけようとする。一見したところ自然な議論であるが、董仲舒は前漢の人物、『呂氏春秋』は戦国時代の成立、「天聖令」は北宋時代の成立とはいえ現存していない唐の時代の「令」の内容を受け継ぐものであり、これらは全く異なる時代のものであるにもかかわらず、なんの留保もなく同列に論じられる。一方で、第一部における議論では、朱子の上の解釈はその時代感覚によるものだとしているのである(64ページ等)。これはいかにも不自然である。この違和感の理由は『朱子語類』のが次の通り引用されることで明白となる(111ページ)。「『心』というのは、おおづかみには官人のようなものだ。『天命』というのは、だから君主の命だ。『性』は職事と同じ」。なんのことはない。朱子の発言を他のテキストから「解釈」によって導き出したにすぎないのである。「儒学」というのは、自分の言いたいことをそれ以前のテキストの中に捏造することによって翻って根拠とすることに他ならない。ここでは朱子の解釈を見出しているのだから、これこそ「朱子学」そのものである。 「格物」の「物」を「事物の理」と読むのは朱子の完全に創作であるが、これをさらに著者は天理(=「職務条項」)の息づいている「いのち」、その「いのち」の「行為」、「行為」を行う「生き物」と独自に解釈し、その根拠を『礼記』に対する後漢の鄭玄や唐の孔穎達の注釈、後漢の『説文解字』、『論語』に求める。「事」と「職」については、第一部においても『荀子』を引用して結びつけている。一方で、上述の「令」の解釈と同様に、「理」と「職」が結びつけて理解されるのは、「『債務』と『職務』に通有する『つとめ』の感覚が国家公務員の中に育ち、さらに広く『つとめ』の感覚が支える信用秩序創出の可能性が育ちつつある時代」(64ページ)に朱子が生きたためであるとする。これも明らかに矛盾しているのであって、つまりは著者の「解釈」を古典に勝手に読み込んでいるのである。 何故こんなことが起こりうるのかを考えるに、おそらく著者は、朱子には古典を字義通り読む意図など(少なくとも客観的には)これっぽっちもなかったということを忘れているのだ。つまり、朱子の思想を解釈するにあたって、その根拠としている古典を訓詁することは全く無意味であるにとどまらず、かえって朱子の学問をそのまま繰り返すことに他ならない。それは即ち朱子学なのである。
Posted by 
朱熹のテクストを読みなおすことを通じて、既存の朱子学のイメージをくつがえすような、朱熹の本当の思想を明らかにする試みがおこなわれています。 本書は二部構成になっており、第一部では朱熹の生涯と彼の生きた時代についての解説にあてられています。とはいっても、概説的な時代状況の説明では...
朱熹のテクストを読みなおすことを通じて、既存の朱子学のイメージをくつがえすような、朱熹の本当の思想を明らかにする試みがおこなわれています。 本書は二部構成になっており、第一部では朱熹の生涯と彼の生きた時代についての解説にあてられています。とはいっても、概説的な時代状況の説明ではなく、社倉にかんする朱熹の政策提言に焦点をあてています。その背景に著者は、皇帝個人を中心とするパーソナルな人間集団として国家秩序を理解するか、それとも職務と権限というパブリックな機能をもつシステムとして理解するかという対立が当時の中国において存在していたことを指摘します。 こうした議論は、朱熹のテクストを読み解く第二部における議論と密接につながっています。著者は、朱子学における「理」が、国家の実現するべき「事業」を秩序づけて官吏に分担する「職」のあり方と相同的な関係にあることを明らかにしています。こうしたテクストの解釈を通じて著者は、封建的な身分秩序を人びとに強制してきた悪しきイデオロギーであるとする朱子学のイメージを塗り替え、生き生きとしたものとして現代によみがえらせようとしています。 著者のこれまでの研究成果にもとづいた内容で、朱熹の思想を朱熹そのひとのテクストにもとづいて解釈する著者の思索の現場に居合わせているような臨場感をおぼえました。
Posted by 
[ 内容 ] 朱子学は封建的な大義名分論としてイメージされるが、「朱熹」その人は実は朱子学者ではない。 本書は、南宋という時代を生きた朱熹という一人の人物の生涯をたどり、そこに交錯する歴史の現場に立ち会いつつその思考の核心を捉える、新たな「読み」の実践である。 職・理・事・命・性...
[ 内容 ] 朱子学は封建的な大義名分論としてイメージされるが、「朱熹」その人は実は朱子学者ではない。 本書は、南宋という時代を生きた朱熹という一人の人物の生涯をたどり、そこに交錯する歴史の現場に立ち会いつつその思考の核心を捉える、新たな「読み」の実践である。 職・理・事・命・性などの重要語をめぐる朱熹の注解に肉薄するとき、彼が鋭敏な眼で現実を見据え、時代の課題に向き合い、生涯を賭けて彫琢した哲学的ヴィジョンが姿を現す。 [ 目次 ] 第1部 書物の旅路―朱熹、その生と思索の現場から(朱熹の生涯;朱熹の生きた時代;「職」と「理」) 第2部 作品世界を読む―『四書集注』に見る哲学的ヴィジョン(「天命之謂性」の注解を読む―『中庸章句』より;「明明徳」の注解を読む―『大学章句』より(1) 「格物」の注解を読む―『大学章句』より(2)) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by 



